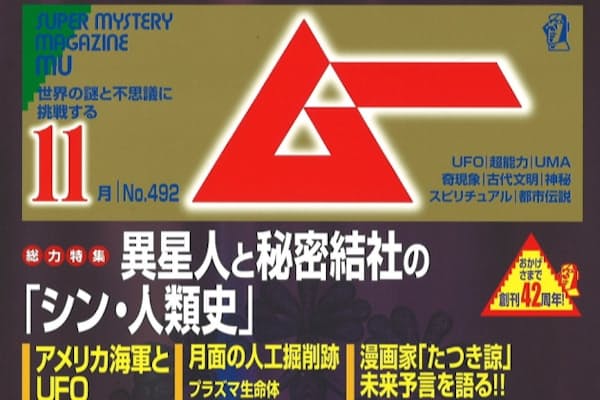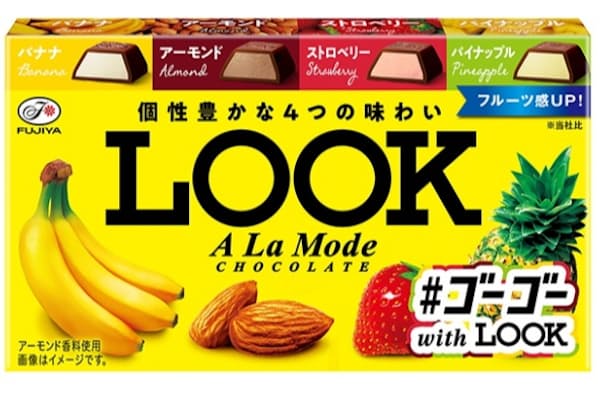井村屋の肉まん・あんまん 「中華まん」ではなかった!?
井村屋「肉まん・あんまん」(上)
ヒットの原点
井村屋の「肉まん・あんまん」シリーズは家庭用の売り上げが伸びている
冬の風物詩的な商品となっている「肉まん」や「あんまん」。実はアツアツの蒸したてを店頭で食べられるよう、スチーマーで蒸して提供する方法を考案し、最初に売り出したのは、津市に本社を置く食品メーカーで、氷菓「あずきバー」でおなじみの井村屋だ。「冬のファストフード」として日本人を温めてきた井村屋の「肉まん・あんまん」はいつ誕生し、どうやって広まったのか。秘密を探った。
冬のイメージが強い肉まん・あんまんだが、コンビニエンスストアの店頭で売り始められるのは8月半ばのお盆過ぎからだという。近年は暑い夏が10月ごろまで長引く傾向にあるが、店頭のスチーマーはまだ残暑のきついうちから動き出す。
需要期の冬を経て年を越し、毎年3月には終売となるのが通例だ。ところが、スーパーなどで売られる冷凍品は新型コロナウイルス禍が広がった20年以降、通年で売る小売店が徐々に増えている。「巣ごもり消費」の変化は肉まん・あんまんにも及んでいるようだ。
「コロナ禍で家庭内での消費が増えた影響もあったのでしょうか、夏でも売れる商品になりつつあります。これまではコンビニが8割、スーパー販売の家庭向けが2割でしたが、コロナ禍以降は家庭向けが前年同期比で数ポイント上昇しました」。井村屋の花井雅紀・開発部長にコロナ禍以後の販売状況を聞くと、こんな意外な答えが返ってきた。
井村屋は肉まん・あんまん商品を「中華まん」とは呼ばない。実際、公式ウェブサイトの肉まん・あんまん商品ページ内に「中華まん」の文字はない。
いわゆる中華まんは日本では1927年に「新宿中村屋」の屋号でしられる中村屋が「天下一品 支那饅頭(まんじゅう)」という名で発売したのが最初とされる。あくまで中華の味がベースで、あんまんは中身の餡(あん)もゴマがメインだった。
しかし、井村屋はこの中華風をなぞらなかった。「日本風のしょうゆベースの味付けにした肉まんと、和菓子を思わせる『アズキのあん』で作ったあんまんを商品化したのが井村屋でした」(花井氏)。
井村屋に限っていえば、「肉まん・あんまん」は中華まんではなく、「和中折衷」のオリジナルフードだ。もともとアズキに強みを持つ井村屋らしいアレンジともいえる。
和風のイメージがある井村屋だが、米国生まれのパイレストラン「アンナミラーズ」も運営していて、なかなか懐が深い。国内唯一の店舗は東京・品川で営業を続けている。