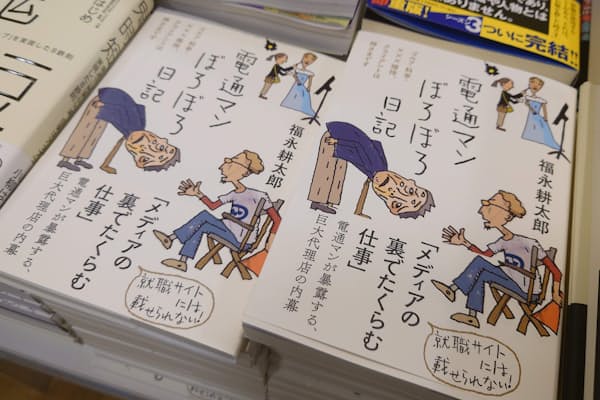「大辞職」に揺れるアメリカ 仕事も人生も見つめ直す
海外便(1)
キャリアコラム
飲食店街で増える求人の張り紙(ワシントン、高橋恵里撮影)
年功序列の崩壊、ジョブ型雇用導入、転職の一般化など日本のビジネスパーソンを取り巻く環境は目まぐるしく変わっています。日本の雇用慣習は海外から見て特殊だとも言われていますが、海外の実情はどうなっているのでしょうか。キャリアコラム「海外便」では海外の就職やキャリアにまつわる現地事情をお届けします。初回は、「大辞職」に揺れる米国の街角から。
◇ ◇ ◇
「私たち全員やめます。ご迷惑をかけてすみません」
この夏、米国中西部にあるハンバーガーチェーンの看板に掲げられた店員からのメッセージがネットで話題になった。人手不足など働く環境への不満が募り、店長をはじめほとんどの従業員が辞めたことが背景にあったようだ。退職者が続出し、一時的な閉店や時間短縮に追い込まれる飲食関連の店舗はほかにも相次いでいる。
「スタッフに優しく接してください」の張り紙
「Great Resignation(大辞職)」――。最近、米国ではこんな言葉がよく聞かれるようになった。この数カ月、自ら仕事を辞める人の数が記録的な水準に高まっているためだ。労働省の統計によると、4月に過去最高の399万人に達したあと、9月にはさらに増えて443万人に上った。新型コロナウイルス感染症の拡大前の2019年は毎月350万人程度で推移していたので、一気に1~2割も増えたことになる。
業種別にみると、目立つのはやはりホテル・外食と医療関連だ。人と接する仕事でコロナ感染が心配なのに加え、マスク着用などをめぐって客から暴力や暴言を受けるのが怖いという声も聞かれた。レストランや飛行機内でのトラブルが数多く報道されているので、無理もないことだと思う。飲食店はもともと低賃金や休みが少ないなど待遇が悪いとされていて、そこにコロナが追い打ちをかけた格好だ。
「burn-out(バーンアウト=燃え尽き)」も「大辞職」のもう1つの要因とみられている。パンデミック(世界的大流行)で健康や将来への不安が強まるという下地があるなか、多くの患者が押し寄せた医療機関はもちろん、在宅勤務で仕事とプライベートの境界があいまいになった人たちも、心身に過大な負担を感じている。マッキンゼーが4月に発表した調査では、49%の人が何らかの「燃え尽き」を感じていた。
働き手が減り、深刻な人手不足が広がっている。筆者の住むワシントンDCも無縁ではない。
自宅マンションの受付係として平日昼に働いている女性が、夏ごろから週末も働いているのに気づいた。最初は夏休みシフトなのかと思っていたが、秋になってもずっと働きづめだ。週末の担当者が辞めた後、後任が見つからないのだという。金曜夜の勤務の翌朝、また受付に座っていることもある。いつも笑顔で対応してくれるが、疲れがたまっていないはずはないだろう。残った人たちへのしわ寄せが心配だ。夏に訪れたカリフォルニア州のファミリーレストランでは「スタッフが不足しています。優しく接してください」という張り紙を見かけた。
待遇改善迫られる企業 「仕事の大再評価時代」
トラック運転手の不足で物流も滞るなど、マイナスの影響は大きい。一方で、働き手の立場から見れば、労働環境や仕事に対する考え方を見直すきっかけになるとの期待もある。
実際、低賃金が敬遠された外食産業をはじめ、賃上げが相次いでいる。労働省の統計によると、エンターテインメントや飲食を含む娯楽・ホスピタリティ産業の一般従業員の平均時給は今年に入って急上昇し、9月に16.7ドルと1年前に比べて2ドル近くも上がった。