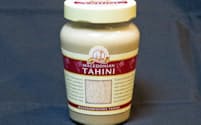賀茂ナス、宇治茶… 京都伊料理店のティーペアリング
イタリア美味の裏側(17)イタリア食文化文筆・翻訳家 中村浩子

日本で今一番勢いが感じられ、未来も見据えているイタリア料理店は、京都市の「cenci」(チェンチ)だろう。「ミシュランガイド京都・大阪2022」で初めて一つ星を獲得。今年3月に発表された「アジアのベストレストラン50」では、昨年の91位から43位に大躍進した。坂本健オーナーシェフは、農林水産省料理人顕彰制度である「料理マスターズ」ブロンズ賞を2019年に受賞している。「cenci」の昼のコース(サービス料込み1万2100円)をティーペアリングでいただき、日本を代表するイタリアンについて、地域発信とサステナビリティーの観点で考えてみた。
まず食前酒代わりのティーは、山本甚次郎(京都府宇治市)の碾茶(てんちゃ:抹茶にするための茶)「あさひ」の新茶を水出し冷茶にしたもの。新茶であることと、冷えすぎない温度での提供は、清涼感をもたらし、汗を引かせてくれる。同社は100年以上続く茶の生産者であり、日本最古の碾茶乾燥炉をもつ茶製造販売所でもある。

前菜は、日本人唯一の公認パルマハム職人、BON DABON(ボンダボン)の多田昌豊さんのペルシュウ(パルマ方言で生ハム)をのせたひと口塩味チェンチと、ガスパチョの組み合わせ。希少な国産ペルシュウを使った料理は「cenci」の看板メニューの一つで、今回は岡山県の吉田牧場のリコッタと廃棄ホエイ(乳清)を自家製モッツァレッラに詰めたブッラータ(本来は生クリームを中に入れる)やジャガイモのペースト、ユズコショウをチェンチの土台に詰め、生ハムをのせた。ガスパチョは赤玉ネギ、赤パプリカ、セロリ、キュウリを乳酸発酵させ、トマトを加え、調味料は塩だけ。
坂本シェフは大学在学中に英ロンドンへ短期留学し、イタリア人がスーパーで仕入れた食材でつくったカルボナーラにいたく感動した。そのことが、坂本シェフを料理の道に進ませた。店名は、そのイタリア人が働いていた古着屋の名前「cenci」(ぼろ切れの意)と、トスカーナの揚げ菓子名の両方の意味から来ている。「京都で生まれ育ったので、時間をかけてきちんとつくる物に大切な価値があると思っています。それは、高級食材とは違う価値観だと思います」と坂本シェフはいう。その価値観は、100年続く宇治の茶生産者の茶葉や、新潟県産豚24カ月熟成の国産生ハムを選ばせる。
塩と酸とオリーブオイルで素材の味引き出す

次は、年に3回は異なる調理法で出すというアユ料理。滋賀県のアユの名産地、高島市の小アユに塩を振って軽くローストし、骨をはずし、身はパン粉揚げにした。水切りヨーグルトと発酵レモンとディルのソースでいただく。アユの骨煎餅(せんべい)は油で揚げた。上にすりおろしたのは、吉田牧場の長期熟成ハードチーズのマジャクリ。風味はコンテというチーズに似る。アユの肝とロメインレタスの苦味、ソースの酸味を楽しみ、カリッとした骨煎餅との食感の違いも楽しい一皿だ。ティーペアリングはネパールの発酵度の低いダージリン紅茶で、強すぎない香りが料理に補われる。
「(大卒後に初めて働いた)『イル・パッパラルド』(京都市)の料理長だった笹島保弘シェフから言われたのは、『素材にちゃんと塩を当てなさい。ぼんやりした料理はあかん』ということでした。そこにヴィネガーやレモンなどの酸を振ると、おいしくなるというその塩梅(あんばい)を学びました。その後、塩と酸とオリーブオイルの使い方でどう素材の味を引き出すかがイタリア料理の鍵だということに気がついたんです」(坂本シェフ)
イタリア料理の酸というとヴィネガーやレモンが基本だが、野菜や果物、乳などの発酵による、奥行きのある酸味が「cenci」の料理には生かされている。「飯尾醸造(京都府宮津市)の『富士酢』で発酵のおもしろさに気づいたのがきっかけです」と坂本シェフは話す。

魚料理が続いて、北海道産の伝助アナゴの炭火焼きに、ローストしたトマトを添えた料理が登場。新ショウガとエシャロットの酢漬け、クレソン、パクチー、カルダモン、クミン、コリアンダー、フェヌグリークというスパイスを混ぜたものが、ロースト後に冷ましたトマトにのる。舌に後味として残るエスニックな風味は、ティーペアリングの台湾阿里山茶で洗い流される。
日本料理の技法をふんだんに取り入れる

その後はグリーンアスパラガスとアオリイカの料理で、さらに続くのは、イタリア中部の料理、ピアディーナから発想したクレープ料理。クレープ生地は、千葉県のイマフンという生産者が自家採種するイタリアコムギの全粒粉と北海道の薄力粉、オーツミルクを混ぜたもの。クレープにのるのは、素揚げした賀茂ナスとホワイトコーン、アマランサス、シュンギク、バジル。アーリオ・エ・オーリオ(ニンニクとオリーブオイル)風味のパン粉とアーモンド、そして揚げエシャロットも入っている。ソースにはホワイトコーンのピュレ、バジルペースト、ホワイトバルサミコが使われている。
これらの具を巻いて食べるクレープは、日本人の誰もが好きなモチッとした食感だ。これに合わせたのは、エチオピア産とエクアドル産の豆による焙煎の浅い水出しコーヒー2種。料理とのコーヒーペアリングはまだ珍しく、料理の風味が深みを帯びるのを感じた。
この後に、高い熟成技術をもつサカエヤ(滋賀県草津市)が80カ月熟成させた鹿児島経産牛の熟成肉、ニラとサザエのパスタ、北海道の放牧牛乳などを使ったデザート3品と続いた。

実は、坂本シェフにはイタリアでの料理修業や現地のリストランテ勤務歴はない。「笹島シェフが輸入野菜に疑問をもったことから、賀茂ナスなど日本の食材を使って日本料理と融合させる役割がありました。笹島シェフが独立開店した『イル・ギオットーネ』の本店料理長時代には、日本の食材によるイタリア調味料をベースにしたイタリア料理の表現を任せていただいたのが大きかったと思います。日本料理の技法は『露庵 菊乃井』にしょっちゅう食べに行って、カウンターで料理長に話を聞いたり、菊乃井で修業された『てのしま』(東京・港)の林亮平さんと情報交換をしたりして学びました。『cenci』開店時には、縁があった生産者の思いを伝え、素材をしっかりと出していく、京都で育った自分がおいしいと思うものを、自分らしく出していくと決めたんです」と坂本シェフは明かした。
日本料理の技法をとり入れるだけでなく、陶器やガラス器やカトラリーも、地元の作家や骨董・アンティーク店の品を好んで使う。たとえば、グリーンアスパラガスとアオリイカの料理のティーペアリングは、地元の店で手に入れた骨董の銚子(ちょうし)と猪口(ちょこ)で出された。「僕もそうですが、京都では、地元農家の野菜を食べ、醸造酢を使い、甘酒を飲み、地元の伝統産業である陶芸家の器を使い、服飾作家さんの服や鞄(かばん)を使う。そのライフスタイルにはすでに循環があります。このレストランも循環のある場でありたいと思うのです」(坂本シェフ)

時間をかけて作られた高い品質、作りすぎず捨てない物づくりへの姿勢と美意識。それらへの共感に支えられた、もちつもたれつの循環が、ちょうどよい大きさでなされる場。持続的な水産資源を守ろうとするシェフの団体、Chefs for the Blue(シェフス・フォー・ザ・ブルー)(東京・渋谷)の京都支部の立ち上げにも坂本シェフは名乗りを上げ、すでに勉強会を始めている。ここは、右肩上がりの消費や拡大を目指すのではない、もともとサステナブルなライフスタイルが反映された京都イタリアンの店なのだ。
イタリア食文化文筆・翻訳家。東京外国語大学イタリア語学科卒。イタリアの新聞社『ラ・レプブリカ』極東支局長助手をへて、文筆・翻訳へ。著書に『イタリア薬膳ごはん』(共著)『「イタリア郷土料理」美味紀行』、訳書に『イタリア料理大全 厨房の学とよい食の術』(共訳)『スローフード・バイブル』。
関連リンク
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。