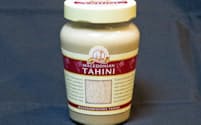今や第4次焼きいもブーム 1次は江戸期にさかのぼる!

日本の秋の味覚は多彩だが、庶民派の代表格といえば焼きいもとその材料であるサツマイモを使ったメニューだろう。
ブームの最初は江戸時代、川越の広告キャッチ

菓子類ではカルビーが「おさつスナック」を1981年から発売しているが、現在も秋の限定商品として売り出している。最近はほかにも各社が様々なサツマイモを使った菓子類を発売し、スーパーなどではそうした"おさつ菓子"の専用コーナーが設けられているところもある。
また、焼きいもはもともとは身近でそのものを安価に楽しめるものだっただけに、外食のメニューとしては取り扱いにくいもののように思われていたが、最近はレストラン、カフェなどでも"おさつメニュー"が秋メニューとして多くなっている。高価格商品が登場しているのも、注目の動き。たとえば東京ステーションホテルは「なると金時のティラミスパフェ」(2880円)、「さつまいもラテ」(1880円)を9月1日から販売している。

身近なものから高級品まで、秋はサツマイモメニューが目白押しだ。
今、食品メーカー、小売り、外食、ホテルの各社がサツマイモに力を入れる理由の一つは、2020年秋冬にコンビニなどで焼きいもが大ヒットしたこと。たとえば、「ローソンストア100」では2020年9月から2021年2月末までの間に「100円焼きいも」が1日平均1万本以上売れたという。そうした動きなどから、「コロナ禍の中でなぜか焼きいもが売れる」という認識が食ビジネス界に広がった。
また、「第4次焼きいもブーム」なるパワーワードもある。調べてみると、これはいも類振興会理事長の狩谷昭男さんという方が書かれた「焼きいもブームの歴史とその背景」という論述が元となっているようだ。
それによると、第1次ブームは江戸時代の文化・文政期~明治維新(1804年~1868年)、第2次ブームは明治時代~関東大震災(1868年~1923年)、第3次ブームは1951年~1970年、そして第4次ブームが2003年から現在(論述が発表されたのは2015年)だという。
サツマイモは17世紀に琉球(現在の沖縄県地域)に伝わり、やがて薩摩(現在の鹿児島県地域)でも栽培されるようになった。この作物に飢饉(ききん)対策の可能性を見た8代将軍・徳川吉宗が取り寄せて江戸や現在の千葉県地域で試験栽培したのが18世紀だが、今の埼玉県川越市一帯を管理していた名主がその栽培法を採り入れて川越での栽培が始まったという。
当時川越は水運で江戸とつながっており、川越産のサツマイモで、江戸の第1次焼きいもブームが起こったようだ。「九里よりうまい十三里」という宣伝文句の十三里(約51キロメートル)は江戸~川越の距離という(現在は日本橋~川越市間は道路で48キロメートルほどなので、51キロメートルは水運での距離かもしれない)。九里は同じく秋の味覚のライバルであるクリにかけたとされるが、吉宗の命で試験栽培をした地域の一つが九十九里浜と伝わるので、暗に「官より民」を自慢する気持ちがあったかもしれない(幕府にばれると処罰されそうだが)。
昭和期、「石焼きいも」の発明で国民的おやつに

さて、第1次ブームから第2次ブームはほとんどつながっていて100年以上となるが、それだけ長い期間、焼きいもは人気商品だったわけだ。江戸から明治になっても砂糖はまだまだ貴重品の時代。手ごろな価格で甘いものが食べられることはありがたかったに違いない。
太平洋戦争が終わった1945年の日本は凶作もあって深刻な食糧不足に見舞われていた。そんななかで政府はサツマイモを含むイモ類の栽培を奨励したことから、サツマイモ栽培が全国的に行われるようになった。その1945年ではなく1951年が第3次焼きいもブームというのはなぜだろうか。
実は1951年に「石焼きいも」が発明されたのだ。それ以前の焼きいもは、江戸時代はかまどに焙烙(ほうろく。焼いたり煎ったりするための土鍋)を置いて焼くなどが一般的で、関東大震災後にはインド料理で使うタンドールのようなじか火オーブン式の「つぼ焼き」が流行したという。

それに対して、石焼きは2つの点で新しさを持っていた。発明者は東京・向島(むこうじま)の三野輪万蔵さんという人だったと言う。石焼きは読んで字のごとく熱した小石でいもを包む方式だが、これはイモに均等に熱を通しやすい方法だ。さらに、三野輪さんはその専用調理機を特注のリヤカーに乗せて引き売り屋台を作った。そして、秋・冬の農閑期に東北地方の農家の出稼ぎの一つとして石焼きいも屋台販売網を展開したという。
1951年は日本が外貨を獲得するようになって、国民の所得が上向き始めた頃。そして国策で大量に栽培されたサツマイモはだぶついていた。そんな情勢のなか、焼きいもは手ごろな価格のスイーツとなって家や職場の近くに登場し、大人気商品になったのだ。

ところが、そのブームが1970年ごろに下火になったというのが、さびしいことながら興味深い。1970年は大阪万博の年で、ケンタッキーフライドチキンなどのファストフードが日本に上陸した年。菓子ではその少し前から「かっぱえびせん」という"甘くない菓子"がヒットし、1971年には「カップヌードル」という"甘くない間食"も登場している。そんな食生活、食志向の変化のなか、焼きいもはいったん"おやつの代表"の座を他に譲ることとなった。秋冬の季節商品であることも、お菓子ビジネスがマスマーケット化するなかでは不利に働いた。
では、2003年からの第4次ブームとはいかにして興ったのか。前出「焼きいもブームの歴史とその背景」によると、2003年に静岡のスーパーマーケットで焼きいもオーブンを使った焼きいもの販売が始まったという。この焼きいもオーブンはその後も改良を重ねながら、ほかのスーパーにも普及していった。
低温でじっくり焼くことで甘みがアップ
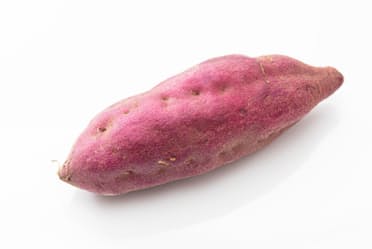
スーパーの店頭で見かける焼きいもオーブンは電気式が一般的だ。これは安全面からガスではなく電気を選んだものだが、加熱温度を管理しやすいなど電気機器としてのメリットを引き出しており、これがおいしさアップにもつながっている。
生のサツマイモは、かじってみると実は焼きいもほどには甘みを感じない(おなかを壊す可能性があるので味見をする際は気をつけて行ってください)。しかし、サツマイモはβ-アミラーゼという酵素を持っている。これは私たちの唾液にも含まれるアミラーゼの一種で、でんぷんを麦芽糖(水あめの主成分)に変える働きを持っているのだが、これが最も働く温度が70℃前後だという。電気式の焼きいもオーブンはこのβ-アミラーゼが働く最適温度を長く保つ仕組みを持っている。スーパーの店頭の焼きいもオーブンは、いわば石焼きいもに次ぐ大発明なのだ。

焼きいも用のサツマイモ品種にも交代があった。かつて焼きいも用品種といえば、ベニアズマ(農林36号)という品種が主流だった。これは「ほくほく」食感が特徴だった。ところが、2000年代に入って種子島産の安納いもが話題になる。これは「しっとり」「ねっとり」食感と蜜のような甘みが特徴だった。さらに、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)ではしっとり・ねっとりをターゲットとしたサツマイモ品種の開発を行い、べにはるかという新品種をリリースし、これが最近の焼きいもブームの人気品種トップとなっている。
焼き方の進歩、人気品種、そして「秋冬に移動販売が来る」焼きいもから「身近な小売店でいつでも買える」焼きいもへの変化によって、第4次焼きいもブームが発生、継続しているというわけだ。
ただ、そんなブームに水を差す困ったことが起きている。サツマイモ基腐(もとぐされ)病という病気が広がり、サツマイモ収量の低下を招いているのだ。2018年から沖縄県でサツマイモが立ち枯れし、イモが腐敗する症状が多発。他県でも同様の現象が見られるようになり、2021年には全国に波及している。これにより、農家は収入減になる一方、消費者にとってはイモの値上がりという問題になっている。
サツマイモは新物のほかに、前年までに収穫したひねいもというものがある。これは温度と湿度のコントロールでイモの表面に薄いコルク層を生じさせるキュアリングという方法で、長く貯蔵できるようにしているもの。これがあることで急激な価格変動をある程度抑えられていると考えられるが、病気まん延が長期化すると別な対策も必要だ。
現在は、基腐病の被害を広げないために種苗の移動の管理を強化するなどの対策を取っているが、もう一つ、被害を増やさないための対策として取られているのが早期収穫だ。病気が発生する前の早い段階で収穫するのだ。

病気が発生する前のイモは食べても問題ない。ただ、イモが小さいとか不ぞろいとかになりやすいという問題はある。そこで注目したいのが、冒頭でも取り上げた食品メーカーの菓子や、外食、ホテルのサツマイモメニューだ。菓子やスイーツの原材料としてなら、形や大きさの違いは許容しやすい。こうした商品を楽しむことは、サツマイモ農家の応援につながるだろう。
また、さまざまな食品を業務用冷凍食材に加工しているデイブレイク(東京・品川)は、不揃いのサツマイモを使った「ひとくち冷凍焼き芋」を開発。温めて食べるほか、凍ったまま"焼きいもアイス"感覚でも楽しめるという。業務用で小売りはしていないが、利用している小売店やレストランを見つけて楽しみたい。
(香雪社 斎藤訓之)
関連リンク
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。