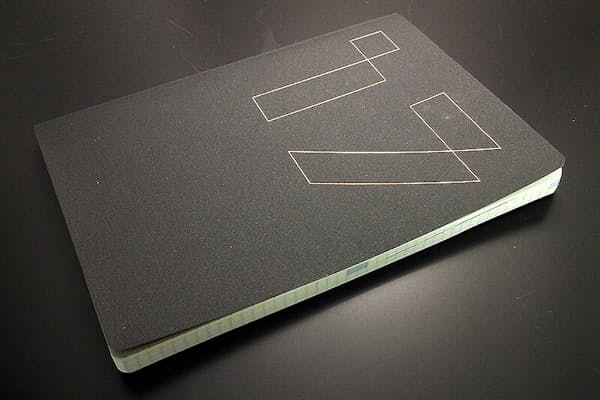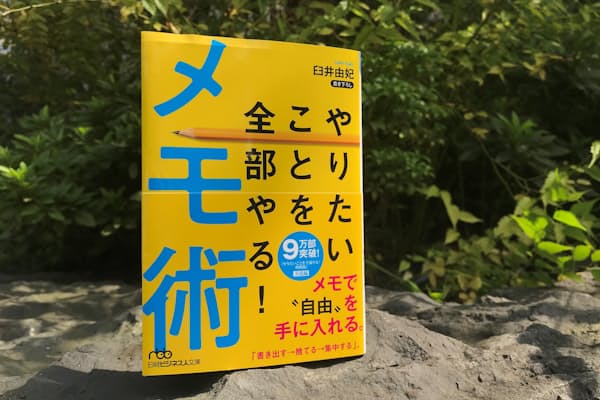3段階のメモを駆使 体系的に情報を整理し活用する技
『TAKE NOTES! メモで、あなただけのアウトプットが自然にできるようになる』より
ブックコラム
58冊の本と、数百本の論文という、大量の執筆をしたニクラス・ルーマンという社会学者がいます。彼の著作のクオリティーはずばぬけていて、専門分野以外でも古典的名著になっています。どうしてそんなことができたのか? その答えは、彼が編み出したツェッテルカステンという名前のメモ術にあります。本稿では、『TAKE NOTES! メモで、あなただけのアウトプットが自然にできるようになる』(日経BP)より、メモをなぜ取った方がいいのかと、ルーマンのメモ術の一部を、抜粋、編集し紹介します。
◇ ◇ ◇
優秀な人ほど、新しいアイデアを生むのに苦労する
たとえば、もしあなたが、よいアウトプットをしたいと思っていたとします。アウトプットをするとき、いちばん苦しむのはだいたい優秀な人です。
優秀な人は、最高の表現を見つけようとするので、文章を書くのに苦しみます。書くテーマを見つけるのにも長くかかります。最初に思いついたことはそんなにすばらしくない、そしてすぐれた問いは、待っていても降ってこないと経験で知っているからです。文献をもっとよく知りたいからといって図書館で時間をかけるので、読む量も多くなり、格闘する情報量も増えます。
しかし、たくさん読んでも、アイデアがそれだけ増えるとは限りません。特に最初のうちは、調べれば調べるほど、逆に取り組むアイデアがかえって少なくなります。
ほとんどのアイデアは他の人がとっくに調べてしまっているとわかってしまうからです。
また、すぐれた書き手は、「当たり前」のその先を見通そうとします。限界を乗り越えようとします。他の人のようなやり方はできません。たとえ、どのようにかみ合うかわからない複数の異質なアイデアにマニュアルなしで対応しなければならなくとも、いばらの道を行きます。
優秀な人は、そもそも他人より扱う情報が多い
これらすべてが意味するのは、増えつづける情報を記録するためのシステムが必要だということです。そうしたシステムがあれば、結びつけ、新しいアイデアを生み出すことができるようになります。
優秀でない人物には、こうした問題は起こりません。自分の能力の範囲にとどまり、いわれた参考書だけを読んでいれば(あるいはそれすら読まなければ)、外部のシステムを使う必要はありませんし、いつもの「文章の書き方」に従えば文章が書けます。
実際、優秀でない人は自分をたいして疑わないので、テストを受けるまで自分を優秀だと思い込むことがあります。これを心理学用語で「ダニング=クルーガー効果」といいます。
優秀でない人は、自分自身の限界を知ることができません。世の中には膨大な知識があることがわかってはじめて、自分がいかに知らないかが見えてくるからです。
このように、何も知らない人が自信過剰になるいっぽうで、努力した人が自分の能力を過小評価することがあります。優秀でない人は、書く題材を見つけるのに苦労しません。自分の意見をもっていないか、もう十分に考えたと自信をもっているからです。さらに、本から裏付けとなるエビデンスを見つけるのにも苦労しません。裏付けを否定するような事実や主張を見つけて検討する興味もスキルもないからです。
それに対して優秀な人は、まだマスターしていないことに気が付いてしまい、どんどん自分のハードルを上げていきます。
だからこそ、膨大な知識をたくわえた、成績優秀な人が、心理学用語の「インポスター(詐欺師)症候群」に陥ることがあります。実際には誰よりもその仕事にふさわしいのに、自分は適任ではないと思い込む症状です。
洞察は簡単には生まれない。メモは意見を主張するためだけでなく、共有する価値のある洞察を得るためのツールである―そう理解している優秀な書き手のために、本書『TAKE NOTES!』はあります。