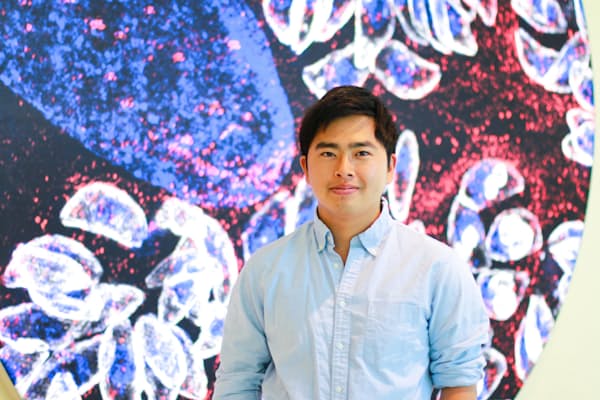土星探査を投資で実現へ 東大発起業家が夢に挑む
キャリアコラム
東京の羅悠鴻・代表取締役
エレベーター向けのデジタルサイネージ(電子看板)事業を展開する東京大学発ベンチャー、東京(東京・千代田)代表取締役の羅悠鴻さん(28)。三菱地所と共同出資会社を設立し、プロジェクターでエレベーター内に映像を投映するプロジェクション型のメディア事業にも参入した。東大では「はやぶさ2」事業に携わった杉田精司教授の下で天文学を専攻し、地球外生命探査という壮大な夢を抱いた羅さん。なぜ起業家に転身したのか。
エレベーターの扉に大画面が出現
「エレベーターの中でシネマ?」。東京・大手町にある三菱地所所有の大手町ビルヂング。築60年を超え昭和の薫りが漂う大型オフィスビルとして知られるが、最近「面白いエレベーターがある」と話題になった。
エレベーターに乗ると扉が閉まり、その扉に50インチほどの大画面が登場しダイナミックな映像が映し出される。プロジェクターを使い投映された画面だ。映し出されるのはニュースなどの情報だが、このエレベーターに初めて乗った人は迫力のある映像を見て一様に驚くという。三菱地所と手を組み、この「エレシネマ」事業を仕掛けたのが羅さんだ。
2017年、東大大学院のバンド仲間など同級生2人と創業した。東京という社名はバンドメンバーが好きだった曲の名前で、羅さんは「登記できるか不安だったけど意外とすんなり通った」と笑う。同社は、エレベーター内に後付けで設置するデジタルサイネージ事業「東京エレビGO」を展開。ビル管理者側の負担がゼロで、メディア事業者として広告収入を稼ぐという「エレベーター広告モデル」でビル事業者の注目を集めたという。