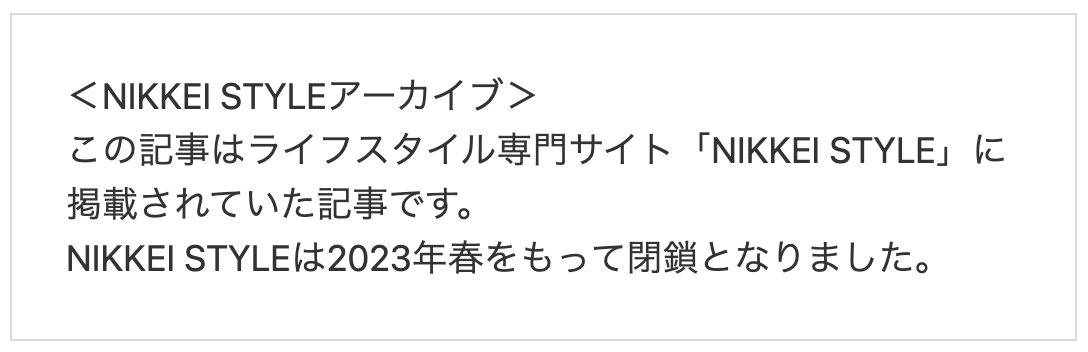「宮崎映画のような温かい抱擁」 台湾系米国人の旅

私(写真家のMike Kai Chen氏)はいつも夢のような場所に引き寄せられてきた。フォトジャーナリストとして、現実と空想のはざまにあるような景色を追いかけることが仕事の一部になっている。
崖の上の喫茶店、熱々の食べ物を売る屋台がひしめく坂道、赤いちょうちんの光。台湾の九份(きゅうふん)はそうした魅惑的な場所の一つだ。子供のころから訪れているため、この小さな山村のことはよく知っている。私が生まれた台北からバスで90分、海のそばにある。

昼は熱帯の楽園、夜は神秘的な雰囲気
伝統と現代的なものが同居する九份は典型的な台湾の町だが、かつて植民地支配したオランダ(17世紀)や日本(20世紀前半)の特徴も随所に見られる。また、昼間は太陽の光が降り注ぐ熱帯の楽園である一方で、夜はさまよう霊に出くわしそうな神秘的な雰囲気も漂わせている。
19世紀末に金の採掘が始まり、比較的静かだった九份は1945年まで続いた日本統治時代に、にぎやかな村になった。当時の面影は伝統的な旅館や建造物に残されている。建造物は山肌に積み重なり、曲線を描く細長い屋根には日本的な瓦が張られている。

映画監督の宮崎駿氏は九份からインスピレーションを得たことを否定しているが、この町の印象的な風景と2001年の映画『千と千尋の神隠し』との関連性を見いだす人も多い。
アカデミー賞にも輝いたこのアニメ映画は、10歳の千尋が不思議な世界に迷い込み、両親を恐ろしい呪いから救うという物語だ。その道中、千尋は湯屋の従業員、ボイラー室の釜爺(かまじい)とススワタリ、謎めいたカオナシなどと出会い、皆の助けを借りながら、夢のような世界を旅する。

千尋は湯屋で働く際に、千という偽名を与えられ、本当の名前を忘れそうになる。ほかにも、アイデンティティーと帰属を考えさせられる場面は少なくない。こうした普遍的なテーマが、欧米、特に移民の国である米国でこれほど共鳴した理由かもしれない。宮崎氏の作品はすべて、私の心の中で特別な位置を占めている。
私は3歳のとき、家族で台湾からカナダのトロントに引っ越し、その後、米国のカリフォルニア州に移った。現在、私は台湾系米国人を自称しているが、ほかの多くの人と同じように、台湾人と呼ぶには米国人すぎるし、米国人と呼ぶには台湾人すぎるとしばしば感じる。
私の家族は可能な限り、台北に残る祖父母を訪ね、おじやおば、いとこたちと集まっていた。祖父と図書館で漫画を読む、朝5時に公園を散歩する。いつも台所で片付けをしている祖母を眺める。台湾で過ごすこうした特別な時間の一つが九份旅行だった。

私たちきょうだいは年を追うごとに距離を感じるようになっていたが、食べ物が家族を一つにまとめ、忘れられない思い出をつくってくれた。私たちの好物は、屋台や小さな店で売っている定番のタピオカティーだった。祖父とアイスクリームを食べに行くこともあった。私はいつも、台湾でよく食べられている牛肉麺を両親にねだっていた。私たち家族は豆乳とファントンでつながっていた。ファントンとはもち米のおにぎりのことで、具は油条(細長い揚げパン)、漬物、豚肉のそぼろだ。
老街に並ぶごちそう
これらの好物の多くは台湾を象徴する夜市の一つ、九份老街で見つかる。日没後になると、通りは一気に活気づく。ちょうちんに照らされた屋台から熱い湯気が立ち上るその光景は、『千と千尋の神隠し』の冒頭で、千尋と両親がずらりと並ぶ麺類や肉料理の屋台に出くわしたときのようだ。
曲がりくねった老街にも、ごちそうがずらりと並ぶ。魚のフライ、シロップがかかった手作りの芋圓(ユーユェン)、ソーセージの串焼き、もち米で包んで蒸した肉団子、そして、数え切れないほどの麺類。

九份の頂上を飾るのは、阿妹茶樓(アーメイチャーロウ)からこぼれ出る金色の光だ。100年の歴史を持つこの建物はもともと鍛冶屋。華麗な日本建築が、霊たちの憩いの場で、千尋の仕事場でもある湯屋を連想させる。
阿妹茶樓では、緑豆ケーキなどの菓子を伝統的なお茶とともに楽しむことができるうえ、窓からは東シナ海を一望できる。この崖にはほかにも小さな喫茶店が点在している。
宮崎氏の映画は、多くの人にとって温かい抱擁のようなものだろう。私は九份に戻って同じような感覚を抱いた。壊滅的なパンデミック、祖母の死、写真家としての新しいキャリア、アジア系米国人であることの意味を問い直すなど、前回ここに来てから多くの変化があった。それでも、この山村はすべての魅力を維持し、私のルーツである食べ物、時間、人々を思い出させてくれた。
(写真 MIKE KAI CHEN、聞き手 ALLIE YANG、訳 米井香織、日経ナショナル ジオグラフィック)
[ナショナル ジオグラフィック 日本版サイト 2022年7月24日付]
関連リンク
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。