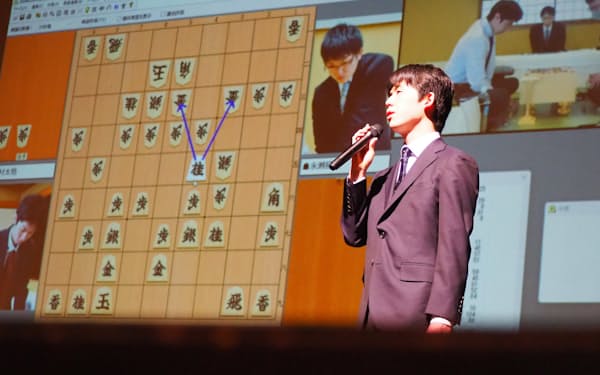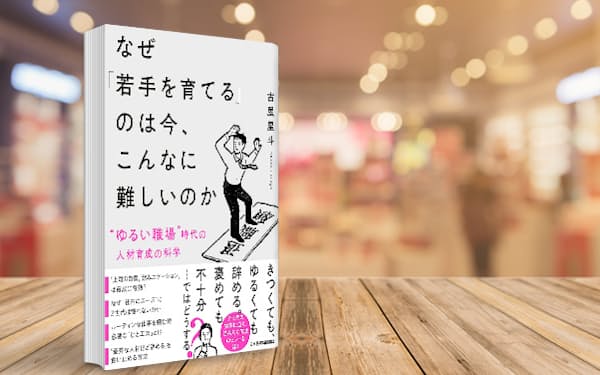夏野菜を鮮やかに調理 ナスは素揚げ、色素の流出防ぐ

旬を迎えた夏野菜はおいしく、そして見栄えよく調理したい。例えばナスは表面を油で覆うと、色素の流出が抑えられ、つややかに仕上がる。色鮮やかにできる理由を考えてみよう。
夏は多くの色とりどりの野菜が出回る。紫色のナス以外にも、緑色のピーマン、赤色のトマト、黄色のトウモロコシなど、その色彩で視覚からも食欲を刺激する。
ところがこうした野菜の色は調理の過程でくすんだり、煮汁に溶け出して薄くなったりするケースがある。彩り豊かに見栄えよく仕上げるにはどうしたらいいのだろうか。
野菜の色はその野菜に含まれる色素で決まる。色素は種類によって性質が違うため、それに合わせた調理の工夫が必要になる。
緑色の野菜に多い緑色色素クロロフィルは長時間の加熱や酸に弱く、褐色に変わりやすい。調理時は加熱時間を短くし、ドレッシングなど酸性の食材や調味料は食べる直前に加えるとよい。
一方、トマトやパプリカなど赤や黄の野菜を彩るカロテノイドは比較的安定していて変色しにくい。弁当や作り置きに向く食材だ。
例えば酢豚にはピーマンをよく使うが、酸性のあんがかかって時間がたつと、緑色がくすんだ褐色に変化してしまう。代わりに赤や黄色のパプリカを使うと見栄えがよい。
ナスの皮の紫色はアントシアニンという色素による。ミョウガや紫キャベツ、ブドウなどに多く含まれる。水に溶けやすいため、ナスを煮るときは要注意。断面から煮汁へと色素が溶け出してしまうからだ。皮の色が抜けて白っぽくなったり、味噌汁などの汁が黒く濁ったりする。見た目が気になる人もいるだろう。
色素が溶け出すのを防ぐには素揚げ、油通しといった下ごしらえが大切になる。ナスの煮浸しや南蛮漬けでは切ったナスを160~180度の油で揚げてから、煮汁や漬け汁に加える。表面が油で覆われ、色素が汁に溶け出しにくくなるのだ。あらかじめ火を通しておくことで、煮汁に浸して調理するのにかかる時間を短縮する効果もある。
素揚げは片付けが面倒で、カロリーが気になる人もいるだろう。そういうときはフライパンに底を覆うくらい多めの油を入れ、炒め揚げにする。大きめに切った場合は皮が下になるようにナスを入れ、皮全体に油が回るようにして揚げ焼きにする。それからひっくり返して断面を焼く。

ラタトゥイユやカポナータといった料理をつくる場合はナスなどの野菜をそれぞれ多めの油で炒め揚げにしてから、トマトや調味料と合わせてサッと煮る。具材ごとの色が鮮やかで、存在感のある仕上がりになる。
ナスは味噌汁に入れてもおいしいが、炒め揚げにして使えば汁が濁らず、皮の色も鮮やかだ。鍋に多めの油を熱してナスを炒めた後、キッチンペーパーで余分な油を拭き取ってだしを加え、味噌を溶き入れれば鍋ひとつで完成だ。
さらに油の量を抑えたい場合、表面に油をまぶしてから電子レンジで加熱する方法もある。揚げたり、炒め揚げにしたりした場合ほどではないが、色素流出が抑えられる。
油をまぶすにはポリ袋を使うと簡単だ。切ったナスと油を袋に入れ、風船のように中に空気の入った状態で口を手で握って閉じる。よく振れば表面に満遍なく油がなじむ。
素揚げ、炒め揚げ、油をまぶして電子レンジ加熱の順で油の使用量が多く、色落ちしにくい。目的や好みに応じて使い分けてほしい。
話が戻るが、ナスを切ったら水にさらすことが多い。断面の変色を抑え、渋みの原因となるアクを抜くためだ。切って放置すると、ナスに含まれるポリフェノールという成分が酸化され、褐色の成分に変化する。変色を防ぐには酸化に関わる酵素の働きを抑えたり、酸素を遮断したりする必要がある。手軽なのが水につけて空気、つまり酸素に極力触れさせない方法だ。酵素の働きが抑えられるので塩水を使うときもある。
ただしナスを揚げるなどする場合、必ずしも水につけておく必要はないだろう。揚げれば渋みは感じにくいし、切ってすぐ加熱すれば変色しにくいからだ。水につけておいて揚げると、油はねしやすくなる。加熱直前に切り、水につけずにすぐ揚げよう。実践してみてほしい。
◇ ◇ ◇
ガリは甘酢でピンクに変色

アントシアニンという色素は酸性で赤や赤紫に、アルカリ性で青や緑に変色する性質がある。とりわけ酸性にした際の鮮やかな色は料理に彩りを添えるためによく利用されている。例えば梅干しづくりに使われる赤しその汁はそのままでは暗い紫だが、梅に含まれるクエン酸によって鮮やかな赤紫に変わる。
すしに添えられる「ガリ」のピンクもアントシアニンの色だ。材料となる新生姜は通常は薄いクリーム色をしているが、甘酢に漬けると、淡いピンクに変わる。野菜の色について知るのも楽しい。
(科学する料理研究家 平松 サリー)
[NIKKEI プラス1 2022年6月18日付]
関連リンク
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。