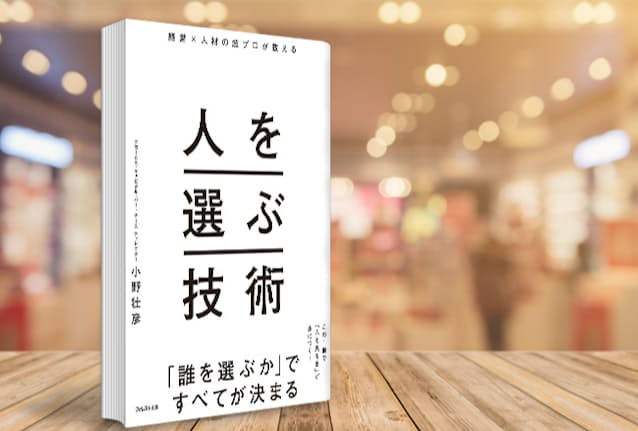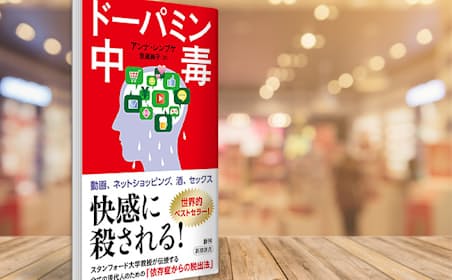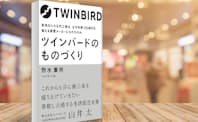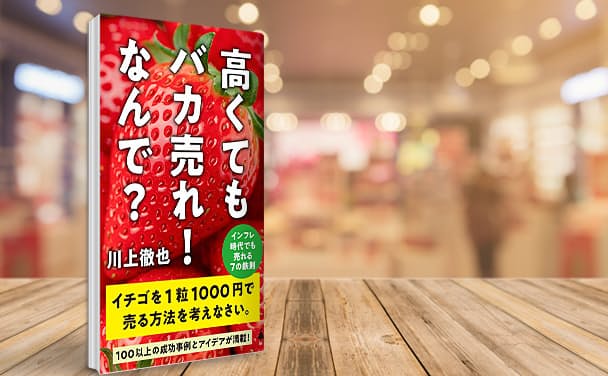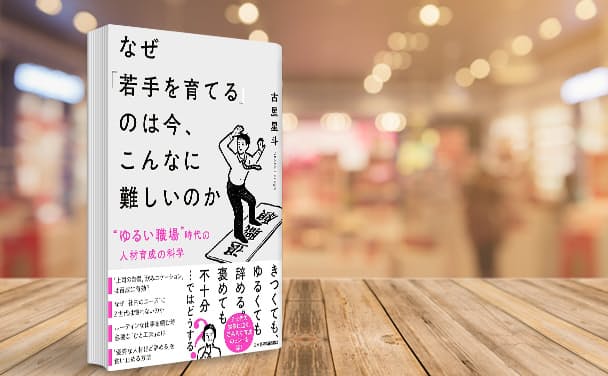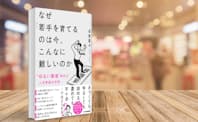採用面接を行ったことがある人なら、採用した人材が思っていたのと異なるタイプだった経験があるかもしれない。「人を見る目」はビジネスシーンで部下や社内外のパートナーなどを選ぶ際だけでなく、友人関係の構築などプライベートでも養っておくべき能力だ。
本書『経営×人材の超プロが教える 人を選ぶ技術』は、「人を見る目」は学んで身に付けることができるとして、そのためのフレームワークを紹介する。人物を見抜き、「こういう仕事に向いている」と見立てる「人を選ぶ」力について、面接する際の具体的な質問などのテクニックも示す。
著者の小野壮彦氏は、ハイレベル経営層のヘッドハンティングを手掛けるエゴンゼンダー社に勤めた経歴をもつヘッドハンター。現在はグロービス・キャピタル・パートナーズのディレクターを務める。
■「鈍感力」という優秀さも
人物を見極めるシーンでは、人物の「優劣の判断」「善悪の判断」の2種類が求められる。そこで、縦軸を「優秀」「平凡」、横軸を「人として善」「人として悪」とする4象限に分ける。このとき、「優秀・人として善」に分類される人材は、採用するなら絶対に見逃してはいけない、いわば理想のタイプだ。一方、「優秀・人として悪」に分類される人材は、成績は良いのに問題を起こすなど扱いが難しいタイプが多いという。この4象限を頭の片隅に置いておけば、人を見る際の基準にできそうだ。
もっとも、人物の優劣や善悪の判断は、簡単ではない。著者自身、弁が立ち、勢いや華のある人を優秀と判断しがちだったために、朴訥(ぼくとつ)とした人の「粘り強い」「鈍感力がある」といった優秀さを見落としたことがあるという。その人物は、後にビジネス界で大成したそうだ。
ほかにも、学歴に対する思い込みや、無意識に自身と異なるタイプの人物の評価を下げてしまうといったバイアスなどによって、優秀な人を見落とす例があるようだ。常に自らのバイアスをチェックする姿勢が欠かせないのだろう。
■誰かを「排除する」ことではない
タイトルの「人を選ぶ」という言葉からは、やや尊大な印象も受ける。しかし、読了後の感想は違った。著者が人を選ぶことの「傲慢さ」を自覚し、つねに自身を戒めながら本書を書いているからだろう。
そもそも、人を選ぶことの目的は、誰かを「排除する」ことではない。本人さえ気づいていないかもしれない「行動特性」を探り、備える「ポテンシャル」を見抜き、ふさわしい仕事を任せることができるならば、本人にとっても社会にとってもプラスになる。かりに「失言リスクのある人だ」と見抜いたならば、その失言をさせないようなアドバイスやマネジメントにつなげることもできるのだ。さらに言えば、人を選ぶ技術によって、振り返って我が身を評価し、見立てる力も養うことができる。
「人を見る目」がある人たちは、何を見ているのか。彼らに自分はどう映るのか。それらを探るうえでも、本書は一読の価値がある。
2020年から情報工場エディター。08年以降、編集プロダクションにて書籍・雑誌・ウェブ媒体の文字コンテンツの企画・取材・執筆・編集に携わる。島根県浜田市出身。