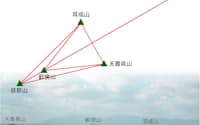輝き戻った究極の甲冑、伝統工芸が結集
春日大社・赤糸威大鎧(奈良市) 古きを歩けば(22)
あかね色を背景に、金色の雀(すずめ)が躍り、虎が哮(たけ)る。精緻な金工と、鮮やかな色彩のコントラストから「日本一豪華」と称される国宝「赤糸威(おどし)大鎧(よろい)(竹虎雀飾)」が初の本格修理を終え、奈良市の春日大社宝物殿で公開されている。甲冑(かっちゅう)は伝統工芸の集大成だと改めて感じさせる逸品だ。
■兜の正面に隙間無く金物細工
鎧は高さ約135センチ。兜(かぶと)の正面に隙間無く飾られた...
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。