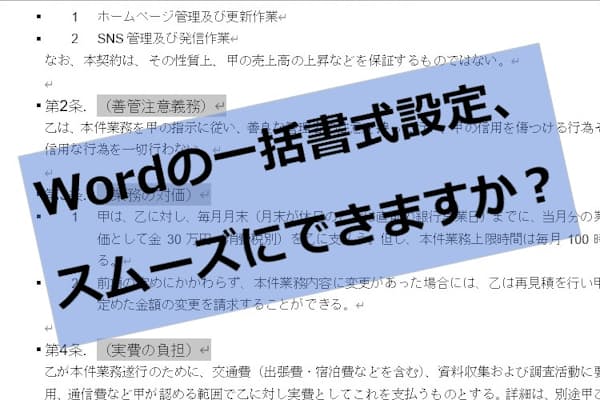男性の育休取得が激減…背景に「パタハラ」
イクメンプロジェクト委員 渥美由喜
男性の育休取得率が大きく低下、実は1000人に4人もいない

図1 厚生労働省「女性雇用管理基本調査」(2007年以降は厚生労働省「雇用均等基本調査」より作成)。事業所規模5人以上。2011年度の数値は、岩手県、宮城県、福島県を除く
男性の育児休業取得率がガクンと低下した。2012年度の男性の育児休業取得率はわずか1.89%で、前年度の2.63%から0.74ポイント減少(図1)。安倍晋三首相は「『女性が働き続けられる社会』を目指すのであれば、男性の子育て参加が重要」と成長戦略の中で打ち出しているが、これに逆行するかのような動きだ。
実は3年前から、男性の育休取得の対象者は拡大している。労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止により、妻が専業主婦でも産後8週以内であれば、夫は育児休業を取得できるようになった。にもかかわらず、育児休業の取得者が増えないということは、男性が育休を取りやすい環境づくりが進んでいないことを示している。
たとえ育休を取ったとしても、期間は短い。「1~5日」が4割、「5日~2週間」が2割と2週間未満が6割を占める。育休取得者の割合はここ10年微増しているものの、その大半が1カ月未満という短期の取得者だ。
取得期間別の割合をみると、1カ月未満の取得者は2005年度の31.7%が12年度に81.3%へと高まっている(図2)。「わずか数日か、1、2週間休んだぐらいで、イクメンなんてエラそうな顔をしないでよ!」と憤慨する女性の声も聞こえてきそうだ。つまり、男性の大半が数日から数週間の「なんちゃって育休派」なのだ。

図2 男性の育休取得期間は1カ月未満と、3カ月以上が増加傾向と二極化している(出元:平成17 年度厚生労働省「女性雇用管理基本調査」、平成20・24年度「雇用均等基本調査」に基づき渥美氏が作成)
別の統計もみてみよう。月に20日以上育休を取得すると、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されるが、11年に育児休業給付金の給付を受けた男性の実数は4067人。出生児数(107万人)を基に、育休取得率を算出し直すとわずか0.38%。男性で20日以上の育休を取得した人は、1000人に4人もいないのが実情だ。