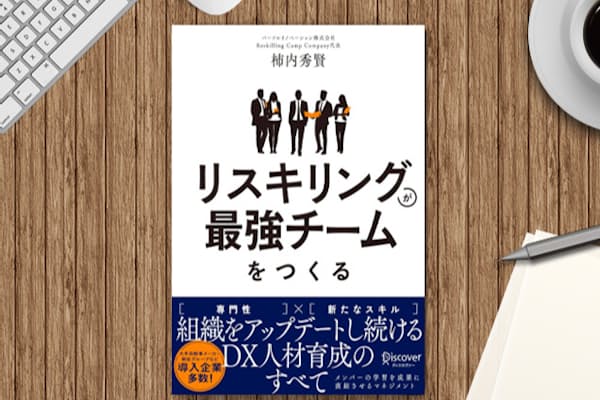哲学・歴史・古典… 職場研修で教養を磨く
グローバル化・法令順守に対応
中国の古典や西洋の哲学・思想、世界の歴史に古今東西の文学……。幅広い教養や人間性を身に付けるのを狙った「リベラルアーツ研修」を取り入れる職場が目立つようになってきた。受講するのも経営を担うリーダーはもちろん、若手・中堅層にまで広がっている。ビジネスの世界とは縁遠いようにみえる教養をなぜわざわざ職場で、忙しい時間を割いてまで学ぶのか。その背景を探った。

三井物産では歴史や宗教などを題材にした研修を今年度から導入(東京・大手町)
「『和を以て貴しとなす』の聖徳太子には議論も
続きは会員登録(無料)が必要です
NIKKEIリスキリングの会員登録をしてください。登録は無料です。
会員登録(無料)すると
- 組織戦略や個人の成長に関する記事が読み放題
- リスキリングのヒントになるセミナー動画が見放題
- 編集者の気付きやオススメ記事をメルマガでお届け