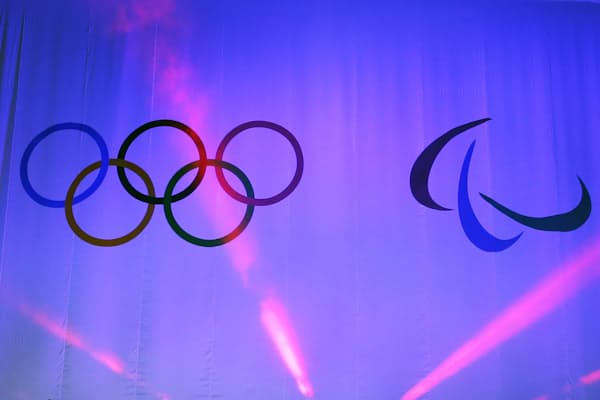五輪後の経済を生き抜くオープン&クローズ戦略
生き残るために、支えるために~プロローグ(2)
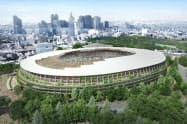
日本スポーツ振興センター提供
足踏み状態が続く日本経済。当面は2020年開催の東京五輪・パラリンピックをめざし、カンフル剤を打ち続けて景気の底上げをはかっています。薬が効いている今のうちに、東京五輪後の時代「post 2020」に向けての準備ができるかどうかで、私たち働き手の、その後の展開が大きく変わります。
この連載では、心理学に通じた公認会計士・税理士の藤田耕司氏と、日本経済新聞社の渋谷高弘編集委員が、新たな時代へ向けて挑戦を続けている人たちへの取材を通じて、その答えを探ります。今回はそのプロローグ編の第2回。

藤田耕司(ふじた・こうじ)=左 公認会計士、税理士、心理カウンセラー。1978年徳島県生まれ。2002年早大商卒。04年有限責任監査法人トーマツ入社、11年退社。12年藤田公認会計士税理士事務所(現FSG税理士事務所)、13年FSGマネジメント、15年日本経営心理士協会を設立。 渋谷高弘(しぶや・たかひろ)=右 日本経済新聞社 編集委員。1990年入社。主に企業取材、法務関連を担当。主な著書に「中韓産業スパイ」「特許は会社のものか」。
藤田渋谷さんは民間企業や法律関連分野を主に取材されています。そうした分野から「post 2020」をどのように考えますか。
渋谷 すでに1990年代から起きていたことですが、業績不振に陥った日本企業が多くの技術者をリストラした結果、その技術者が外国企業、例えば韓国や中国の企業に引き抜かれ、技術やノウハウが流出しました。日本の技術を習得した外国企業が競争力をつけ、結果として日本企業は更なる打撃を受ける。こうした悪循環が今後も続いてしまわないか心配です。
藤田 渋谷さんの著作「中韓産業スパイ」(日本経済新聞出版社)は、そうした日本企業の競争力と知的財産権の在り方がテーマですね。
渋谷 技術流出、さらにいえば技術者という人的財産を日本企業が軽視してきたことが、日本の危機を招いていると指摘するために書きました。
人的財産の軽視が日本経済の危機を招いた
渋谷 日本企業の競争力低下の行き着く先の代表的な事例が、電子機器受託製造サービス(EMS)世界最大手、台湾の鴻海精密工業(ホンハイ)によるシャープ買収です。