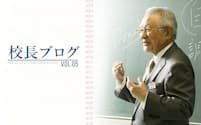好きなことしかやらない新人 コロナ下で重要な共感力
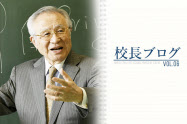
「高校4年生」と呼んでいた
新型コロナウイルスは、デルタ株の流行もあり、未成年者にも感染が広がる懸念が高まっています。渋渋と渋幕では、9月中にワクチン接種を希望する生徒と教職員を対象に実施することにしました。コロナ禍で、学校の教育現場でも難しい選択を迫られています。昨年も一時的にオンライン授業は実施しましたが、なかなかネットのみでの教育は難しいです。やはり対面も必要だと考えています。
学校現場で大事なのは生徒同士の交流です。同級生や先輩後輩などの仲間と気軽に話したり、普段から刺激し合ったりすることがすごく大切なのです。昨年春、大学に合格した生徒たちは、自分たちを何て呼んでいたか、ご存じでしょうか。大学の大半の講義はオンラインになったので、新しい友人ができない。中高時代の友人しかいないので、自分たちを「高校4年生」と呼んでいたのです。これでいいのでしょうか。
今年に入り、オンラインか対面か、講義形式については大学によって対応が分かれています。早稲田大学は対面授業の再開に意欲的のようですが、東京大学などは依然慎重のようです。確かに学校側には覚悟が必要になります。私も教員になって60年ぐらいになりますが、感染症のパンデミック(世界的大流行)なんていう経験は初めてです。
ただ、渋渋、渋幕では対面授業・イベントを大事にしたいと考えています。例えば渋渋ではパラリンピック終了後の6日から2学期をスタート、基本は対面授業で行おうと考えています。もちろん問題が起これば、すぐにオンライン授業に切り替える準備はできています。9月中旬に予定されている文化祭もコロナ対策を徹底してリアルで実施する考えです。
デジタル化で浮き彫りになった課題
今、学校教育は大きな転換点を迎えています。パソコンやダブレットなどデジタル端末が全生徒に行き渡り、「個別最適化教育」が実現できる環境になってきました。1人ひとりの個性を大事にして教育できることはすごくいいことだと思います。コロナ禍のなか、デジタルを活用した教育はさらに進むでしょう。しかし、課題も見えてきました。
最近、企業の人たちと会話していると、こんな声が聞こえてきます。「今の新入社員は好きなことしかやらない。嫌になると、すぐ会社を辞めると言い出す」。これはいかがなものでしょうか。やりたいことをやるのはいいけど、周りの人たち、社会と折り合いをつけないといけません。個人の自由と社会、この問題はギリシャ文明が興隆した時代から常に問われる課題です。
古代ギリシャの哲学者、ソクラテス。国家が信じる神を尊ばず若者を堕落させたとして裁判で死刑を宣告されました。ソクラテスは、若者に個人の自由を説いていたようですが、国が認める神々を侮辱したと訴えられたのです。宗教は、近代国家が生まれるまでの社会の維持装置の役割を果たします。近代になると、宗教に代わって各国家はそれぞれの法律を制定し、社会の秩序を保ったわけです。
しかし、21世紀になってグローバル化やデジタル化が急速に進み、社会は再び大きく変わろうとしています。国家という枠組みが存在感を薄め、それぞれの個人の独自性や能力が問われる時代が来そうです。
アダム・スミスは「同感」、今は「共感」
個性は大事です。しかし、社会のニーズに合わない、自分勝手な主張や行動は通じないでしょう。自分たちで考えないといけないですね。自分は何をやりたいのか、それは社会に役立つことなのか。渋渋、渋幕では数学や英語などの教育はもちろん一生懸命にやっていますが、ある意味それ以上に大事にしているのが「リベラルアーツ(教養)」教育です。
渋渋、渋幕両校では私が「校長講話」を通じて直接生徒たちと対話しながら、リベラル・アーツ教育を実践しています。ここでもソクラテスなど哲学者の話は必ず出てきます。
リベラル・アーツ教育を追求する中で、次の時代をよりよく生きていく上で必要なモノは何か考えました。個性を大切にしながら、社会と共生するには「エンパシー(共感)」が大事だと思います。経済学の祖、アダム・スミスは人間にとって大切なモノは「シンパシー(同感)」だと主張しました。しかし、多くの人とつながるネット社会ではさらに進んで「共感」が必要ではないでしょうか。
コロナ禍でも共感力の高い人は成長するでしょう。話は少し変わりますが、渋渋に優勝カップが届きました。世界の高校生がプログラミング力を競う国際情報オリンピックで渋渋の菅井遼明くんが金メダルを獲得し、送られてきたのです。日本代表は菅井くんのほか、渋幕、灘高校、麻布高校の4人。菅井くんにとって彼らは他校のライバルでありながら、友人にもなった。切磋琢磨しながら、日本代表としてベストを尽くしたようです。4人とも個性的で優れた能力があり、きっと共感力も高い生徒だと思いますね。
麻布高校を経て東京大学法学部卒、1958年に住友銀行(現三井住友銀行)に入行。62年に退職し、父親が運営していた渋谷女子高校を引き継ぐ。70年から渋谷教育学園理事長。校長兼理事長として83年に同幕張高校、86年に同幕張中学をそれぞれ新設。96年に渋谷女子高を改組し、渋谷教育学園渋谷中学・高校を設立。日本私立中学高等学校連合会会長も務めた。
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。