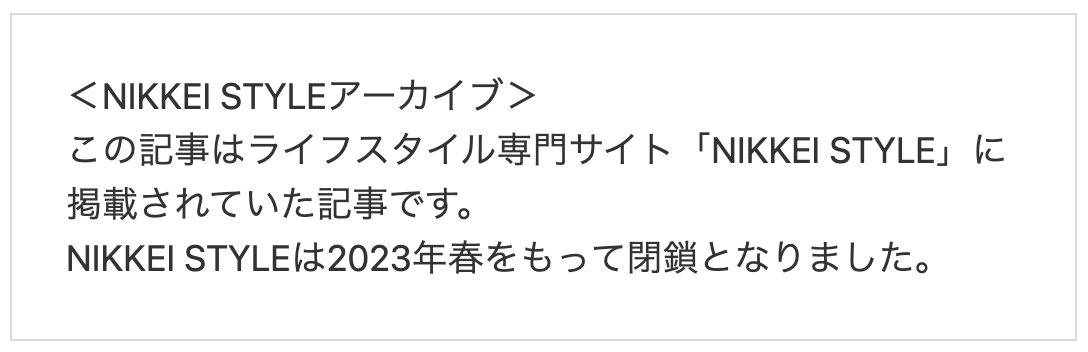コーヒーにもフルコース登場 バリスタが拓く新市場
コーヒーを語ろう

仕事の合間の気分転換、あるいは一日に区切りをつける食後の一杯。そんなコーヒーのイメージが、この店では覆されてしまう。
多くのカフェが個性を競う東京・清澄白河に「KOFFEE MAMEYA-Kakeru-(コーヒーマメヤ カケル)」が開業したのは今年1月。外観は元の倉庫そのままで、ガラス張りの入り口正面には額縁舞台のような豆売りカウンターが鎮座する。その背後に30弱の客席がコの字形に並び、内側に据えた3つの作業台の周りで白衣を着たバリスタがキビキビと立ち働く。天井高く6本の柱が立つ空間は四阿(あずまや)を思わせる。

予約が基本の同店の看板商品はコース仕立てのスペシャルティコーヒーだ。焙煎(ばいせん)度合いが異なる同じ豆の飲み比べもあれば、指定した豆を様々な方法で抽出し、菓子とのペアリングを楽しむ"フルコース"もある。今回はエチオピアの豆のブレンド「ラズベリーキャンディ」を指定して「コーヒーマメヤコース」(2800円)を試してみた。
まずはキリリとした水出しコーヒー。整った酸味が甘味をまとう。水出し風にミルクで抽出した「ミルクブリュー」は口当たりまろやかで、コクはしっかり。さらにペーパーフィルターで抽出したコーヒー、ラテ、エスプレッソにスイーツ、と続く。水出しとミルクブリューにはモクテル(ノンアルコールのカクテル)も添えられる。コロナ禍で休止中だが、コーヒーを使ったカクテルもメニュー化している。

たっぷり1時間、コーヒーの多彩な表情を堪能し、飽きることがない。これは出しゃばらず、如才のないバリスタの接客に負うところも大きい。同店を運営する嗜好品研究所(東京・渋谷)代表取締役の國友栄一さんはこう話す。
「想定よりも客単価が高く、少々驚いています。お客様の8割がコースをオーダーするし、6800円のコースも注文が入る。開業初月から利益が出て、週末はフル稼働が続いています」
「コーヒーでも、三つ星レストランのような非日常を体験できる店を作りたい」。そんな國友さんの思いからカケルは生まれた。定期的にシェフやパティシエなど食のプロとコラボするイベントを開き、新しいコーヒーの味わい方も提案する。店名の「カケル」は異業種との「かけ算」を意味している。
グルメ化の波はコーヒーにも
コロナ禍にあって、この特異なスタイルの店が順調に滑り出したのも、決して物珍しさからだけではない。近年のブームなどを経て、この国にコーヒーの「ガストロノミー(美食)化」「グルメ化」を受け入れる素地がようやく固まってきたからだ。國友さんはそう分析する。
「グルメ化はある意味、食の本質です。おいしいものを口にしたら、もっとおいしいものが欲しくなる。市場が成熟すれば、なぜそれにお金を払うのか、という『意味』を強く意識する人も増える。コロナ禍でその傾向は強まっているかもしれません。コーヒーも例外ではなく、店でも自宅でも、こだわりの対象としての存在感が大きくなった。新しい味の体験を求めるお客様も増えていると実感します」

國友さんの言葉を借りれば、コーヒー市場はターニングポイントを迎えている。そこで重要な役割を担うのが、バリスタなのだという。今までにない高付加価値のサービスと商品を、お客に納得して受け入れてもらえるかどうかは、バリスタの腕次第だからだ。
「私はロースター(焙煎業者)はメーカーで、バリスタはシェフだと考えています。バリスタは様々な焙煎豆の中からいい素材を見極め、それを調理し、お客が喜ぶ最終製品にして提供する。高い抽出技術に加え、ブレンドの腕前やお客の好みを探るカウンセリングと接客能力、ペアリングなどの演出力も求められる。『表現者』としてのセンスと力量が問われる職業です」
小規模な自家焙煎の喫茶店はともかく、日本の著名なカフェの多くは、自ら豆を焙煎するロースターでもある。いうなればメーカーとシェフの機能が融合した事業体として、味わいの表現を追求しているわけだ。また、腕を上げたバリスタの中には、表現の幅を広げようと焙煎技術の向上に関心を寄せる人もいる。だが、この点、國友さんは徹底した分業論者だ。
「私たちは豆の焙煎はしません。なぜなら、表現の幅が、自分たちが焼く豆の範囲に限定されてしまうからです。また、ロースターは生産者と関係を深め、豆に日々向き合って焙煎の技術を磨かねばならない。バリスタとはまったく別の職業で、一人の人間がこの二つを両立させるのはとても無理だと思う」
時代の転換期において、コーヒーの新たな可能性を消費者に紹介し、市場を切り拓(ひら)くバリスタの存在価値を、今こそ広く認知させたいと國友さんは考える。それはバリスタの現状に対する危機感の裏返しでもある。

「日本では職業としてのバリスタの歴史が20年程度とまだ浅く、抽出マシンのオペレーター程度の認識にとどまる人もいます。せっかくキャリアを積んで腕を磨いても、現場ではそれに見合う付加価値を価格に乗せてもらえない。10年選手のバリスタが淹(い)れても、5カ月のアルバイトが淹れても、店では1杯が同じ500円ですから。このままでは、バリスタは安い人件費とオートマチック化の波に飲み込まれてしまう」
これは世界共通のバリスタの悩みでもある。相応の対価を得ながら、自らの技術を発揮し続けられる進路を模索するベテランは少なくないという。
現在、嗜好品研究所が抱えるバリスタは13人。様々なバックグラウンドを持つ面々が、自らの腕を恃(たの)みに集っている。「これまでは優秀なバリスタが技術をアウトプットする場が限られていました。私の役目は、彼らが存分に活躍できるステージ(舞台)を用意することです」。その舞台の一つが、カケルなのだ。
ロースターと客を橋渡しするバリスタ
バリスタが屋台骨を支える別の店が、カケルの前段にある。2017年に東京・表参道に開いた豆売り特化の「KOFFEE MAMEYA(コーヒーマメヤ)」。国内外の著名なロースターから豆を調達し、単一農園のシングルオリジンや独自のブレンドで販売する、いわばセレクトショップだ。
小さなカウンターをはさんでバリスタがお客と対峙して、好みを聞き、当日扱う豆のプロフィルを説明する。購入した豆には、1杯あたりの最適な豆とお湯の量、抽出時間などを記したレシピを添える。鍛え抜いた抽出とカウンセリングの技術を生かして「バリスタが、バリスタとして豆を売る方法」を模索した末に考案したスタイルだ。バリスタはロースターとお客の橋渡し役に徹する。
コンセプトは「家のコーヒーをもっとおいしくする」。良質の豆は増えたが「おいしい飲み方、ちゃんとした淹れ方を知りたい、というお客様はまだ多い。でもロースターの壁を越えた中立的な立場でお客様に助言する存在が、この業界から抜け落ちていたんです」。
両店を貫くのは「バリスタの力を生かし切る」というポリシーだ。同時に、その斬新な運営スタイルは、消費者の潜在ニーズをしっかり捉えてもいる。「根本的には何事もお客様目線で考えます」と國友さんはきっぱりと言う。
「お客様目線」を肝に銘じるようになったきっかけがある。イタリアでバリスタ修行した後の03年、大阪にイタリアン・バールを開業した。本場のスタイルを忠実に再現したが、なかなか軌道に乗らなかった。「日本では日本のお客様が喜ぶ形に昇華させないと商売にはならない」。そんな反省を胸に09年、開業に携わったのが東京・表参道の「パンとエスプレッソと」だ。購買頻度の高いパンとコーヒーを組み合わせた"日本型バール"は成功を収めた。

続いて11年に開業したのが「OMOTESANDO KOFFEE(表参道コーヒー)」。普及途上のスペシャルティコーヒーを手軽に飲める、当時はまだ珍しい持ち帰り主体のコーヒースタンドだった。古い日本家屋の内部にキューブ型のスタンドを配置するユニークな構えが話題を呼び、1年間限定のはずだった営業が15年まで続いた。ちなみに店名が「COFFEE」でなく「KOFFEE」であるのは、売店「KIOSK」のKに由来する。
エッジの効いたこの店も「いいコーヒーを手軽に飲むスタイルは必ず浸透する」という、肌で感じた潮流の変化をカタチにしたものだった。
「根本はお客様目線でも、オリジナリティーは大事にしています。ビジネスとしての成立と"ひとりよがり"とのバランスにはすごく注意している。そこは自分のセンスを信じるしかない」
人口減の影響は避けられないが、それでもスペシャルティコーヒーの市場は工夫次第で伸びる余地が大いにある、と國友さんは確信している。今までにない、潜在ニーズを刺激するアプローチを探し続ければ、活路は開けるとみる。
カケルが世に問うグルメスタイルは、他社も導入する動きがある。競合は激しくなるが、消費者の認知が広がれば市場全体の成長余地は拡大する。それこそ望むところだという。大事なことは、さらにその先へと、どこよりも早く歩を進めることだ。すでに國友さんの頭の中には、次の新業態の絵が描かれている。=おわり(名出晃)
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。
関連企業・業界