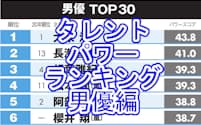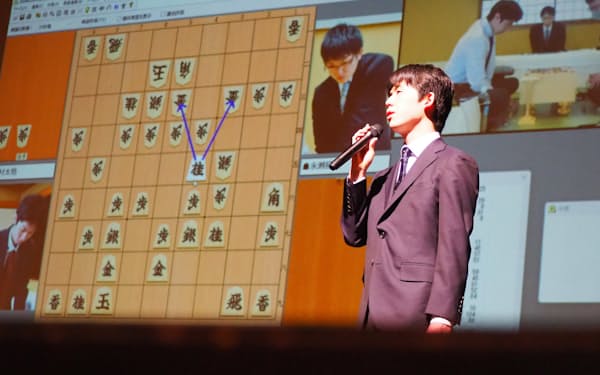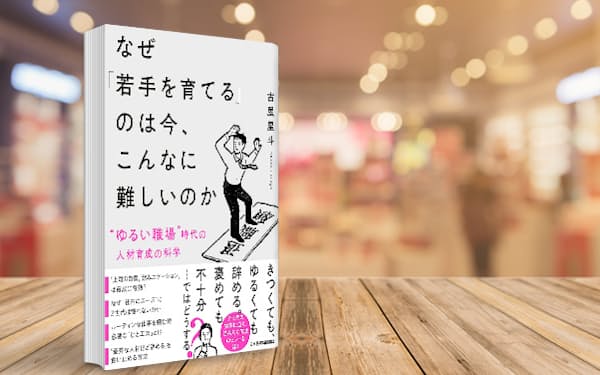阻まれた初の男性育休 「昭和体質」の会社見切り転職

男性育休取得推進の動きが広がりつつあり、男性が育休を取りやすくするための改正育児・介護休業法も成立した。一方で、いまだに、仕事のために子育てに関われないことが「武勇伝」のように語られ、育休を取れる雰囲気ではなかったり、上司に異動をほのめかされるなどの「パタニティー・ハラスメント(パタハラ)」を受けたりする職場も残っている。コロナ下で実家などに頼れず、父親が育児の「戦力」としてさらに重要になっている中、男性育休取得実績がゼロの企業で育休取得を試みた男性の体験談を聞いた。
「お義母さんが仕事辞めれば」上司の言葉にあぜん
横浜市在住の松田修さん(仮名・28歳)に昨年7月、長女が生まれた。当初は出産後、妻と子どもが妻の実家に帰るつもりだったが、コロナ禍のため見合わせ、松田さんが育児休業を申請することにした。
しかし勤務先の大手専門商社は「昭和体質」で、ごくまれに女性社員が育児休業を取得する時でさえ、陰で上司が「本当は辞めてもらったほうがいいんだけど……」と愚痴を言うような職場だった。もちろん男性の育休取得実績はゼロ。
上司に相談したのは、まさに最初の緊急事態宣言が出たころ。「産後間もない妻だけでは買い物もままならないので、心苦しいが1カ月の育休取得をお願いしたいと頼みました」
しかし上司は「君の仕事は誰にやらせるの」と渋い顔をした。「実家を頼れないのか」と聞かれたので、義母は店舗勤務で不特定多数の人と接触があり、感染リスクを考えると帰省できないと説明した。すると上司は「お義母さんはパートでしょ。仕事を辞めればいい」。松田さんはあぜんとしたという。
松田さんの妻は語る。「母はパートとはいえ勤続20年で、新卒入社なら課長に昇進するくらい長い間、スキルを磨いてきました。担当部門のリーダーとして勤務シフト作りを任されるなど、責任ある立場にも就いています。でも上司にとって女性のキャリアなど、どうでもいいことなのでしょう」
最終的に、松田さんは同僚一人ひとりに仕事の肩代わりをお願いし、分担表を作って上司に提出。その期間、週2日は出社し、それ以外の日はリモートで仕事をしてやりくりした。このため結果的には育児休業制度を適用せず、在宅勤務扱いになった。
それでも上司は、「育休」の直前、こう言い放ったという。「復帰したら営業から外れて人気のない部署へ行くか、一般職として働くことも考えなければいけないだろうな」
実家の家族がコロナ感染、両親は自宅隔離
松田さんの妻は、夫が家で買い物や料理などを引き受けたことを「とても助かった」と振り返る。さらに打ち明けた。「会社は『いちいち感染を心配していたらきりがない』『万に一つもない』と思うのかもしれません。でも万に一つは起きたんです」
出産のための入院から退院後間もなく、実家に住む弟がコロナに感染。両親は陰性だったが濃厚接触者として2週間、出勤停止を命じられ自宅から出られなかった。「里帰りしていたら、私も実家に隔離されていたかも。赤ちゃんはどうなっていたか……」と、表情をこわばらせた。
また、会社が夫の育休取得希望を「妻のわがまま」であるかのように攻撃したことにも憤りを感じている。「私が夫に育休を取らせ、家事をさせる『鬼嫁』で、夫は被害者だなどとチクチク言われたそうです。でも共働きで実家の助けも借りられない中、夫婦で家事と育児を分担するのは、当たり前ではないでしょうか」
夫妻は育休取得に当たり、労働基準監督署やNPO法人ファザーリング・ジャパン(FJ)に相談した。松田さんはFJからのアドバイスが、心の支えになったという。「新卒入社で他の職場を知らないので『世の中こんなもので、自分がおかしいのかも』という思いがどこかにありました。でもFJのメンバーに『いまどきありえない』と言ってもらえて、自分は間違っていないと安心し、会社と交渉できました」
ファザーリング・ジャパン(FJ)東北の理事で自身も10年ほど前、育休取得に伴うパタハラ被害を受けた後藤大平さんは、松田さんのケースについて「当時と何も変わっておらず、時が止まったようだ」と驚く。
一方で、「変わらなければという意識が企業にあっても手が回らず、実際に組織を変えるまで至らないケースはいまだに多い」と後藤さんは指摘する。
「夫が飲み会に誘われた」職場の無理解、妻は悲鳴
FJなどが昨年8月、妊産婦と夫らに対して実施した「コロナ禍の妊娠・出産」に関するインターネット調査(有効回答数558件)によると、里帰り出産の希望者はコロナ禍前は43%だったが、コロナ禍後は25%と減少した。高齢の親に対する配慮や、母子への感染に対する懸念、県をまたいだ移動制限などで、里帰りを控える人が増えたことがうかがえる。
さらに病院や自治体、NPOなどの両親学級も、一時休止になったり人数が制限されたりして、受講できた人の割合が大きく減少した。実家も支援機関も頼れない中、母子の孤立を防ぐには、夫の育児分担が不可欠だ。
しかし同じ調査の自由記述欄は「親に来てもらえず、両親学級もなく不安ばかりで毎日泣いていた」「激務の夫も積極的に育児をしてくれるが限界がある。(自分は)寝不足でボロボロ」といった母親の悲鳴であふれている。中には「夫は新生児がいると伝えているのに、歓迎会の主役として飲み会に誘われた」と、職場の無理解を嘆く声もあった。
改善しないテレワーク 古い企業風土に嫌気
松田さんは今年初めに転職した。育休取得を巡る会社側の対応だけでなく、古い企業風土に限界を感じたのも一因だという。
転職前の会社では、上司たちは「もう何日も子どもの顔を見ていない」と得意げに語り、「今日子どもの誕生日なんだよね」と言いつつ、だらだら残業している。コロナ禍で全社的にテレワークを始めたものの、社内システムがパンクして結局、社員は出社せざるを得なかった。受発注がいまだにファクスで行われるなど、業界にもリモート化を妨げる慣習が残っていた。
さらに2度目の緊急事態宣言が出された時、これらの仕組みが全く改善されていないことに、松田さんは深く失望した。「業界も会社も横並び体質で、新しいことに取り組むのを嫌がる。この職場に留まっても、自分と家族が望む形で働き続けるのは難しいと思いました」
同世代や若手の社員には、共働き家庭も多かった。しかし「会社はそんな現実から目を背け、『夫が大黒柱として稼ぎ、妻は家事育児』というジェンダー規範にしがみついている。その結果、社員の妻たちの勤め先から労働力を奪っています」と、松田さんは批判する。
職場では松田さんの退社と同時に若手2人が辞め、その後も離職者が相次いでいるという。「私の苦労を目の当たりにして、未来に希望を持てなくなったという若手もいました」と、松田さんは話した。
カギは「イクボス」づくり 採用の成否も左右
FJ東北理事の後藤さんは「仕事と育児を両立できる職場づくりは、人材の流出防止だけでなく、採用の成否にも大きく関わります」と指摘する。
「大学生は今、意中の企業の先輩とLINEなどでつながっています。企業の内情は『あの上司はやばい』といった人名まで含めて筒抜け。人を大事にしない会社は、学生本人から敬遠されるだけでなく、情報を就活仲間にまで拡散されてしまいます」
そして「人を大事にする」職場づくりのカギを握る存在こそ「イクボス」だと強調した。「管理職は『慣れ親しんだ方法で職場運営するほうが楽』と考えがちかもしれません。しかし『男は仕事・女は家庭』というバイアスを取り除き、性別に関係なく多様な働き方を選べる職場を作るには、キーパーソンとなる管理職の意識を変えることが、最も重要です」
子育てにほとんどタッチしたことのない男性上司の場合、こり固まった意識を変えるのは簡単ではない。しかし、具体的な情報を提供することが一つのやり方だと、後藤さんは言う。「出産で母体がどれほどダメージを受けるのか、成果を出しているワーママたちは、夫とどのように家事育児を分担しているのか、といった具体的な情報を伝えることで、部下の立場や葛藤を理解してもらい、両立可能な職場作りに取り組む必要があります」(後藤さん)
(取材・文 有馬知子)
[日経xwoman 2021年6月10日付の掲載記事を基に再構成]
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。