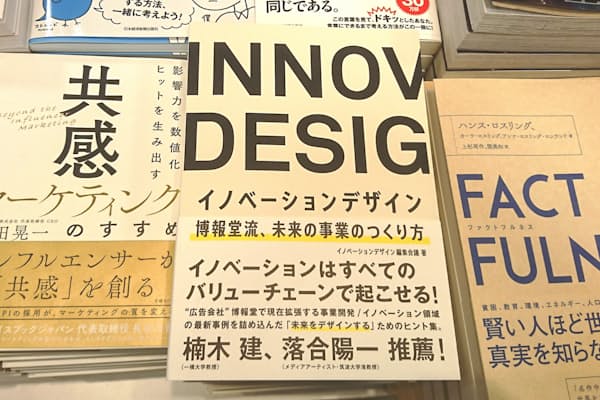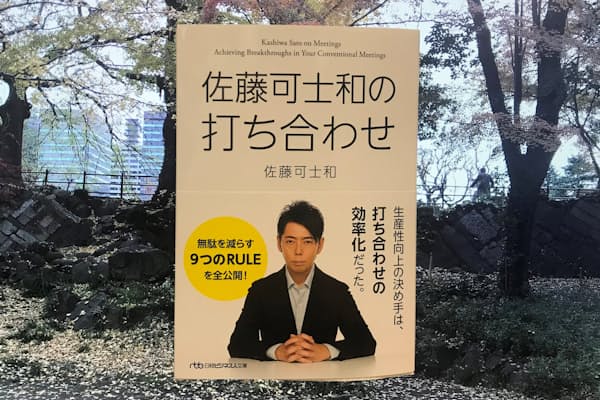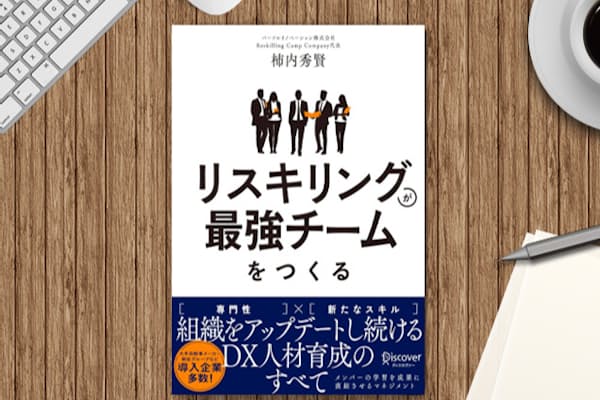博報堂人事の推し本 クリエイティブな仕事したい人へ

博報堂と博報堂DYメディアパートナーズの両社で人事部長を勤める沼田宏光さん
就活生から根強い人気を誇る広告業界。博報堂DYホールディングス傘下の博報堂と博報堂DYメディアパートナーズで人事部長を勤める沼田宏光さんは2冊の本を新入社員に薦めている。『ハイ・コンセプト 「新しいこと」を考え出す人の時代 富を約束する「6つの感性」の磨き方』と『凡才の集団は孤高の天才に勝る 「グループ・ジーニアス」が生み出すものすごいアイデア』だ。社内向けのSNS(交流サイト)で「ぜひ読んで」と紹介しているほか、就活生向けの会社説明会で言及することもあるという。
右脳を生かした思考が重要な時代
一冊目の『ハイ・コンセプト』は米国の作家・経営思想家のダニエル・ピンク氏の著書。2005年米国で発刊され、世界的ベストセラーになった。未来学者のアルビン・トフラーは1980年の著書『第三の波』で、農耕社会、産業社会に次ぐ情報化社会の到来を予言したが、ピンク氏は、さらにその先には創造性を求められる「第四の波」が迫っていることを豊富な事例で明らかにする。さらに、論理や分析など左脳主導思考の知識労働者が主役だった情報化社会に代わって、ハイ・コンセプト(新しいことを考え出す人)の時代には、クリエイティビティや共感など右脳を生かした思考が重要になると説く。「デザイン」「物語」「全体の調和」「共感」「遊び心」「生きがい」という6つのキーワードを使って、新しい時代を生き抜くヒントを示唆している。
沼田さんは06年、日本語版が出た直後に読んで衝撃を受け、以来何度も読み返してきた。
「15年以上前に出た本ですが『AI時代の~』とイマドキの枕詞(まくらことば)をつけても十分通用します。最近流行のアート思考やデザイン思考も、ベースはすべてこの本で語られている」

出版:三笠書房
ピンク氏はアル・ゴア元米副大統領の首席スピーチライターを務めたのち作家、経営思想家に転じ、『フリーエージェント社会の到来 「雇われない生き方」は何を変えるか』『モチベーション3.0 持続する「やる気!」をいかに引き出すか』などを発表。その先見性が高く評価されている。『ハイ・コンセプト』では、新たに到来する社会をリードするのは右脳主導思考ができる人だと指摘している。