がん治療の副作用を改善 鍵は「頑張りすぎない運動」
がんになっても働き続けたい~辻哲也さん(下)

働く世代のがん患者が仕事を続けるには、体力の回復・維持、身体機能の改善は大切な要素になる。近年、がんによる身体機能の低下や、手術など治療の過程で起こる障害に対するリハビリテーションが広がってきている。
自身もがんになったライター、福島恵美が、がんになっても希望を持って働き続けるためのヒントを探るシリーズ。日本のがんのリハビリテーションをけん引してきた、慶應義塾大学医学部リハビリテーション医学教室の辻 哲也教授に、前編「どんな『がん』でもリハビリ大事 体の機能低下を防ぐ」では、がんリハビリの役割を伺った。後編では治療中・治療後のリハビリの効果や運動の仕方を聞く。
運動が治療中の倦怠感を軽減する
――私は抗がん剤治療を受けていたときに、強い倦怠(けんたい)感に悩まされました。安静にしていた方がいいと思っていたのですが、2019年に第2版が出された「がんのリハビリテーション診療ガイドライン」[注1]には、化学療法・放射線治療中のリハビリが強く推奨されていて、「知っていれば運動したのに…」と残念な気持ちになりました。辻先生はこの診療ガイドラインの策定に携わられていますが、リハビリが強く推奨される理由をお聞かせいただけますか。
化学療法や放射線治療は、いろいろな病期のがん患者さんが行います。例えば乳がんの患者さんが手術後に根治率を高めるために補助療法として実施したり、進行したがんの患者さんなら延命のために行ったり、骨にがんが転移した痛みを止めるための治療だったりします。いずれにしてもこのような治療では、倦怠感や吐き気などの副作用がよく起こり、患者さんは「治療中だから安静にしないと…」とあまり動かなくなります。動かないと体力が低下し、疲れやすくなるからよけいに動かない、という悪循環が起こります。
しかし、身体機能や活動量をそれほど落とさないようにリハビリの運動療法を行えば、筋力や体力がついて倦怠感の症状がよくなり、体を動かすことで気分転換も図れます。すると、副作用が減り、治療を最後までやり遂げやすくなり、気分が上向きになり、総じて生活の質が上がります。もちろん、吐き気が強くて食べられないようなときに、無理に運動する必要はまったくありません。調子のいいときには体を動かそうと意識づけをし、寝た状態で不活動にならないようにしていくことがとても大事です。治療中は適度に運動し、治療後は社会復帰や元の生活に戻るために、しっかり運動することが重要になります。
[注1]公益社団法人日本リハビリテーション医学会 がんのリハビリテーション診療ガイドライン改訂委員会編『がんのリハビリテーション診療ガイドライン第2版』金原出版,2019.
有酸素運動と筋トレを習慣づけて
――がんで治療中、治療後の患者は、どれくらいの運動をしていくのがいいですか。
がんで治療中の方は、副作用の出方や体力レベルがそれぞれに違いますから、できるときにできることをやっていく、というくらいでいいと思います。とにかくベッドに寝てばかりいないで、座ったり、立ったり、できれば歩くというふうに。入院している方は病院内を歩く、通院治療中なら家の周りを散歩するところから始めます。この時期の運動の目安としては、疲れすぎず翌日も継続して行えるくらいがいいでしょう。調子が悪いときは休みます。そこから少しずつ歩くなどの有酸素運動に加えて筋トレ、ストレッチを組み合わせるのがよく、主治医とも相談して運動を習慣づけます。
治療後やがんの状態が落ち着き、もう少し強度を上げられる方は、中程度の有酸素運動(ウオーキング、ジョギング、エアロバイク、水泳など)を週に150分することが推奨されています。中程度というのは、例えば歩くなら会話はできるけれど、歌は歌えないというくらいです。1日に30分を週に5回、1日20分を毎日でも構いません。筋トレは1日おきに週3回(違う筋肉を鍛えるのなら毎日でも可)、例えばスクワットなら8~12回が目安です。筋トレは最後の1回がややきついと感じる強度を目安にします。このような運動ができる時期なら、スポーツジムなどに通うのも一つの方法です。ただし、運動していいかどうかは主治医に確認しましょう。
運動習慣ががんの死亡率を減らす報告も
――辻先生は、一般社団法人キャンサーフィットネスの顧問を務められています。がん患者やがんサバイバー(がん経験者)を対象に、フィットネス教室を行っている団体ですが、この活動への思いを教えてください。
キャンサーフィットネスの代表理事・広瀬真奈美さんとは、講演会でご一緒したときに知り合い、運動を通してがん患者さんを支援するのは大事な取り組みだと思いました。この活動が多くの人に広まるといいなという思いがあり、スタッフからの相談に応じたり、患者さん向けの講座で講義をしたり、団体のウェブサイトをチェックしたりして参加しています。
2020年12月からは会員制のオンラインサロンが始まりました。10分程の運動の動画が毎日のように公開され、後から動画を見ることもできます。コロナ禍で直接スタジオに行くことが難しい中、オンラインだといろいろな地域の方が参加できるので、副次的な効果が生まれてとてもよかったと思っています。がんサバイバーの方々は、再発予防の観点からも運動が勧められているので、運動の啓発普及をしていくこともとても大事だと考えます。
――がんサバイバーの中でも、特に乳がんになった方は運動した方がよい、と聞いたことがあります。
乳がんが中心ですが、運動習慣のある身体活動が高い方と、運動習慣がない方を比べた大規模研究があります[注2]。がんによる死亡率は、身体活動が高いほうが低く、乳がんだけでなく大腸がん、前立腺がん、脳腫瘍でも同じように報告されています。その明確なメカニズムは人では分かっていませんが、動物実験では腫瘍のあるラットに運動させると腫瘍が縮小することが分かっています。運動することで免疫が上がったり、体にダメージを受けやすい酸化ストレスが減ったりするからではないかと言われています。ですから、がんサバイバーの方は、生涯にわたって運動習慣を持つことが推奨されているのです。
――運動したほうが体にいいと分かっていても、なかなか習慣にならない人は、私を含めて少なくないと思います。そのような人たちにアドバイスをお願いします。
運動に限らず減量など、何かを継続して行うには、少し物足りないくらいのレベルで、毎日コツコツ続けるのがいいと思います。三日坊主になる人は、だいたい最初に頑張りすぎてしまいます。活動量計やスマートフォンの万歩計、ノートでもいいので記録を付けると、後から見返したときに、これだけ運動したと励みになります。家族や仲間と一緒に運動するのも、怠けにくくなる方法の一つです。運動の実際の効果は、2カ月から3カ月で現れてきますので、少し長い目でみてください[注3]。
[注2]J Natl Cancer Inst. 2012 Jun 6; 104(11): 815-840.
[注3]公益社団法人日本リハビリテーション医学会 がんのリハビリテーション診療ガイドライン改訂委員会編『がんのリハビリテーション診療ガイドライン第2版』金原出版,2019.
仕事をする上で大事な体力の回復
――がんのリハビリをけん引してこられた辻先生が、がんになっても働きやすい社会にしていくためには、どのようなことが必要だと思われますか。
患者さんとしては、運動を習慣づけることで体力がつき、仕事復帰がしやすくなると思います。がん患者さん約4000人を対象にした、仕事に関する悩みのアンケート調査[注4]では、1位が「体力の低下」、2位が「病気の症状や治療による副作用や後遺症による症状」と、リハビリに関わるところがとても多いのです。体力を回復するため、治療中からの体力づくりが一番大事だと考えています。がんの治療による副作用や後遺症には、肩が上がりにくい、手足がしびれるなどいろいろですが、運動することで改善するものもあります。また、細かい手の動きができないのであれば、自助具を使う方法もあります。リハビリ科のある病院では、そのようなサポートができますから、相談してもらうといいと思います。
職場では、患者さんが体力の低下や副作用、後遺症で悩んでいることを共有し、環境面で配慮することが大切です。例えば、リンパ節を切除することでリンパの流れが滞って足や手などがむくむリンパ浮腫の患者さんは、ずっと座り続ける仕事はつらいものです。配置転換などをして仕事が継続できるように、主治医と職場の産業医や上司らが話し合える関係をつくることも重要だと思います。
[注4]『2013がん体験者の悩みや負担等に関する実態調査報告書 がんと向き合った4,054人の声』(「がんの社会学」に関する研究グループ)https://www.scchr.jp/book/houkokusho/2013taikenkoe.html
――最後に読者にこれだけは伝えておきたい、ということはありますでしょうか。
私が考えた「がんのリハビリ5カ条」ですね。今回のまとめとしてこの5つをお伝えしたいと思います。
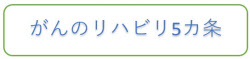
2.がんと診断された直後から、リハビリ科スタッフのサポートを積極的にうけましょう
3.手術前と手術後は早期からリハビリを受けて、合併症を防ぎ、後遺症を軽減するようにしましょう
4.薬物療法や放射線療法による体力低下・副作用の改善、症状軽減、生活の質(QOL:Quality of Life)の向上にもリハビリは有効です
5.積極的な治療ができなくなった時期にも、リハビリは症状緩和、日常生活支援、QOLの向上に有効です
◇ ◇ ◇
(ライター 福島恵美)

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。















