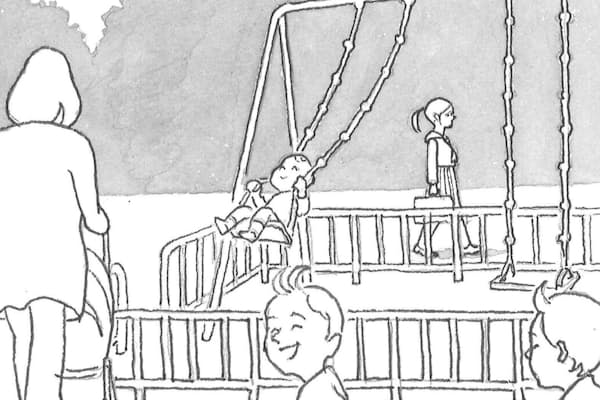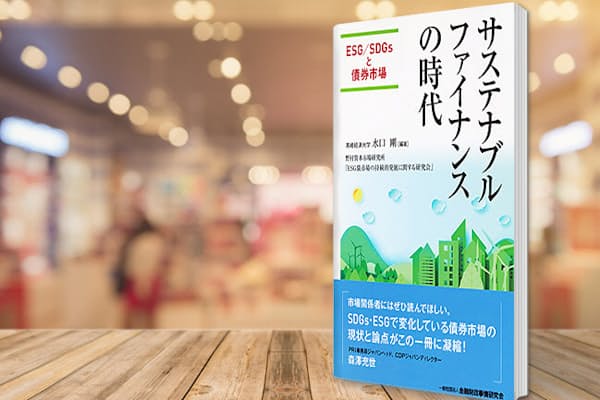1食100円弱で過ごしたパックン 子供の貧困解決に動く
タレント、東京工業大学非常勤講師 パトリック・ハーラン氏

子供たちの未来のため
日本社会に支援の輪を広げたい
――多方面で活躍しているパックンことパトリック・ハーランさん。最新刊『逆境力』では、厳しい経済環境下で育った少年時代のエピソードを紹介しながら、日本の子供の貧困の実情と、問題解決に向けた行動を提唱しています。執筆のきっかけは。
日本は、公教育も社会保障もしっかりしたいい国だと思いますが、半面、貧困に苦しんでいる人の存在が見えなくなっていると感じます。良くも悪くも「一億総中流」の意識が強く、皆が普通に暮らせていると思い込んでいる人が多い。でも、日本にも貧しい暮らしを余儀なくされている人たちは確かに存在していて、その割合は年々増加しています。
僕は米国で育ちましたが、小学校低学年の時に両親が離婚して、母と2人だけの貧しい家庭で育ちました。食事は1人1食89セント(100円弱)、10歳から新聞配達のアルバイトで家計を支えました。母や周囲の人のサポートもあり、大学に行くこともできましたが、「お金がない」という不安と劣等感を抱えて生きるのはとてもつらかった。貧困で苦しむ子供の気持ちが分かるからこそ、その現実を多くの人に知ってもらい、支援につなげたいと思ったのです。
――タレントとして活躍されている今も、「貧乏だった子供時代」が心に深く刻まれているそうですね。

僕の心の中には今でも、コンプレックスと劣等感でいっぱいの少年が生きています。その彼が僕に言うんですよ。「過去の自分を忘れていないよね?」「日本にも貧困で苦しんでいる子供たちがたくさんいるのに助けてあげないの?」って。良心の声だと思います。
せっかく今、メディアで発信できる立場にいるのだから、貧困に苦しむ日本の子供たちのためにできることをしたい――そんな思いが、年々強くなっていました。
――本書では厳しい経済環境を生き抜く知恵や工夫が詳細につづられていますが、パックンの前向きさに加え、周囲の温かいサポートも印象的でした。日本に比べ米国は、社会全体で子供をケアしようという意識が強いのでしょうか?
日本と米国の違いは2つあると思います。まず、米国では社会に貧困が存在することを皆、分かっています。そこに対する支援が必要だということも。日本の多くの人はそこが分かっていない。
2つ目に、日本人にはそうした支援は「国がやってくれるもの」と考える癖があります。米国人は違います。「政府は何もしてくれないから、自分たちで何とかするしかない」と思っています。だから個人同士が助け合うのです。
日本では地域社会のつながりがどんどん薄くなり、家庭環境が厳しい子供が孤立してしまいがちです。社会のセーフティーネットからこぼれ落ちてしまう子供をこれ以上増やさないために、今すぐ対策が必要だと思います。