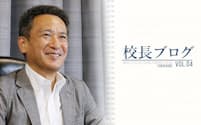学校現場に脳科学を 「三日坊主」責めるのは間違い
工藤勇一・横浜創英中学・高校校長
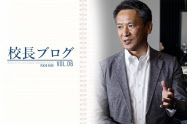
この4月で横浜創英中学・高校の校長として2年目を迎えました。2020年度は、自律した生徒を育てることを最上位目標に掲げ、全教職員で目標実現のための課題を洗い出し、改善策の全てを今後5年間の中期的成長戦略として整理しました。21年度はいよいよそのスタートです。自律した生徒を育てていくための環境づくりと教師の支援の在り方の研究については、東京都千代田区立麹町中学の校長時代にも多くの試みを行ってきましたが、中でも非常に有効だったのが脳科学の活用です。
脳科学者と出会い、麹町中で3年間共同研究
4年前、元経済産業省の方の仲介で麹町中に突然1人の若い脳科学者が訪ねてきました。米カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)で神経科学を学んだ青砥瑞人さんです。神経科学が今後の教育を大きく変える可能性があることについて、私に熱く語ってくれました。近年、脳神経科学の研究は急激に進歩しており、脳のどの部位がどんな機能をもち、特定の環境、アプローチで脳がどのように変容するのかということが次々と科学的に解明されているそうです。青砥さんの話は、従来の学校教育の問題点をなかなか上手に説得し切れない歯がゆさを感じていた私に大きな勇気を与えてくれました。

この出会いがきっかけとなって、青砥さんと共に脳科学を活用した教育のあり方について研究を始めたのです。約3年間の研究成果は、生徒へのアプローチの方法にとどまらず、学校運営システムや教育環境、教員自身の人材育成の方法など広範囲にわたり、振り返れば学校教育の在り方のすべてを一から問い直してくれるものとなりました。(麹町中での実践研究については20年2月に文部科学省で行われた研究発表会の様子がユーチューブで公開されています)
青砥さんと麹町中で始まった研究でしたが、2年目からはドキュメンタリー映画「みんなの学校」で有名な大阪市立大空小学校の初代校長の木村泰子さんや、フェイスブックなどを通じて全国から延べ200人以上の一般の方々も参加したことにより、その後2年間の研究は一層実効的なものへと成長していきました。
この研究で特に注目したのが、「心理的安全性」と「メタ認知能力」です。
「心理的安全性」→失敗しても大丈夫な環境づくり
心理的安全性とは、端的に言えば「強いストレスがかかっていない状態、心理的に安心できている状態」のことです。人間の脳が深い思考をしたり、理性的な判断を下したりするためには心理的安全性の確保が不可欠なのだそうです。その指摘から、子どもたちに『失敗しても大丈夫だよ』という環境を作ることが学校や家庭の重要な役割であることがひとつ大きなテーマとなりました。
青砥さんからの受け売りですが、脳科学の視点からもう少し専門的な話を加えたいと思います。人の脳には前頭前皮質と呼ばれる部位があります。人のおでこの裏から頭頂部にかけてある大きな部位で、様々な高度な機能を担う重要な部位だそうです。この部位は人が心理的安全状態にあると活発に働き、逆に人が心理的危険状態にあると前頭前皮質の機能が著しく低下することがわかっています。
心理的危険状態の例としては、何かミッションを実行しなければならない場面で強い緊張状態にあるときや、誰かと言い争いになっていたり、強く叱責を受けたりしているときを想定してみてください。そんな状況に置かれたとき、低下する機能の代表的なものには「感情をコントロールする機能」「意識的な注意や思考をする機能」「不適切な行動を抑制する機能」などがあります。

大声で怒鳴られ続けている子どもが「お前、話を聞いているのか」などと、さらに叱られている場面を見かけることがありますが、心理的危険状態では思考する部位が機能しなくなるのですから、叱っている大人の声が耳に入ってこないのは当然でしょう。
最近、米グーグルをはじめとして、多くの企業で「心理的安全性」を確保することが創造的な組織を作る上で重要な条件だということが言われていますが、こんな事例からもお分かりいただけるのではないでしょうか。
「メタ認知能力」→トラブルを学びに変える
とはいえ、社会に出ればストレス要因はいくらでもあります。
心理的安全性が大切だからといって、もし学校を完全にストレスフリーにできたとしても、そんなことでは逆にストレス要因を乗り越える力は育ちません。そこで重要になることが、トラブルを経験するなかで、葛藤や失敗といったネガティブな記憶をポジティブな学びに変えていくために必要な能力、それが「メタ認知能力」です。
青砥さんの説明によればメタ認知能力とは、自らを俯瞰(ふかん)的に見て、第三者的な視点に立って自分自身をより良い方向に上書きしていく能力ということですが、この力は本人の課題解決能力や目標達成能力を大幅に底上げするだけではなく、新たな課題に直面したときに子ども自らが心理的安全性をつくりだす能力も高めることになるため、これからの激動の時代を生きるためにますます必要となるスキルだと言えます。
もう一つのメタ認知能力については「三日坊主」という事例を挙げてお話ししたいと思います。
三日坊主はほぼ全員が経験しているはずです。学校で「三日坊主になったことがない人っている」と聞いても、手を挙げる子どもはまずいません。その一方で「三日坊主って恥ずかしいことだと思っている人は?」と聞くと、今度はほぼ全員が手を挙げます。それは「うまくいかなかった原因は自分が頑張らなかったからだ」と失敗体験と精神論をひもづけてしまっているからです。真面目な子は燃え尽き症候群になりやすいと言われますが、その理由はこの延長線上にあります。
しかし、青砥さんの説明によれば、脳は本来、新しいことやこれまでの自分とは異質なことには頑張るようにできていません。脳が勝手にストップをかけようとするわけです。つまり、「頑張れない自分はだめだ」と自分を責める必要はなく、むしろ三日坊主を精神論で乗り越えることこそ間違っていることになります。
優れた人は自分のありのままをよく知っています。続けられない自分を見つめ、続けるための仕掛けを工夫します。このような力が「メタ認知能力」ということができます。
イチロー、ダルビッシュの続けるための工夫
アスリートの中にはこの能力が優れた人たちが大勢います。
例えば元大リーガーのイチローさんです。イチローさんは様々なルーティーンで有名ですが、それらは、まさに続けるための仕掛けだということができます。
野球の米メジャーリーグで活躍中のダルビッシュ有選手は多彩な変化球を繰り出す好投手として知られていますが、彼は自宅に練習場をつくり、投球している姿をビデオで常時撮影し、ボールの球速や軌道、回転数などを解析し、変化球の研究をしているそうです。監督やコーチからフォームをこうしろ、ああしろといちいち指示されているわけではありません。解析機器を使い、データを解析することで第三者目線となり、メタ認知能力を高めているわけです。
二刀流で知られる大谷翔平選手もメタ認知能力が高い一人です。超一流の選手となったのは天性の才能と練習のたまものと思われていますが、高校時代に、自分で作成した目標達成シート「マンダラート」も奏功したと言われています。9×9のマスをつくり、真ん中のマスに自分の成し遂げたい目標、他の8マスに目標達成の要素をそれぞれ書き記しています。自分を客観分析し、目標を明確にしたのです。
驚いたことに、すでに高1の頃に真ん中のマスに「ドラフト1位で8球団から指名」、その右隣のマスに「スピード時速160キロメートル」と目標達成の手段を記しています。さらに時速160キロという目標達成のため、「肩まわりの強化」など8項目の達成手段・要素なども記しています。このチャートを部屋の中に貼って、常に自分の目標と達成手段・要素を確認していたそうです。
脳とは実に不思議なもの。心臓が飛び出すほどの緊張場面、緊張を解こうと意識すればするほど緊張は増すばかりなのに、何度か大きく深呼吸するだけで血圧が下がり、気持ちまで落ち着くなどということも、脳の仕組みを理解すれば理にかなったことのようです。
子どもたちに一方的に与え続ける教育が、なぜ子どもの主体性を奪うのか、精神主義的な指導方法が、なぜ子どもたちを劣等感でいっぱいにしてしまうのか、これまで多くの人々が強い違和感を感じながらも長い間変えることのできなかった日本的な教育方法の問題も最新の脳科学の研究の理論を活用していけば、確実に説明できそうです。脳科学は今やスポーツ界だけでなく、世界中のあらゆる分野で活用させるようになってきましたが、今後はよりよい教育にアップデートするために大いに活用されていく時代が来ることを確信しています。
1960年、山形県生まれ。東京理科大学理学部卒。1984年から山形県の公立中学校で教えた後、1989年から東京都の公立中学校で教鞭(きょうべん)をとる。東京都教育委員会などを経て、2014年から千代田区立麹町中学校の校長に就任。宿題や定期テスト、学級担任制などを次々廃止するなど独自の改革を推進。2020年4月から現職。青砥瑞人さんと共著で「最新の脳科学からわかった!自律する子の育て方」(SB新書)
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。