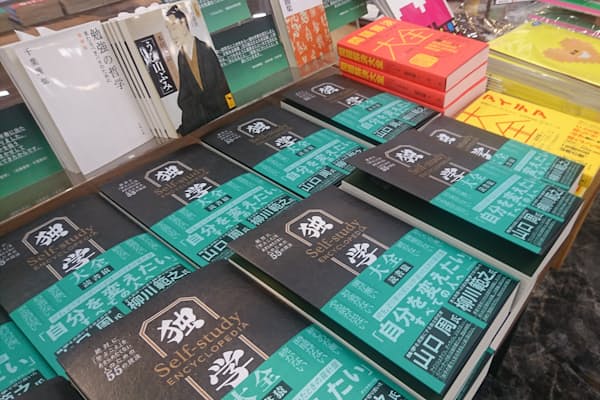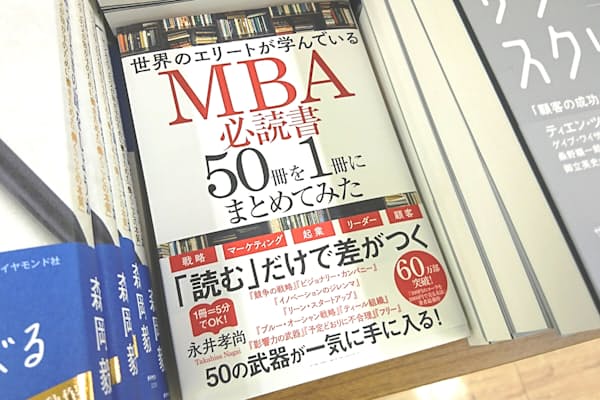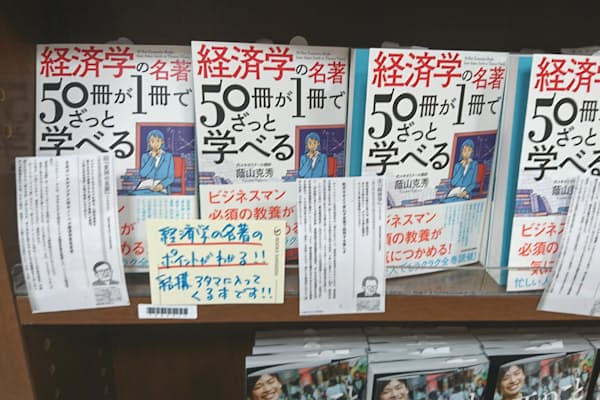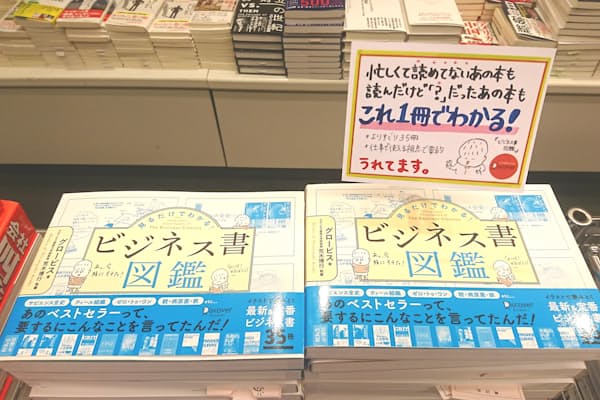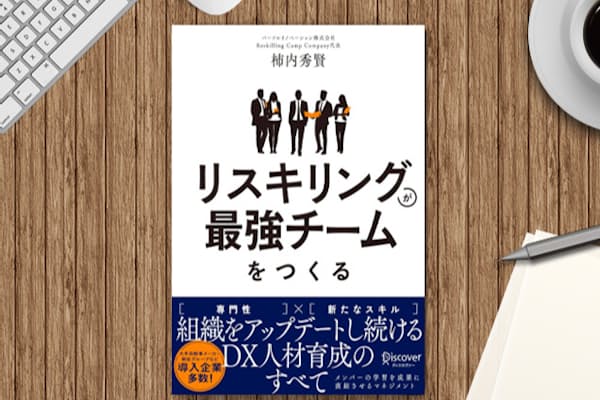「なんでも読む」ではダメ 本を自分の力にする読書法
『読書大全 世界のビジネスリーダーが読んでいる経済・哲学・歴史・科学200冊』より

『読書大全』著者の堀内勉氏
『読書大全 世界のビジネスリーダーが読んでいる経済・哲学・歴史・科学200冊』(日経BP)の著者、堀内勉氏は、次世代のビジネスをけん引していく若者こそ、真の読書体験によって、常日ごろから人間としての練度を高めておく、つまり人間としての知性の基礎体力や体幹を鍛えておく必要があるという。インターネットで様々な情報が手に入る今日、そもそも読書にはどういう意味があるのか。『読書大全』の一節から見ていこう。
◇ ◇ ◇
「自分の頭で考える」ための読書
読書は、重大な選択を迫られたとき、危機的な状況に陥ったとき、人生の岐路に立たされたときに、正解のない問いに答えるための「一筋の光明」ともなるものです。
しかし、どんな本でもとにかく読めばいい、というものではありません。

『読書大全』(日経BP)
そこでここでは、読書に当たっての注意点をいくつか挙げておきたいと思います。
まず、読書の目的は、本をたくさん読むこと、たくさんの知識を身につけることではないということです。良い本をじっくりと読んで、それを自分のものにした上で、さらに自分の頭で考えるということを目的とすべきです。
哲学者のアルトゥル・ショーペンハウアーは、読書の方法論を論じた『読書について』の「自分の頭で考える」という章で、以下のように乱読を戒めています。
どんなにたくさんあっても整理されていない蔵書より、ほどよい冊数で、きちんと整理されている蔵書のほうが、ずっと役に立つ。同じことが知識についてもいえる。いかに大量にかき集めても、自分の頭で考えずに鵜呑みにした知識より、量はずっと少なくとも、じっくり考え抜いた知識のほうが、はるかに価値がある。(中略)
自分の頭で考えてたどりついた真理や洞察は、私たちの思想体系全体に組み込まれ、全体を構成するのに不可欠な部分、生き生きした構成要素となり、みごとに緊密に全体と結びつき、そのあらゆる原因・結果とともに理解され、私たちの思考方法全体の色合いや色調、特徴を帯びるからだ。(中略)
本を読むとは、自分の頭ではなく、他人の頭で考えることだ。たえず本を読んでいると、他人の考えがどんどん流れ込んでくる。これは、一分のすきもなく完璧な体系とまではいかなくても理路整然たる全体像を展開させようとする、自分の頭で考える人にとって、マイナスにしかならない。
自分の頭で考えてたどりついた真理や洞察は、私たちの思想体系全体に組み込まれ、全体を構成するのに不可欠な部分、生き生きした構成要素となり、みごとに緊密に全体と結びつき、そのあらゆる原因・結果とともに理解され、私たちの思考方法全体の色合いや色調、特徴を帯びるからだ。(中略)
本を読むとは、自分の頭ではなく、他人の頭で考えることだ。たえず本を読んでいると、他人の考えがどんどん流れ込んでくる。これは、一分のすきもなく完璧な体系とまではいかなくても理路整然たる全体像を展開させようとする、自分の頭で考える人にとって、マイナスにしかならない。