東大院修了しピアニストに 目指すは新たな音楽の形
ピアニスト 角野隼斗さん

東京大学大学院在学中に日本最大級のピアノコンクールでグランプリを受賞したことをきっかけにプロの道を本格的に歩み始めた若きピアニスト、角野隼斗(すみの・はやと)さん。「Cateen(かてぃん)」という名前で演奏動画を配信するユーチューブチャンネルの登録者数は70万人を突破し、人気ユーチューバーとしての顔も持つ。多彩な活躍を見せる角野さんは20年春、大学院を修了したばかり。学生時代に人工知能(AI)を研究していた角野さんに、研究から学んだことや音楽活動との相乗効果などについて聞いた。
研究で「音色」について考え深めた
――東京大学大学院情報理工学系研究科を修了し、ピアニストの道に進みました。どのような思いがありましたか。
「『音楽が趣味ではないかも』と思い始めたのは、大学院1年生の夏に第42回ピティナ・ピアノコンペティションという非常に大きなコンクールでグランプリを頂いてからです。それは当時の僕としても大きな驚きでしたが、同時に、中途半端な気持ちでピアノはできないというプレッシャーや責任を感じることの方が、喜びよりも強かったです」
「最初は研究者と音楽家を両立しようと思っていました。ですがそのうち、自分は別に研究成果をあげたいわけではないと気付き、今は音楽を全力でやろうと、音楽の道を選びました。それでも、自分や他人の演奏がどうなっているのかを解析して理解するために音響的な分析をすることはあるので、音楽表現に生きる形で研究を活用していくと思います」
――大学院での研究はどんな内容だったのですか。
「機械学習の手法を用いた自動採譜・自動編曲です。実際に演奏された音楽を機械が『耳コピ』で楽譜にできるかどうか、というイメージです。既存の自動採譜の手法は、実際のピアノの音源と、それに対応するピアノのMIDIデータ(音程や長さ、強さを記録した演奏情報)、つまり『正解』を用意します。機械学習のネットワークにピアノ音源を入力すると『MIDIピアノロール』というピッチ(音の高さ)と時間の2次元データが出てくるので、それが正解のMIDIデータとどのくらい離れているかを計測して学習精度を上げていきます」
「ただ、ピアニストとして既存の手法に違和感がありました。例えば半音だけ違った音が入ると目立ちますが、オクターブで重なっていることは、耳で聞いたときに不自然ではない。しかし既存の手法だと、どちらも間違いと認識されてしまう。人は耳で音楽を聞くものです。そこで、出力されたピアノロールを再度ピアノで弾いてみて、MIDIデータではなく、音と音で比べるという学習方法を提案しました。この方法だと正解データがない場合でも、音だけ用意されていれば学習ができるので、大量の学習データを必要とする機械学習の弱点を補えると考えました」
――そういった研究で、どんなことを解き明かしたいと思っていたのですか。
「このような研究をしていると、音色がどうなっているのかを改めて考えるきっかけになりました。ピアノの仕組みを考えると、ハンマーが弦に当たる瞬間の速度だけで音色は決まるはずです。ですがピアノをやっている人間からするとそれだけでなくて、様々な打鍵方法によって音色が変わると思っていますし、そもそも音色とは音を出す微妙なタイミングや音量のバランスなども含めて我々は音色だと感じています。このように音楽を要素分解して、機械でどう再現できるかを考えていました」
AIは人の演奏を再現できる?
――機械やAIが、人間が演奏しているように音楽を再現することはできるのでしょうか。
「コンピューターで音楽を制作するとき、DAW(デジタル・オーディオ・ワークステーション)というソフトを使って弦楽器の抑揚を設定したりしますが、それは半分機械にやってもらっているようなものです。実際に人間が弾いてはいないけど、音源をパソコンで組み合わせることで人間が弾いているように表現しています。それを今後、機械がどこまで自動でできるようになるかという話で、すでに大抵の人に違和感がないように作ることはできると思います。そういう意味で言えば、機械は人間が演奏しているように音楽を再現できると言えます」

「AIについては、全て見せ方の問題だと思っています。『AIが自動演奏をする』『AIが作曲をする』などと言いますが、実際は人間がシステムを作っているだけで、AIが自律的に考えてやっているわけではない。それを人間がやっているように見せるのか、AIがやっていると見せるのか、それはプロデューサーの戦略だと思います」
――音楽活動と研究は相乗効果がありましたか。
「そうですね。大学院のときの研究アイデアも自分が音楽をやっているところからきているので、他の研究者とは違うアドバンテージになりました。自分の耳コピやアレンジが機械でどう再現できるのかを考えることは、リズム感やタイミングといった人間が無意識にできていることがどうなっているのかを要素分解していくことにつながります。そういう無意識にやっていることを分析できていた方が、音楽表現の助けになると思っています」
「アカデミアの世界というのは、既存研究のサーベイ(調査)とそれに対する検討や考察があります。それらを踏まえ、新規性を出すことができて初めて論文になります。この考え方のスキームは、音楽をやる上でもYouTubeをやる上でも同じだと思うんです」
「音楽やYouTubeで自分の立ち位置を確立している人は、明らかに他の人にないものを持っていて、それは研究で言う新規性です。ですがそのオリジナリティーを出すためには、今まで人類がどういうことをやってきたのかを知る必要があります。そうでないと『車輪の再発明』になってしまう。僕は自分自身が、人間の過去から学んでそれを未来に生かしていくという意識がすごく強い。それは短期間でもアカデミアの世界にいたからなのかもしれません」
「東大生ピアニスト」と言われていたときのプレッシャー

――順風満帆に失敗の少ない人生を歩んでいる印象がありますが、プレッシャーやコンプレックスに悩むこともありますか。
「一時期『東大生ピアニスト』と言われることが非常に多かったのですが、それはピアニストとしての中身が伴って初めて成立する肩書です。そうでないと単に『東大生』というピアニストと何の関係もない要素が加わっただけで、音大にも行っていないし、きちんとした音楽教育を受けていないと思われかねない。そうならないために、東大生であるということとは全く関係なく、自分の立ち位置を確立しなければならないというプレッシャーはずっと感じていました」
「コロナ禍の昨年3~4月は家にこもって、作編曲や演奏動画を配信するYouTube活動に集中していました。2019年と比べても2020年はピアニストとして自分が思っていた活動がやりたいままに実現できた気がしますし、YouTubeのチャンネル登録者数も5倍、6倍と伸びていったのは、すごく自分の中での自信につながりました。それもあって最近は東大生ピアニストという肩書は気にならなくなりましたね」
いつか「AIオーケストラ」を
――今後の展望、目標は。
「現在の肩書はピアニストですが、『音楽家』になりたいと思っています」
――「音楽家」とは。
「明確な定義はありませんが、(グラミー賞を受賞した)イギリスのマルチ楽器奏者ジェイコブ・コリアーのように、演奏の裏にある『音楽を表現』するという部分を強く持った人や、創造性の高い人が音楽家だと思います」
――どんな音楽を作りたいですか。
「クラシック音楽はめちゃくちゃすごい人類の遺産だと思っています。ですが、このままだとどんどん過去の音楽になってしまう。それが怖い。だから僕はクラシックを他のジャンルと掛け合わせて新しいものを作っていきたいと強く思っています」
――音楽とAIの組み合わせで何かやってみたいことはありますか。
「いつか自分の演奏を完全再現できるAIができていたら面白いなと思います。自分がこうすれば相手(AI)はこう返してくるということがわかっているから、デュエットしたら自分の表現の幅が2倍になる。そういうのがいくつもあれば、自分の思い通りに演奏できる機械のオーケストラができるはずです。しかも機械なのでものすごく高度な曲でも練習する必要がない。AIでそういうことができるようになったら、おそらく新しいものができるんじゃないでしょうか」
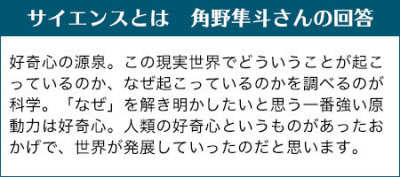
1995年生まれ。千葉県出身。開成高校卒業後、東京大学工学部に進学。2018年、ピティナ・ピアノコンペティション特級グランプリ、および文部科学大臣賞、スタインウェイ賞を受賞。19年リヨン国際ピアノコンクール第3位。これまでにブラショフ・フィル、日本フィル、千葉響などと共演。18年9月より半年間、フランス国立音響音楽研究所(IRCAM)にて音楽情報処理の研究に従事。留学中にクレール・テゼール、ジャン=マルク・ルイサダに師事。20年、東京大学大学院を修了。
(聞き手はライター 橋口いずみ)
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。














