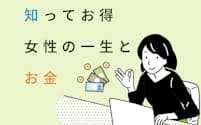賢い夫婦の資産づくり 月1回の会議で貯蓄額アップ
知ってお得 女性の一生とお金(最終回)
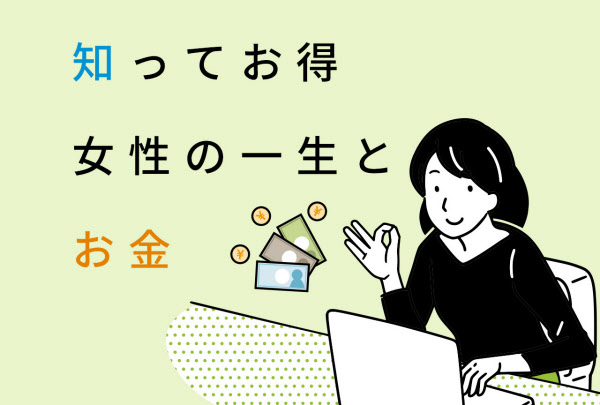
それぞれの収入で自分名義の資産をつくる
家計の現状や今後の計画については、共働きかそうでないかにかかわらず、夫婦で風通し良く話し合うことが大切です。それぞれの家庭には今後のライフプラン(住宅取得、子育てなど)があり、夫婦の希望や意見をすり合わせ、実現に向け協力して資金づくりを進める必要があるからです。そのための家計管理についても、双方が納得できる方法をとりましょう。
共働き世帯の場合、家賃や公共料金は夫の銀行口座から引き落とし、食費や日用品は妻が購入といった支出の分担をするケースが多いと思います。そのような方法をとる家庭は、できれば月に1回会議を持ち、実際に支払ったお互いの負担額を把握しておくといいでしょう。どちらかの負担が多すぎる月など、バランスを修正することができます。
家計を管理するための銀行口座を夫婦どちらかの名義でつくり、収入に応じた割合で拠出する方法もあります。家賃や公共料金などはもちろん、生活費のためのクレジットカード(家族カードも)をつくり、その引き落とし口座にすれば、かなり楽に家計が管理できます。定期的に会議を持って、使いすぎていないか明細をチェックするといいでしょう。
それぞれの収入は拠出額以外、自分の口座に残るわけですが、話し合いにより貯蓄目標額を決め、その額をつくるのに必要な積立額を月々きちんと貯蓄することが大切です。そうでないと、残ったお金を自由に使ってしまうことになりかねません。また、夫婦のどちらかの名義に偏らないよう、それぞれの収入による自分名義の資産をつくるようにしましょう。
非課税の積立制度を活用
どのような方法で貯蓄をするかは、使う時期や目的により違ってきます。不測の事態に備えての貯蓄や数年以内のライフプランに使う貯蓄は、元本が保証されていつでも引き出せる預貯金で積み立てることです。勤め先に財形貯蓄制度があれば一般財形、住宅の取得を計画しているのであれば財形住宅を利用しましょう。低金利下で預貯金類の収益性は魅力が薄いですが、積み立ては使えないお金を家計から取り分ける機能と考えるべきです。
使う時期が10年以上先というライフプランであれば、投資信託での積立投資も選択肢になってきます。投信などのリスク商品を一定の金額で定期的に積み立てていく方法は、価格が高い時には少ない口数を、安い時には多い口数を購入するため、平均購入単価を抑える効果があるとされ、長期的には値上がり益が期待できるからです。
投信で積み立てるなら、運用益(分配金・売却益)が非課税になる「つみたてNISA」を利用するといいでしょう。制度に適するとして用意された投信の中から選び、年間40万円まで積み立てられます。積立時から最長20年間非課税で運用できますが、引き出しはいつでもできます。
資金づくり、複数の手段や金融商品で
老後資金も少しずつためていけるのが理想なので、余裕があれば個人で加入できる確定拠出年金「iDeCo」を利用するといいでしょう。運用益が非課税になるほか、所得税・住民税の軽減といった税制上のメリットがあります。ただし、60歳まで資金の引き出しができない点には要注意です。
資金づくりのコツは、ひとつの手段、ひとつの金融商品で行わず、複数の手段や複数の金融商品を組み合わせること。貯蓄商品は安全ですが低金利、投信は収益性が期待できるけれども値動きするという、それぞれのメリット・デメリットをカバーし合うことができます。
アラサー世代でもがん関連の保障は備えて
家計に負担なく生命保険に加入するポイントとしては、(1)保障したいリスクの優先順位をつける、(2)すでに備わっている公的保障・勤め先の保障を確認する、(3)コストパフォーマンスのいい保険商品を選ぶ――が挙げられます。
保障したいリスクには、死亡、医療、介護、就業不能、老後、などがあります。アラサー世代に優先順位の高い保障は、死亡、医療、就業不能になるでしょう。ただし、死亡保障は、まだ子供がいないなどお金を残さないと経済的に困る家族がいなければ、大きな保障を備える必要はありません。
医療保障については、入院日数が短くなる傾向が続いているなか、従来型の入院日数による保障のものから、一時金式に給付を行うものが増えるなど、商品性が変わりつつあります。いま過渡期にありますから、すでに加入しているものがあればそれを継続し、新しく加入するのは待ったほうがいいでしょう。
アラサー世代でも、がん関連の保障は備えておくと安心です。がんは早期発見・早期治療で社会復帰できる病気になっていますが、治療期間が長引けば、治療費や治療中の収入ダウンにより資金計画に支障が出ると考えられます。がん保険、就業不能保険でカバーすることができます。
保険の入りすぎに注意、公的保障を確認
保険により家計のリスクを守ることはできますが、入りすぎると保険料の支出が家計への負担となります。死亡も医療も就業不能も、公的保障や勤め先の保障でカバーできる部分がありますから、どのような保障が自分に備わっているか確認し、不足分を加入するようにすれば入りすぎを防ぐことができます。
例えば、死亡の公的保障は公的年金が「遺族年金」として担い、勤め先にも死亡退職金などの制度があると思います。医療の公的保障は健康保険の「高額療養費」に代表され、加入している健保組合によっては上乗せの付加給付を行うところも少なくありません。勤め先の福利厚生制度もチェックしておきましょう。就業不能保障についても、健康保険の「傷病手当金」や公的年金の「障害年金」がベースの保障となります。
同じ内容の保険であれば、保険料が安いほうが家計にプラスです。インターネット経由で賢く加入できる時代ですから、必要最小限の保障を安く備えるようにしましょう。
◇ ◇ ◇
この連載は今回が最終回となります。暮らしに関わる制度、金融商品や保険の上手な利用法など、アラサー女性の将来設計に役立つ知恵やヒントをご紹介してきましたが、活きた情報としてお伝えできたなら幸いです。今までご愛読ありがとうございました。またの機会にお会いしましょう。

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。