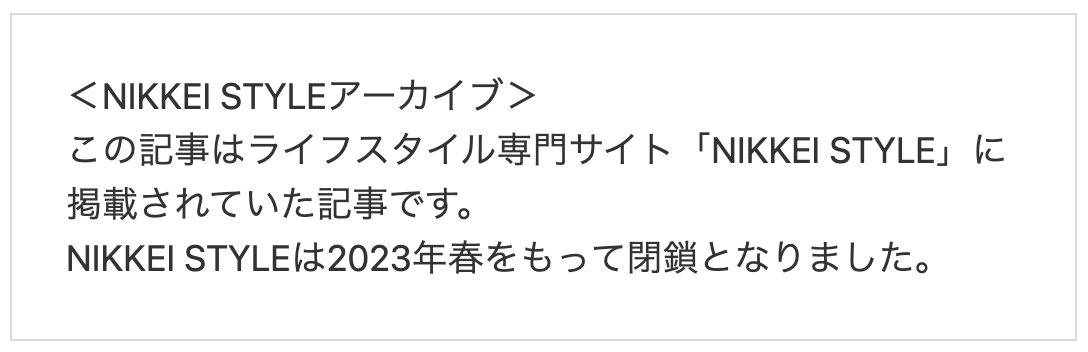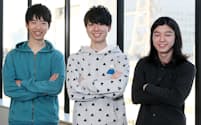いつか必ずみんなで 胸に恩師の言葉、災害支援の道へ
震災10年・離れて今(2)福島県 中島穂高さん

中島さんは中学1年のときに被災し、約半年間の避難生活を余儀なくされた。新型コロナウイルスの感染が広がっていた2020年春に早稲田大学を卒業し、日本赤十字社に入社した。「災害時に役に立てる存在になりたい」と考えたという。
――きれいな花畑の写真を「故郷の1枚」として選んでいただきました。どうしてこの風景を。
「ここは海沿いの南相馬市原町区萱浜(かいばま)という場所です。19年5月の帰省時に朝4時半に起きて、日の出のときに撮りました。ここは震災時、全部津波で流された土地です。地震と津波と原発事故、3重の被害を受けた場所で、自分にとっても原点のようなところです。この近くに家がある上野敬幸さんは子供と両親を亡くし、天国にメッセージを送りたいという思いで、この菜の花の迷路を作られていて、自分も種まきを手伝ったりしていました」
「今では子どもたちが駆け回っていて、ここで本当に被害があったのかと忘れてしまうぐらいきれいに咲き誇っていて。天国にいる上野さんのお子さんも見てくれているのかな、と思いながら眺めていました。上野さんとは『お互い笑いあえる場所を作りたいね』という話をしました」
「死を覚悟した」中学1年
――原発事故の発生後、中島さんの実家がある南相馬市原町区などは緊急時避難準備区域(第1原発から20~30km圏内)に指定されました。当時はどんな状況でしたか。
「1号機の爆発があったのが3月12日。その日の夜にまず(北の隣接市である)相馬市の避難所に家族で身を寄せました。自宅を出るとき、この家にはもう帰ってこれないだろうな、と思いましたね。子供でも原子炉の事故って、ただごとではないとわかりますから。まさに死を覚悟しました」
――放射線の恐怖を感じながらの避難生活、どんな心境でしたか。
「避難所が高校だったので教室で寝泊まりしていたのですが、仮設トイレが外にあって、体育館の前を通るんです。その体育館には、津波で亡くなった方のご遺体が運ばれてきていました。救急車がサイレンも鳴らしていないし、開いているドアからひつぎが見えるから、すぐわかるわけです。それを見るのが怖くてトイレに行くのを我慢した記憶があります。自分は生かされたけれども、こんなにもたくさん亡くなった方がいるんだと、つらい現実を目の当たりにしました」
「原発の状況も日に日に悪化していき、より遠くへ再避難する人が多かった。朝起きると、近くにいたはずの人がいない。それが恐怖でしかなく……。当時は放射線のことがよくわからず不安ばかりで、一刻も早く離れたいと思っていました。だからなかなか避難先を決められない両親にいらだったりもしました」
――その後も都内の親戚宅や福島県中通りにある西郷(にしごう)村など、転々とされて、多感な時期にはつらかったと思います。何か支えはありましたか。
「中1のときの担任で、恩師である清信元江先生から西郷村の避難所に電話がかかってきたんです。『またみんなで集まろうね。今大変だけど、いつか必ずみんなで会えるから』と言ってくださって。とてもうれしかったですし、その言葉を支えに避難生活を送っていました」
――価値観や生き方は変わりましたか。
「だいぶ変わったと思います。当たり前の日常がどんなに幸せなことなのかと。地元に戻ってきてからの学校生活も、失ったことが多かった分、楽しもうという気持ちで過ごしていました」
――救護団体である日本赤十字社に就職されたということは、震災は進路の考え方にも影響したのでしょうか。
「震災後しばらくたってから知ったのですが、第1原発から近い双葉郡の病院で避難行動が混乱し、搬送中や搬送先の施設で入院患者ら多数の方が亡くなりました。救えたはずの多くの尊い命が失われたこの事件は強く印象に残っており、災害時に役に立てる人になりたいと思うようになりました。大学は災害・復興政策を学びたいと思い政治学科を選びました」
――中島さんの身近でも、そういう経験があったのでしょうか。
「母方の祖父は小高区にあった家に帰還できないまま亡くなりました。元気と健康が取り柄のような祖父でしたが、震災後にがんが見つかり13年6月に亡くなりました。近所に住んでいた祖父と同世代の人たちも、帰還できないまま避難先などで亡くなった方が多かったです」
「特に、子供や高齢者、障がいのある弱い立場の方々は、災害など有事の際に社会から取り残されがちです。震災を経験した自分だからこそ、災害で苦しんでいる人々の立場に立って支援できることがあると思い、今の道(日本赤十字社)を選びました」
たくさんの人が集う明るい故郷を、いつか
――大学進学で上京されました。東京から地元はどのように見えましたか。
「上京して、いろんな意味でショックを受けました。地元では復興しようと頑張っている最中なのに、東京はきらびやかなネオンが輝いていて……。離れて見た故郷は、やはりどこか取り残されてしまっているような感覚が、私の中にずっとありました」
――震災から10年、故郷の見方に変化はありましたか。
「最近思うのは、光と影に分かれているなと。避難指示が解除されて少しずつ人々のなりわいが戻ってきている地域がある一方、(福島第1原発が立地する)大熊町や双葉町などはほとんどが帰還困難区域になっていて、大きな隔たりがあるなと感じます。人が戻らない地域は、やはり見ていてさびしいですよね」
「(祖父母の家があった)小高区の居住人口は震災前の3割程度で、そのほとんどが65歳以上。超がつくほどの限界集落です。若い人たちの多くは避難先に定住していきました。20~30年先をしっかり見据えた政策をうっていかないと、将来の地図から南相馬が消えてしまう、そんな危機感を持っています」

――南相馬市出身の20代として、どう生きたいですか。
「これまでたくさんの方々にお世話になったので、恩返しをしたい。特に今は日本赤十字社にいるので、災害で苦しむ人を何かしらの形で救いたい。まだ現場に行ったことはないですが、20年の7月豪雨では義援金の立ち上げに携わることができました。被災地と、被災地を助けたいと願う人たちをつなぐパイプ役になれたらという思いで仕事をしました」
「いずれは福島の復興に携わりたいなと考えています。私は、復興は30年、40年でも終わらない、次の世代にも関わってくることだと思っています。ここまで復興したんだぞって言えるぐらい明るい故郷を同世代の仲間ともう一回つくって、次の世代にバトンを渡したいですね」
(聞き手は安田亜紀代)
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。