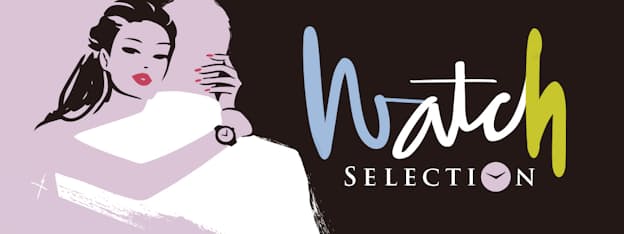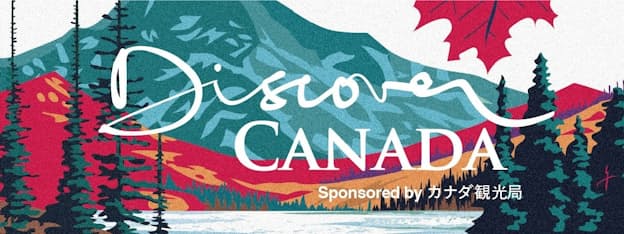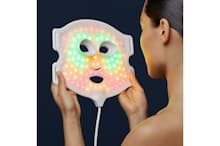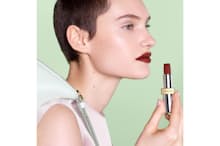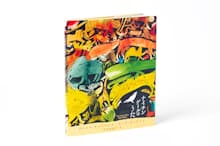先日、前東京五輪・パラリンピック組織委員会会長の森喜朗氏の失言が炎上して、その失言をカバーしたかった会見での振る舞いで、さらに傷口を広げてしまい、結果的に役職の辞任に追い込まれた、という騒動がありました。「あれはないだろう」と誰もが思うような出来事でしたが、それを他人事と思っているだけではいけません。自分のミスや部下のミスはいつ起こるかわからず、謝罪をする事態はある日突然やってきます。そのときの基本を「わきまえて」いますか。会社としての対応をプロの危機管理会社が指導しても、個人の態度や話し方に問題があれば事態が暗転することも珍しくありません。2回目となる今回は「謝罪で気をつけるべきこと」を考えていきたいと思います。(この記事の〈上〉は「『伝わらない』首相は反面教師 新常態プレゼンのコツ」)
「謝罪」では何にいちばん気を付けるべきなのか
謝罪が必要なのはどういう場合でしょうか。「間違ったことをして誰かに迷惑をかけた場合」です。例えば誰かの権利や尊厳を侵したり、損害を被らせてしまった、感情を著しく傷つけたなどの場合ですよね。その場合、物質的な弁済や保証、深刻になると公的な処罰が求められることもありますが、その前に自然発生的に道義的な反応、相手の感情への対応がまず求められます。この時必要となるのが謝罪です。
ですから、謝罪は「間違ったことをしたと認める」「人として取るべき道を取る姿勢を示す」「怒らせたり悲しませたりしてしまった、その気持ちを鎮める」ということが大きな目的です。
こう考えると、絶対やってはいけないことがわかりますね。「間違ったことをしたと認めない」「示すべき姿勢をちゃんと示さない」「相手の気持ちを鎮めることを忘れる」ということです。だいたい、この3つのいずれかをやってしまうと、謝罪は失敗します。危機管理の会社が喜んで失敗の教材にするような謝罪会見は、この3つ全部がそろっています。
こう言うと「自分のパートナーとケンカしたときに悪いと謝ったけど、なかなか怒りが解けなかった」と思い出す方がいらっしゃるかもしれません。そうだとしたら「何が悪かったのか」をあまり考えずに、ただその場を収めようと謝っただけなのではありませんか?
でも相手が収まらないので、逆ギレしたり、不機嫌になったりしませんでしたか?
「相手が怒っている理由をあまり深く考えずに、とりあえず謝っておく」。こういう謝罪の仕方で、さらに相手を怒らせることは少なくありません。怒ったときに、多くの人は「理解や共感」を求めるからです。怒りの感情と共に生まれるのは、自分の被害の大きさや深さをわからせたい、という思いです。ですから、怒っている側の人間がどんな被害をもたらされたか、それをどのように深刻に受け止めているかをまず理解し、共感する姿勢を示せないと、謝罪にはなりません。それを安易にスルーして、「謝ればいいはず」などと思っていると、自分が逆ギレしてしまったりすることになるのです。