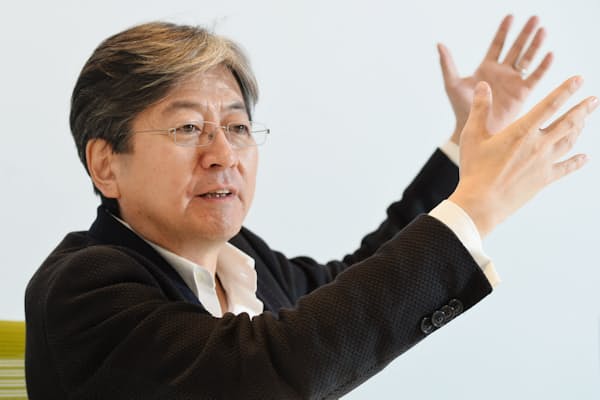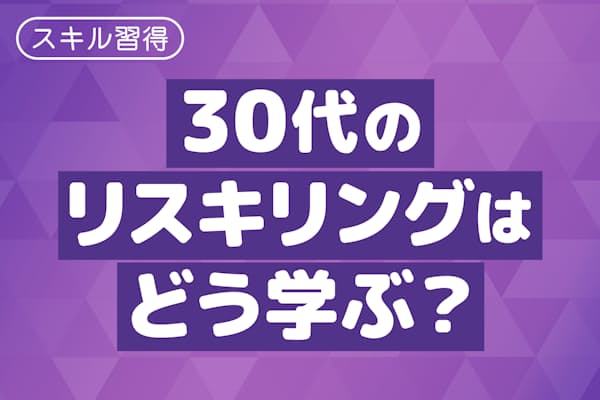Z会秘伝の「朱筆」指導術 添削者にも添削で質保つ
増進会ホールディングス社長 藤井孝昭氏(下)

Z会の教材はしっかり文章を書かせる設問が多い
通信添削で学びをサポートする「Z会」は難関大学を目指す高校生からの支持に強みを持つ。学力を伸ばす秘密は、答案に赤字のペンで「朱筆」を入れる添削者の厚みにある。事業会社のZ会をグループに持つ増進会ホールディングス(HD、静岡県三島市)の藤井孝昭社長は「単に赤ペンで正誤をチェックしているのではない。朱筆はロボットに置き換えようのない、ヒューマンな指導だ」と語る。
<<(上)東大生の4割学ぶ「Z会」 難問生み出す指導部155人
実際の添削例がサンプルとしてZ会のホームページ内で名前を伏せて公開されている。たとえば、古文の例では京都大学の総合人間学部に現役合格したという元会員の答案がみえる。出題文は一休和尚にまつわる逸話で、設問は「傍線部分を、何がどのように違うのかがわかるように、わかりやすく口語訳せよ」だ。当たり前のように読めるこの短い設問文に、「考えるヒント」が隠れている。
元会員の回答はシンプルに現代語訳していて、中身にはそつがない。しかし、採点結果は6点中の3点どまり。主な理由は設問の求めに必ずしもしっかり答えていないから。設問にある「わかりやすく口語訳せよ」とは、「本文では省略されている登場人物の相関関係を補いつつ、発言の意味を読み解きなさい」という意味だ。しかし、元会員は字面を訳しただけ。問いの含意を読み切れていなかった。
「添削にあたっては、解いた本人が気づいていない『どこを見落としたか』『作問者の意図を、どこで取り違えたか』に気づかせてあげることを重視している」と、藤井氏は添削のポイントを明かす。正解を教えるのではなく、思考の道筋を逆にたどって、間違えの原因を正すわけだ。例問の場合、「古文では人物名の省略が珍しくない」という予備知識があれば、問いの意図を見抜きやすくなる。元会員は設問で何が問われているのかに、うまく気づけなかった。
添削者は約180字を費やして、半分しか得点が認められなかった理由を丁寧に指摘。マイナス3点のうち、1点減点部分と2点減点部分の理由をそれぞれに明示している。傍線や矢印を使って、答案の欠陥を具体的に示せるのは、朱筆ならではの視覚的なわかりやすさだ。同時に、隠れている登場人物を、どのように答案に盛り込めば、高い得点につながったのかを補足している。
大学入試ではあらかじめ採点項目が示されていて、すべての要素を満たせば満点が与えられ、答えに過不足があれば減点対象になる。「出題の意図を正しく読み取ることは、正解を導く第一歩。『間違えた理由がわからない』という人に、添削は『なぜ間違ったか』を教え、問いとの適切な向き合い方へ導く」(藤井氏)
間違えた本人すら気づいていない「間違った理由」を見抜くには、その分野の学識だけではなく、問いと答えを巡る経験知が欠かせない。Z会の添削者は「東京大学、京都大学などの難関大学で学んだ人や、教壇での指導経験が豊富な人が多い。名簿に載っている人数は1万人を超える」という。
しかし、難関大学出身や教員経験者だからといって、誰でもすぐに添削の仕事に就けるわけではない。実は添削者も添削を受ける。「適性を確認したうえで、採用を決めてから、添削のトレーニングを積んでもらう。朱筆のベテランを先生役にした研修を受けて、実力を高めたうえでないと、実際に朱筆を握ることはできない。添削者のレベルを高く保つうえで、妥協はない」と、藤井氏は添削者の養成に余念がない。