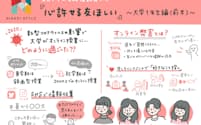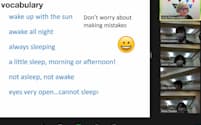コロナ下の留学体験 午前3時のネット授業で得たもの
コロナ下の留学(1)

新型コロナウイルスの感染拡大が始まって約1年。様変わりした大学生活の中でも、とりわけ大きな影響を受けたのが留学だ。昨春時点で海外で学んでいた学生の多くは突然の帰国を余儀なくされ、渡航を予定していた学生も足止めされた。感染の収束が見えない中、留学を希望する学生はいまも中ぶらりんな状況に置かれている。コロナ禍に翻弄された留学経験者たちはその後どう過ごし、いま何を思うのか。胸の内と後輩たちへのアドバイスを聞いた。
「会話弾むようになった矢先、悔しい」
「状況が一変したのは20年3月半ば。急きょアパートを引き払い、25日発の飛行機のチケットを取りました」
タイのタマサート大学に留学していた明治大学3年の碓井杏菜さんは、コロナ禍での慌ただしい帰国を振り返る。中国・武漢での都市封鎖が始まったのが1月末。2月にはタイ国内でも感染者が増え始め、3月に入ると欧米からの留学生が一斉に帰国した。中旬には大学の授業も全面オンラインに移行。キャンパスに通えず、友だちにも会えない。アパートでパソコンに向かうだけなら現地にとどまる意味はないと考え、帰国便が取れなくなる前に慌ててチケットを手配した。

留学は2019年8月から10カ月間、同大の政治学科で学ぶ計画だった。海外で学ぶのは明治大の付属高校3年のときからの夢。当初は欧米の大学を考えていたが、大学1年時にタイに短期留学し、人々の温かさと暮らしやすさにひかれて、長期留学を決意した。1学期目は授業についていくだけで精いっぱいで、一日中、図書館やカフェで勉強した。帰国することになったのは、授業を楽しむ余裕が生まれ、学食でのクラスメートとの会話も弾むようになった矢先。悔しかったが、日本でオンラインの授業を受け続けることにした。
欧米からの留学生の多くは、時差の大きさに耐えきれず脱落していった。しかし日本とタイの時差は2時間。生活は乱されずに済んだ。授業のオンライン化で案外良かったのは、発言しやすくなったことだと碓井さんは言う。
「対面だと英語が流ちょうな学生の勢いに負けて発言の機会を逸してしまうこともあったのですが、Zoomだとチャット欄に書き込みをしたり、挙手ボタンを押したりできるので、タイミング良く発言できるようになりました。半面、オンラインだと先生が『画面共有』して話が一通り終わったら質問、という風に予定調和の流れになりがち。誰かの何気ない一言から議論が展開していくという、生の面白さはなくなってしまいました」
午前3時からオンライン授業 「対面の倍以上大変」
留学先の米国から帰国。オンライン授業の時差に苦しんだのは、明治大からテンプル大学大学院に留学していた高野瑠音(りゅうと)さんだ。テンプル大がある東海岸と日本の時差は13時間(サマータイム時)。日本時間の午前3時から授業を受ける羽目になった。
特に大変だったのはチームプロジェクトだ。米国企業を一社選び、事業展開について分析した上で、弱点を克服するためのマーケティング施策を考えるという課題に5人で取り組んだが、時差があるのは高野さん一人だけ。授業前のチームの打ち合わせにも支障をきたし、歯がゆい思いをした。

オンラインならではのコミュニケーションの壁も痛感した。米国人の学生が早口で話し始め、複数の会話がかぶると途端に聞き取りづらくなる。ましてやその会話に自分も入っていくのは至難の業。「対面授業の2~3倍は大変だった」と苦笑する。一方で、場の空気を共有できない分、自分の考えを即座に言葉にせざるを得なくなり、言語化能力が向上。「学びが濃くなった」実感があるという。
「対面だと、"You know"の一言で、なんとなく理解してもらえたことも、オンラインでは通用しない。しかも話すだけでなく、自分の考えをディスカッションボードに文章で書き込まないと評価してもらえないので、ごまかしが効かなくなるんです。そういう意味では鍛えられました」
高野さんの場合、秋以降は、夜中から朝までオンラインで授業を受けた後、日中は就活というハードスケジュールになった。留学生を対象にした就活イベント「ボストン・キャリアフォーラム」にオンラインで参加。個別企業との面接などもオンラインだったため、睡眠と食事以外はずっとパソコンにかじりついてる状態で、洗濯など身の回りのほとんどを、親に頼ることになった。「実家に帰っていたからこそ、それが可能だった。米国で一人暮らしのままだったら、まず無理だった」と振り返る。
「就活に影響しかない」
留学を切り上げ、日本の大学に復学した人もいる。都内の有名私立大商学部の4年生で、19年9月から8カ月の予定で中国の大学に留学していたAさんは、同国での感染拡大を受け昨年1月に帰国した。オンラインで留学を継続する選択肢はあったが、対面と同じだけの効果を得られるとは思えず、4月から日本の大学に戻ることに決めた。ところが蓋を開けてみると、復学した大学でも春学期はすべてオンライン授業に。「対面じゃないなら、中国の大学のオンライン授業で良かったのかも……」と複雑な表情だ。
「留学の中断で、思い描いていたものの半分くらいしか達成できなかった。それは本当に悔しい。授業はもちろん、卓球の部活で一軍メンバーに選ばれ、大会に向けて張り切っていたのに、それもなくなってしまった。就活への影響?いや、影響しかないです。留学経験者は有利だと聞いていたけど、深みを持つエピソードが語れない」
取材中も、留学が突如終わってしまった悔しさをにじませたAさんだが、いまは意識してプラスの面に目を向けるようにしているという。
「留学中にできなかったことを、できたかように『盛る』のではなく、期間は短いなりに頑張ったことに焦点を当てようと。難しい会計学の授業にも教授に食らいついて頑張ったし、友人もできた。今も語学力をアップするための努力を続けている。就活ではそういう点をアピールしていきたいです」
それでも得られたものは大きかった
「プラス面に目を向ける」というのは、コロナ禍に翻弄された留学経験者が共通して語った言葉だ。高野さんは、オンライン授業で自分の存在が埋もれないように、ここぞという時にはキーワードを書いたホワイトボードをウェブカメラの前にかざしたり、ズームのリアクションボタンを多用するなどの工夫した。そのことを就活で強調し、第1志望である米国大手IT企業の日本法人から内定を得た。
「コロナ禍の留学でどんな課題に直面し、どう解決しようとしたのかを具体的に話しました。これから仕事をする上でも常に正解のない問題にぶつかるでしょう。その点では、どんな状況でも諦めずに努力する姿勢をアピールできたと思います」
碓井さんも帰国当初は混乱し、悔しい気持ちが強かったが、家族や友人と話す中で、留学で得たものの大きさに気付いた。英語のプレゼン能力が向上したのはもちろん、タイ人学生と語り合う中で、彼らが日本と違って政治について日常的に話し、自分たちが国を変えるのだという気概を持っていることに刺激を受けた。さらに、コロナ禍を海外で経験したことで、進路についての考え方にも変化が生まれた。
「コロナが流行し始めたとき、タイ語のテレビを見ていても状況が理解できず、情報が少ないとどれだけ不安になるかを体験しました。ネットやSNSにあふれる情報の中から信頼できる情報を必死に探す中で、正確な情報を素早く伝えるメディアの役割に目が向き、タイと日本の政府の対応の違いの背景などにも関心が広がった。もともとは航空業界志望でしたが、今はメディア業界に魅力を感じています」
これから留学したいと思っている学生に対するメッセージも聞いた。3人が強調したのは今できることをやる大切さだ。
「留学にいざ行けるとなったときにすぐ行けるように、いまから準備を頑張って」と碓井さん。Aさんは「自分は選ばなかったけど、今だったら、オンラインでの留学が無駄だとは思わない」と言う。言葉が通じず、周囲に圧倒されるもどかしさや悔しさを感じるのはオンラインでも同じ。それが成長のバネになると思うからだ。高野さんもこうエールを送る。「コロナのせいで計画が狂ったと後ろ向きになるのではなく、オンライン化が進んで世界の距離が縮まったというプラス面に目を向けて。準備をしていれば、きっとチャンスはつかめます」
(ライター 石臥薫子)
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。