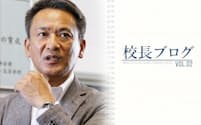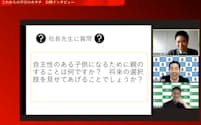学校経営は生徒の手で 修学旅行も制服も自分で決める
横浜創英中学・高校の工藤勇一校長(3)
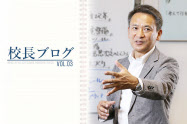
新型コロナウイルスの影響で、横浜創英中学・高校の海外への修学旅行が中止になりました。「生徒がかわいそうだ」と教師陣が代替の国内旅行プランを自分たちで考えると言い出したのですが、私は一言、「代替プランは生徒たちに考えさせたら」と助言しました。教師たちの呼びかけに高2の500人あまりの生徒のうち40人近くが自ら手を挙げ、企画を考えて旅行会社側と折衝を始めたところです。
この件で生徒たちが私のところに相談に来ます。もちろん余計な口は挟みません。ただ、生徒1人1人が当事者意識を持って考え、新型コロナによるリスクなども考慮し、みんながOKのプランになったらいいねと、基本的にはそれだけです。
これまで私は生徒を自律した大人に育てることを教育者としての最上位目標に掲げ、教育に携わってきました。コロナ禍で修学旅行が中止になったのは非常に残念ですが、横浜創英の生徒にとっては、ある意味で価値ある学びの機会にできると思っています。
高校生活を通して自律した大人として成長するには、自らが学校経営に参画し、学校を変えていく当事者となることがどんな行事を行うことよりも効果があります。(2020年3月まで校長を務めた)区立麹町中学(東京・千代田)の事例ですが、中2の1人の男子生徒の提案から生徒会の会則が大きく改訂されたことがあります。生徒会の組織に給食委員会や図書委員会などの各種委員会があります。
給食委員会の場合、各クラスから男女各1人の委員が選ばれ、全校の給食が円滑に行われるよう、当番活動のルールを定めるなど、さまざまな支援活動を行っています。通常、各クラスの給食当番はクラス全員が順番に回るように日程を組んでいるのですが、やる気のない当番に当たると、給食の準備が遅れ、結果的に昼休みが短くなる。それはクラス全員にとって不幸です。それなら希望者のみで給食当番をやったらどうかと給食委員会に彼は提案したのです。

そんなの不公平じゃないかとの指摘もあると思いますが、中2の学年で生徒たちが実験的に希望者を募ったのです。給食当番は各クラスに6人は必要ですが、1クラスを除いた3クラスで条件を満たしました。3人しか希望者のいないクラスには、9人の希望者がでたクラスから3人を借りて給食当番をすることにしたのです。実証実験としての2週間のこの「ボランティア給食当番」は大成功でした。
給食の準備・配膳活動はスムーズに実施され、その学年の全生徒が昼休みを有効に過ごすことができるようになりました。給食当番なんて小さな話だと思うかもしれませんが、この話には続きがあります。この学年は2年後期に生徒会の中心メンバーとなりましたが、全ての各種委員会も男女各1人と無理やりに決めて選ぶやり方ではなく、希望者を募って回すボランティア制にしようとなったのです。
これを生徒総会に諮り、全校生徒で合意されました。もちろんこのプロセスには教師は介入していません。現在、すべての委員会はこの制度下で運営されていますが、委員の意識は「何をやればいいの?」から「何ができるか?」に確実に変化し、新たなアイデアが次々と生み出されるようになったと聞いています。
麹町中学では生徒が主体になって学校運営を担うというスタイルが根付き始めています。昨年も2つのアイデアが実現しました。学校では通常毎月1回、避難訓練を実施しているのですが、以前はすべて先生側がプランを決め、指示して行ってきました。このことに問題意識を持った生徒たちの提案は、実際の災害に本当に対応できるよう、生徒が主体となって実施すべきだいうものでした。
やらされ感の中では当事者意識をもてないというわけです。この生徒たちの提案が基になり、今年度からは予告をせずに避難訓練を実施したり、生徒自らが指示をして避難するスタイルを取り入れています。
この4月から新しい制服に変わりましたが、この件も校則の基本的なルールの権限を生徒と保護者に委譲したことにより実現したことです。まずはPTAの組織に制服等検討委員会が設置され、続いて生徒会の中にも同様の委員会が立ち上がりました。その後、制服業者対象にコンペを開催し、デザインを決めるまでには、およそ2年もの長い時間がかかりましたが、この間、この2つの委員会は誰一人置き去りにすることのない制服のあるべき姿を追求し続けました。

その際、最上位の目標に据えたのは機能性と経済性です。彼らはそもそも制服が必要なのかという実験を夏と冬の季節に分けて行いました。結果として夏の私服はTシャツや短パンなどで過ごせることから、非常に評判がよかったのですが、冬については重ね着も必要となるため、毎日着替えるとなると、私服は意外に経済的ではなく、評判も芳しくなかったのです。
この実験結果を受けて、すべての生徒たちにとって機能的で経済的であることを実現するためには、生徒それぞれが私服と制服を選べるようにすることを基本に据えた方がよいという結論を得たようです。この後、ようやく制服のデザインや素材への議論に移っていったわけですが、当然、デザインにこだわる人は少なくありません。
そこでデザイン決定の説明責任として重視したのが誰にも優しい機能性です。アレルギーのある生徒にも優しく、窮屈にならないようにツメ入りをやめようなどと誰にでもハッピーな機能性に関する意見を持ち寄り、現在の制服が決定されたのです。この4月からの新入生の入学にあたり、入学式さえ制服を着るのか、私服なのかは各生徒の意思に任されました。
生徒会組織の改正も制服のリニューアルも、生徒1人1人が当事者意識を持ち、みんなで議論し、実験したりして模索しました。そして全員がOKの形を探し、1つの結論に達したのです。特に制服リニューアルについては、誰もが自分たちが卒業後に実現することであることをわかった上で、今後入学してくる新たな後輩たちのために活動したことですから、本当に尊敬に値する素晴らしい取り組みだったと感じています。
麹町中学の生徒に関する興味深いデータをご紹介しましょう。日本財団が2019年にまとめた高校3年生を対象とした「18歳意識調査」では、「自分を大人だと思う」と答えた生徒はわずか29.1%、「自分が国や社会を変えられると思う」は18.3%にとどまりました。しかし、同じ調査を3年も若い麹町中学の3年生にしたところ、それぞれ30.2%、50.5%になりました。実際、彼らは学校というもっとも身近な社会のルールや仕組みを変えたわけです。今後、横浜創英の生徒たちもどのように学校を変えていくのか、その変化と成長を楽しみにしています。
1960年、山形県生まれ。東京理科大学理学部卒。1984年から山形県の公立中学校で教えた後、1989年から東京都の公立中学校で教鞭をとる。東京都教育委員会などを経て、2014年から千代田区立麹町中学校の校長に就任。宿題や定期テスト、学級担任制などを次々廃止するなど独自の改革を推進。2020年4月から現職。
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。
関連企業・業界