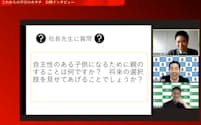分かりやすい先生は逆効果? AI授業で見えたこと
横浜創英中学・高校の工藤勇一校長(2)

10月にSPACE(スペース)というベンチャー企業のアドバイザーに就任しました。代表取締役の福本理恵さんは、東京大学の先端科学技術研究センターで「異才発掘プロジェクトROCKET」のプロジェクトリーダーをやっていた方です。福本さんはこの事業の次のステップとして、子供たちの個別最適な学びを支援するため、ICT(情報通信技術)などを使って様々なツールを開発するスペースを8月に設立。福本さんとは10年近いお付き合いがあり、実は私が3月まで校長を務めた東京の千代田区立麹町中学でも色々お手伝いをしてもらっていました。
日本の学校の基本的な教育スタイルは、明治時代からほとんど変わっていません。「一斉授業」といって1人の教師が多くの生徒に一方的に知識を提供するやり方です。しかし、この方式だと、すでにその学習内容を理解している生徒には余計な授業になる。一方でその授業の前提となる知識を取得できていない生徒はどんどん理解できなくなるばかりです。基本は受け身の学習ですから、自分から自律的に学ぶ生徒は育ちづらいのです。
そこで麹町中では、ICTなども活用し、どうしたら生徒が自律的に学ぶようになるか、様々な試みをやってきました。
麹町中学時代に経済産業省の協力も得て、2018年から「個別最適化学習」の実証実験を行いました。大きな教室に生徒たちを集めて数学の学習をしたのですが、この時間、自分がどこを学ぶのか、そしてどのような方法で学ぶのかを自分で選べるようにしました。生徒たちはそれぞれがICTを使ったり、好きな問題集を使ったりしながら、一人で学んだり、生徒同士で教え合ったり、個別に先生に聞いたりとそれぞれ自分が一番いいと思ったスタイルで勉強するのです。
新しいのは「Qubena(キュビナ)」というAI教材を活用したことです。AIが生徒1人1人の学習進度や習熟度に合わせてコンテンツを提供するというやり方です。タブレットの画面にその生徒に対応した「解くべき問題」が自動的に出題されます。間違った場合はAIが分析して、過去の単元で本人がつまずいているポイントを探し出し、その原因を解決するためにその生徒が解くべき問題を出してくれるという仕組みです。そのデータはリアルタイムで分析されるので、教師側も誰がどれだけ理解しているのかが分かり、生徒をサポートしやすくなるのです。

この個別最適化学習のスタイルだと、教室内のそこかしこから声が聞こえてきて「カオス」のような状況になります。
ただ効果はてきめんでした。中学1年間の数学の授業時間は計140時間あるのですが、数学が比較的苦手だという生徒でも約70時間で1年の授業範囲を終了。成績上位の生徒は5分の1程度の時間で終わり、なかには中1で中3や高1の単元まで進んだ生徒も出ました。その効率性には驚きましたが、何よりこのスタイルの学びの良いところは、生徒の「学ぶ意欲」「学び方」が養われていくからです。
従来の一斉授業型の学びとあえて比較した言い方をすれば、教育でもっとも大切である「主体性」「自律性」が失われないのです。
日本の教育関係者は、分かる授業をすべて子供たちに提供したいと必死でがんばってきました。生徒も保護者も教え方の上手な先生を支持してきたからです。結果、授業のうまい先生がスターのように扱われ、他の先生たちはその先生に見習おうと努力してきたのです。しかし、それをがんばれば、がんばるだけ、教育界は負のスパイラルに入っていくと思います。
ベテラン先生やカリスマ講師のもとで学ばせたいと考える親が多いようですが、そういった方々にお伝えしたいのは、子供たちはもっと教え方のうまい先生を求めるようになるだけで、主体的に自分で考えて行動しようとは思わなくなっていくということです。「あの先生の教え方が下手だったから、自分は成績が下がり、志望する学校に落ちた」とか、人のせいにばかりする人間になってしまいます。これでは「自律した大人」には育ちません。
4月から校長を務めている横浜市の中高一貫の私立校、横浜創英中学・高校では、まだまだ基本的な教育スタイルは一斉授業型ですが、今後は生徒や先生方と一緒になって、どんな学習法がそれぞれの生徒にとっていい方法なのかを考えていきたいと思います。教育は教員だけでやる時代でもありません。福本さん率いるスペースをはじめ、多くの民間企業の知恵や協力も借りて今後のあるべき教育の姿を追求していくつもりです。
1960年、山形県生まれ。東京理科大学理学部卒。1984年から山形県の公立中学校で教えた後、1989年から東京都の公立中学校で教鞭をとる。東京都教育委員会などを経て、2014年から千代田区立麹町中学校の校長に就任。宿題や定期テスト、学級担任制などを次々廃止するなど独自の改革を推進。2020年4月から現職。
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。