自然の世界に境界も分断もない デジタルアートで体感
チームラボ代表 猪子寿之さん

デジタル技術を駆使した創作や独創的なミュージアムの設計で知られるアート集団、チームラボ(東京・千代田)。同社の代表で東京大学工学部出身の猪子寿之(いのこ・としゆき)さんは、科学の学びで身につけた「ボーダーレス」な発想を作品に生かしている。サイエンスとアートとの結びつきや、それが生み出す可能性について聞いた。
――コロナ禍がきっかけの新作があります。どのような思いを込めたのですか。
「紙に描いた花をスマホ撮影してアップロードすると、それが(動画投稿サイトの)ユーチューブ上の花束にリアルタイムで追加される作品『フラワーズ ボミング ホーム』を8月に発表しました。みんなで花束を作ることができ、どこで描いた花でも世界中で見ることができる。テレビに映せば、家のテレビが世界とつながる。家に閉じこもらなければならないときでも、自分の存在と世界がつながっていることを実感できればいい、つながりが祝福されるような感覚を広められればいいと思いました」
言語化したら本来の世界から遠ざかる
――科学との出合いは。
「子供の頃は近くの土手で昆虫やバッタを捕まえ、家に帰って図鑑で確認するような遊びをしていて、それがサイエンスに興味を持つきっかけになったと思います。思春期のころには、科学は世界の真理を認識する方法ではないかと、なんとなく感じるようになりました」
「人は言語で物事を認識している。でも、言語化したらかえって世界から遠ざかると思います。例えば地球と宇宙は、本来は連続的で論理的には境界がない。それが『地球』と言ったら境界ができて、本来の世界のありようから遠ざかる。科学的な認識というのは、世界のごく一部かもしれないが世界そのもの、真理を捉えようとしている。だから信用できると感じられたのです」

――大学で統計を学んだのはなぜですか。
「大学では応用物理・計数工学科に進みました。科学的なアプローチや、統計的なアプローチを世界を認識する方法として身につけたいと思って選択しました」
「例えばニュースで新しい病気で人が亡くなっていると報じられたとします。でも統計的にみると死者数全体は減っているかもしれないし、新しい病気がなかった場合と同じかもしれない。統計的にみたら、社会を破壊するのは新しい病気ではなく、『新しい病気』という言語での認識、つまり誤った認識が広がること自体かもしれない。最近の状況をみながら、こんなことを考えることもあるのですが、こうしたことは、統計や確率について学ばなければ、わからないことです」
――アートの分野に進んだ理由は。
「高校生ぐらいから、授業で出てくる話があまりにも自分の身体の感覚から遠く離れていることだと感じるようにもなっていました。物理でリンゴが落ちるという物理法則について学ぶあたりはまだ身の回りのこととして感じられましたが、原子よりも小さい世界の話になると、見たことがない領域になる。こうした話はもっと頭のいい人に任せようと思いました」
人類にとっての「美」を広げたい
「アートは、世界の見え方、認識の仕方を変えるものです。特に『美』(という価値観)は、人間の生存に直接関係する領域の外に広く及んでおり、美によって人間は行動を決定しているところがある。合理的ではなく、例えばある職業をかっこいいと感じたから選んだり、その日に着る洋服を選んだりしている。無意識の中で美が作用しています」
「その一方で、この大事な美が一体何なのかはよくわからない。アートの歴史をみると、美を拡張していくことの連続のように感じられます。今は美に含まれないもの、美ではないものを作って、美にしていく。美が拡張されることで、ヒトの行動がどう変わるのか、知りたいと思いました。何を美しいと感じるのか、それによって世界との関係が決まってきます。自分たちも生涯をかけて活動を続け、人類にとっての美の基準が拡張されていったらいいなと思っています」

――美の拡張ができている実感はありますか。
「チームラボは2001年から活動していますが、その当時は今よりも、物質として所有できるものの方に価値があるとされていたように思います。物質ではなく所有もできない作品、体験することしかできない作品、それに価値があって多くの人が見たがるとは考えられていませんでした」
「お台場にあるミュージアム『チームラボボーダレス』は18年6月からの開館1年で約230万人が来館し、豊洲の『チームラボプラネッツ』は18年7月からの開館1年で約125万人が鑑賞しました。スペインのバルセロナのピカソ美術館は18年の来館者数が約94万人、オランダのアムステルダムのゴッホ美術館が約216万人です。われわれのミュージアムに世界中の人がこれほど来るとは思っていませんでした。もしここでアートを体験した人が美しいと思ってくれたなら、美の領域を拡張できたと言えるのではないでしょうか」
――科学はどう作品に反映されていますか。
「20年7月にオープンした『チームラボフォレスト』(福岡市)に設けた『捕まえて集める森』は、その根幹に小さい頃の体験があります。周りにいる動物の画像をスマホ画面上の『観察の矢』で射ると、その動物(の情報)がスマホに取り込まれ、見終わったら好きな場所に放すことができる。こんなふうに実空間とスマホを行き来できるミュージアムは世界で初めてではないかと思っています」
「自分で興味あるものを見つけて知る、それも自分の身体を使って探し回るというのは、世界そのものを知っていくことだと思う。知識をただ詰め込むだけでは、世界を知ることを嫌いになってしまう。ミュージアムでの体験が世界を好きになるきっかけになってくれたらと思います」
――「ボーダレス」「プラネッツ」などチームラボのミュージアムが今だからこそ持ちうる意味は。
「『ボーダレス』では、50の作品全てが関係しあって、連続的な空間になっています。境界のない認識に興味があり、連続的現象こそが美しいと考えたものです。『プラネッツ』は、世界と自分が連続的につながれたらと考えて作りました。どちらも世界の本来のありようなのに、放っておくと境界が増えてしまう。世界の分断が大きくなっている中、境界のない世界や世界と連続していることを体験することは今まで以上に重要性が出てくると考えています」
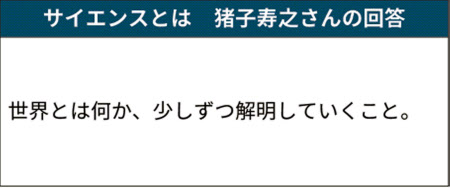
(聞き手はライター 鴻知佳子、撮影 石井明和)
1977年、徳島市生まれ。2001年の東京大学工学部計数工学科卒業と同時にチームラボ創業。大学では確率・統計モデルを、東大大学院(04年中退)では自然言語処理とアートを研究した。チームラボにはアーティスト、プログラマー、エンジニア、CGアニメーター、数学者、建築家など様々な分野のスペシャリストが国内外から参加。アート、サイエンス、テクノロジー、自然界の交差点となって芸術作品を生み出している。
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。
















