大学生、キャリアをどう描く? ジョブ型雇用の時代に

新型コロナウイルスによって、働く環境は大きく変わった。この時代を生きる大学生は、どう心構えをしたらいいか、キャリアの築き方はどうなるのか――。ビジネスSNS(交流サイト)を展開するリンクトイン・ジャパン(東京・千代田)は7月末、学生向けにこれからのキャリアを考えるオンラインイベント「コロナ時代のキャリア作り」を開催。今大学生が知っておくべき働き方の変化や求められるスキルについて、同社の村上臣代表に聞いた。(聞き手はU22の桜井陽)
イベントはビデオ会議システムのZoomで実施し、海外に留学する学生も含め、約50人の学生が参加した。雇用やキャリアについて注目の記事を引用しながらトークを展開した。
ジョブ型雇用とは?
コロナ下の働き方の大きな変化として、職務内容を定めて成果で評価する「ジョブ型雇用」について、最近の導入事例などを紹介しながら解説した。日本の大企業で導入する動きが一気に進んだの背景について、リンクトインの村上さんは「コロナで広がった在宅勤務ですよね。特に大企業で、今までの顔が見えているマネジメントが通用しなくなり、ジョブ型が急に注目され始めたように思います」と話す。
ジョブ型雇用では、あらかじめ仕事の内容や必要なスキルを「職務定義書」(ジョブディスクリプション)で明確にして、その達成度合いで評価や報酬が決まる。ただ、日本企業では、在宅勤務でログイン時間をチェックするなど、サボっていないか監視する方向へいくケースも多い。これについて村上さんは「日本企業は勤務時間で社員のパフォーマンスを測ってきた。こうした日本型の慣習とリモートワークとの相性が悪さが、表面化してきている」と言及した。
日本の採用システムについても、「日本は新卒採用にチャンスが偏っているので、採用のときには、地頭がいい人がほしい、という話になりがち。中途採用は半分ジョブ型ですが、残り半分は新卒採用のやり方を踏襲している気がします。これらが混在していて、議論が複雑になっています」と指摘した。
キャリアとジョブの違い
雇用環境が変わりつつあるなか、キャリアをどう考えるべきか。村上さんが投稿したCOMEMO(日経が運営する投稿プラットフォーム)の記事「今後に備えるためにも意識したい、キャリアとジョブの違い」を引用しながら、キーワードを整理した。
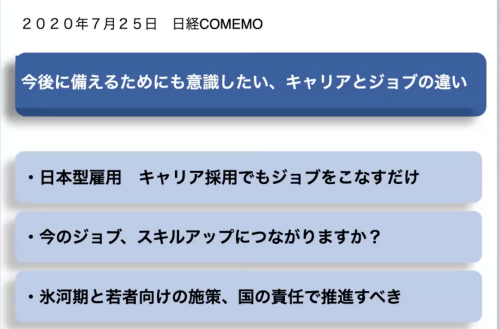
英語で「キャリア」と「ジョブ」、「タスク」という言葉がある。日本語だとこれらが全部「仕事」になってしまうが、「仕事の中には、将来のために積み重なっていく『キャリア』と、会社や上司から与えられて一個一個こなしていくような『タスク』や『ジョブ』がある。自分は今どっちをやっているのかというのを意識した方がいい」という。
U22の桜井から「働いているとその感覚はすごくわかるのですが、まだ働いたことがない学生はどうイメージしたらいいでしょうか」と聞いたところ、村上さんからは次のようなアドバイスがあった。
「新入社員の仕事を考えてみましょう。最初はとりあえず指示されたタスクを120%でやるしかない。そのとき大事なのは、受け身じゃなくて、先輩や上司とコミュニケーションが必要です。締め切りを確認するところから始まり、3割ぐらいできた段階で軽く見せる。さらに改善提案など、どんどん自分の意思を含めてコミュニケーションをとっていく。もし期待以上の成果を出せれば、他の仕事もやってみないかと声がかかる。そのキャッチボールの繰り返しがキャリアにつながっていくはずです」
求められるスキルが多様化
キャリアを意識する学生はスキルについても関心が高い。フィナンシャル・タイムズの記事「2020年代に必要な5つのビジネススキル」を引用しながら、最近注目のソフトスキル(コミュニケーション能力などの非定型スキル)について解説した。
これから求められるソフトスキルについて村上さんは「変化が早いので、とりあえずやってみて判断するという適応力は大事だと思います。それから最近リーダー教育の中に、コンパッション(共感)がキーワードとして出てきているんです。コロナ禍で職場がコミュニケーション不足になりそうなときに、メンバーの気持ちを理解した上で助けていくことがこれからのリーダーに求められるスキルの1つになっています」と語る。

求められるスキルについては、企業の求人においても変化が見られる。「求められるスキルが多様化していて、色々な職種でスキルの掛け算が増えているのが最近のビジネスの特徴です。リンクトインの人材ビジネスのデータ上でも、エンジニアでプログラミングのコードが書けるということにプラスしてプレゼンが上手、イベントに登壇もできる、というような人の需要が顕著に増えています」(村上さん)といった動向があるという。
メンバーシップ型が合うケースもある
イベント中、Zoomのチャット機能を使って、参加学生からの質問やコメントも受け付けた。米国に留学中の学生からは、「どの業界のどんな会社に入るかということよりも、米国ではどんなチームのどんなポジションで働きたいのか、具体的に説明しないといけない機会が多い。日本ではあまりそういう話にならない」という声があがった。
ジョブ型に対比して、日本企業の多くはメンバーシップ型だと言われる。両者のメリット・デメリットについて質問が出たところ、村上さんは「やりたいことがよくわからないという場合には、定期異動で自分の好きな仕事を探していけるメンバーシップ型がいいかもしれません。ジョブ型では、違う仕事がしたくなったら大学院などでもう一度勉強し直してから応募するということをしないと職種を変えることは難しいです」と答えた。
最後に、日本型(メンバーシップ型)の雇用システムが今後どう変わっていくべきかについて、村上さんはメンバーシップ型とジョブ型のどちらがいいかという二元論は危険だと指摘した。「メンバーシップ型もうまく機能している部分とそうでない部分があって、ジョブ型を日本に導入すればうまくいくわけではありません。日本は歴史的な経緯で、(雇用についての)社会保障を会社に依存してしまっているという構造的な問題もあります。しかし時代の変化とともに、会社もそこまで強くなってきている部分もある」と述べたうえで、解像度を高くして議論する必要があると強調した。
青学大理工卒。在学中に電脳隊を設立。経営統合した携帯電話向けソフト開発、ピー・アイ・エムとヤフーとの合併に伴い、2000年ヤフー入社。ソフトバンク(当時)による買収に伴い06年、英ボーダフォン日本法人出向。11年ヤフー退社、12年同社復帰、執行役員チーフ・モバイル・オフィサー(CMO)。17年リンクトイン・ジャパン代表。
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。
関連企業・業界














