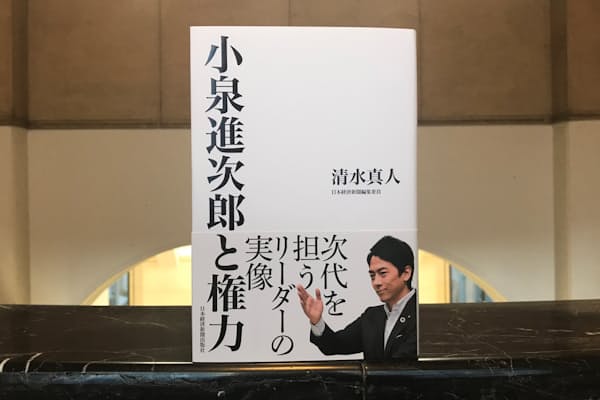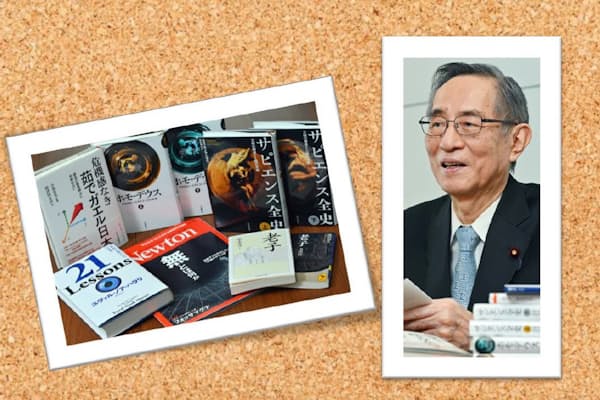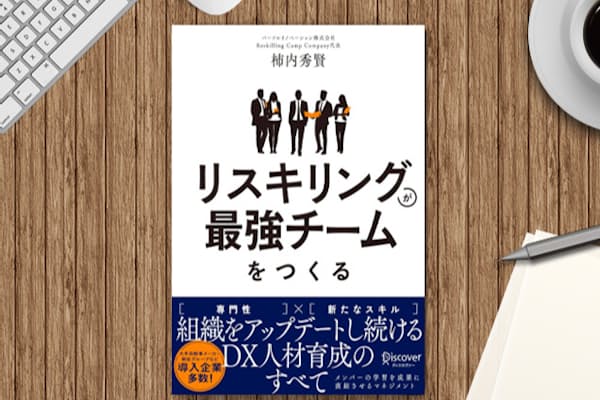「アレクサンダー大王」を座右に 戦い続ける姿に共感
環境相 小泉進次郎氏

「政治も一人では戦えません」と語る小泉進次郎氏

こいずみ・しんじろう 1981年生まれ。関東学院大卒、米コロンビア大で修士号。復興政務官、自民党農林部会長、厚生労働部会長を歴任。2019年9月から現職。
家にある本棚を見て「おやじはこういう本を読んでいるんだな」と思ったりしていました。父が部屋にこもっている時は、たいてい読書をしていた。自分にとって「おやじ=読書」が原体験のイメージです。
幼いころ兄と私が寝ていた畳の部屋に父が入ってきて、本の読み聞かせをしてくれました。『一杯のかけそば』を読んでもらった時に、父はだんだん感極まって声が詰まってくる。泣きながら読んでいるのが分かると、子供心に気づいちゃいけないと思って寝たふりをした。おやじが部屋を出た後にパッと目を開けた記憶があります。
父は動物好きで、今でもNHKの動物番組をよく見ている。本も『シートン動物記』と『ファーブル昆虫記』をときどき読んでもらいました。いま環境相として生物多様性の問題を考える時に、私の中ですぐファーブルとシートンの思い出につながる。育ってきた環境はやはり大事だなあと思う。父に感謝している。
通っていた歯医者さんの待合室にあった絵本の『ぐりとぐら』も好きでした。私の息子はまだ生後7カ月です。話は分からないけど、絵本がすごいなあと感心するのは、パラパラと見せるだけでも反応があること。本が身近にあって、読み聞かせしてもらえる環境を私も用意してあげたいと思います。
中高生のころ、父に「このシリーズを読んで面白くないと思ったら、どの歴史小説も面白くない」と言われたのが司馬遼太郎の『国盗り物語』『新史 太閤記』『関ヶ原』『城塞』の4冊。読んでみたら本当に面白くて、それから歴史小説を自然に読むようになりました。
父のことを時空を超えて生まれてきた武士のようだなと思う時があります。「今はいいねえ、権力闘争に敗れても首は取られないから」とか、「昔ならこんな噂話が聞こえてきただけで死罪だな」といった言葉をよく聞かされました。基準は殺されるかどうかなんですよね(笑)。
私にとっての「座右の書」と言えるのが、塩野七生さんの『ギリシア人の物語3 新しき力』です。アレクサンダー大王の生涯を描き、彼は若くして亡くなりましたけど最後まで戦い続けた。政治の世界も一つの戦いが終わると、次のテーマを見つけて日本のため改革の風穴を開ける戦いが続く。アレクサンダーの生きざまに共感する。
アレクサンダーが先陣を切って敵に突入していく時に、周りには大将の首を取らせないために必死で守る仲間がいる。政治も一人では戦えません。「この人のために」と支えてくれる仲間が、政治、官僚、民間の世界においても欠かせない。アレクサンダーのように歩み続けたいし改革に挑み続けたいと思って、この大臣室にも彼を描いた「イッソスの会戦」のモザイク画の写真を飾っています。