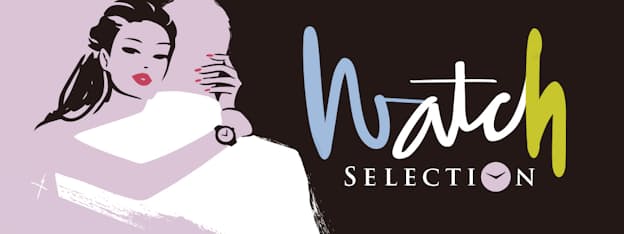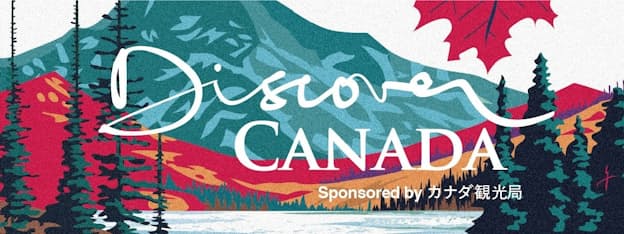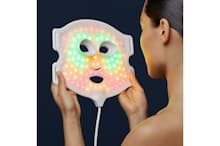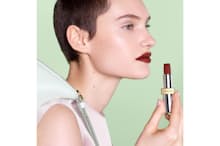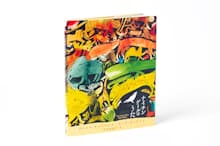コロナショックがビジネスマンの働くスタイルを大きく変えている。深刻な打撃を受けたのがスーツだ。テレワークでカジュアル化が一段と進み、着用する機会が激減。入社式や対面でのリクルート活動がとりやめとなり、“ビギナー市場”も消失した。このまま「脱スーツ」の流れは加速するのか。服飾評論家の石津祥介さんが熱く唱えるのは「スーツは男のおしゃれの神髄。今こそ楽しまなければ損」という逆張りの提言だ。そこで今回のお題は、スーツの楽しみ方について。在宅勤務でスーツから遠ざかった人も、酷暑の和らぎに合わせて思わず袖を通したくなるような、魅力あるうんちくに耳を傾けてみよう。
「誰もがかっこよくみえる」のがスーツ
――石津さん、きょうはいつもの紺ブレではなく、茶のスーツですね。コットン地ですか。
「スーツの話だから、家に帰ってスーツに着替えてきましたよ。普通の紺のスーツではないのが僕のスタイル。こちらはコットンなのだけど、着た時の感覚はウールのサージみたい。俗にいう、コットンポプリンです」
「要はビジネススーツらしくスーツを着たくないということ。日経読者であるビジネスマンのみなさんは難しいな、と思うかもしれません。でもね、きょう僕がこの服を選んだのは、スーツもこういうふうに遊んだら、と提案したかったからなのです」

この日のスーツは厚地のコットン。カジュアルなベルトと茶のレジメンタルタイを合わせた
――コロナショックで一層カジュアル化が進み、スーツを着るシーンが減りました。少しさみしい気がしています。
「だったら、スーツもカジュアルに着こなしたらどう? 僕みたいに」
――なるほど。ジャケットとパンツというビジネスカジュアルは難易度が高いという声もありますが、スーツは1着でキマります。女性のワンピースのように。
「スーツはだれもがかっこよくみえる装い。もっと言えば、スーツでかっこよく見せられない人が、カジュアルスタイルをすてきに着こなせるわけがない。だからスーツをどうカジュアルに着こなすかを考えたらいい。だいたいスーツを楽しまないなんてもったいないですよ。男の特権、男の戦闘服なんだから」
――コロナを機にビジネススーツそのものの品ぞろえも変わってきました。この夏はセットアップが売れました。
「涼しげな軽い素材のセットアップに、Tシャツを合わせる人がずいぶんいました。ただ、それは暑さ対策もある。スーツの本番は秋。商品が出そろい、本格的に楽しめる季節がやってきます。男にとって一番おしゃれのしがいがあるスタイル、それがスーツなんだ」