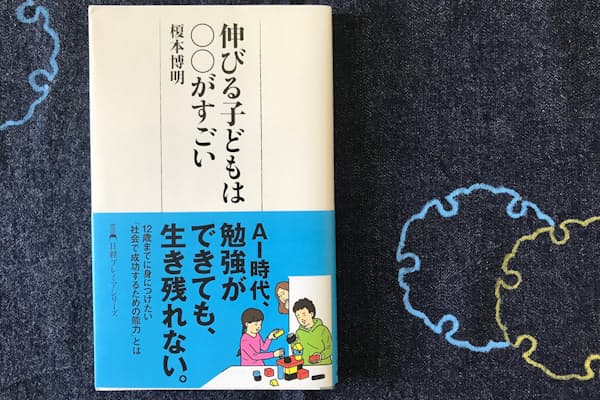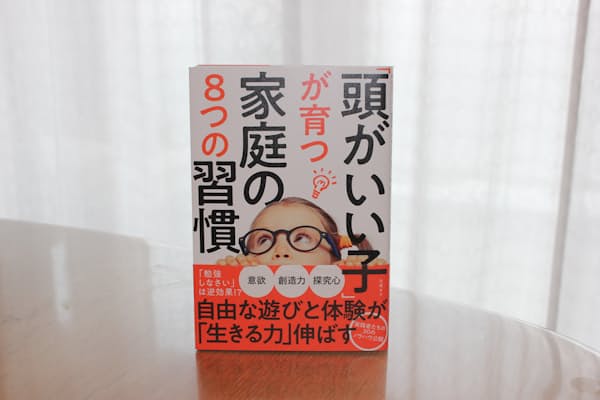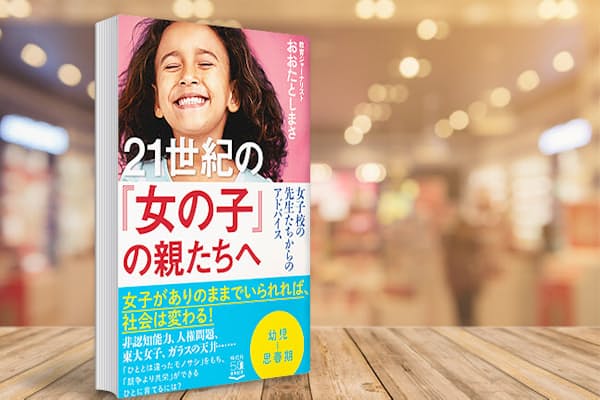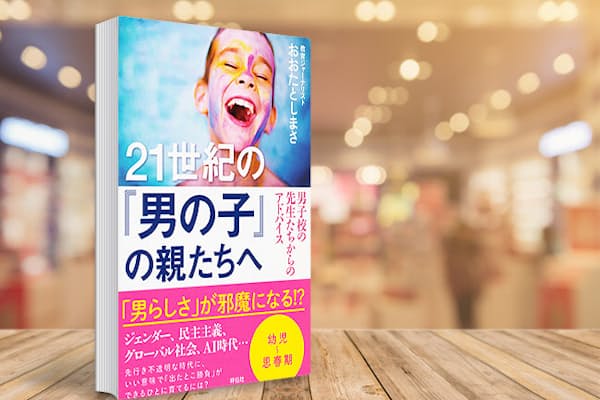DX時代の「エリート教育」 共感と創造で世界を変える
『新・エリート教育』著者 竹村詠美さんに聞く

課題解決を実行する力を育む教育とは
AI(人工知能)やロボティクスが普及する社会では、ビジネスリーダーに求められる資質が大きく変化する。創造力を駆使して社会の課題を解決する力が、よりいっそう重要になるだろう。先端的な教育のトレンドを紹介する書籍『新・エリート教育』を出版した竹村詠美さんに、子どもたちの個性と能力を伸ばす教育のあり方を聞いた。
記憶中心型の教育に限界

竹村詠美さん
当時、息子が小学3年生、娘が年長児でした。彼らは「iPad(アイパッド)」「iPhone(アイフォン)」第1世代で、幼稚園からデジタル機器を触っています。オンデマンド世代に従来型の学び方が適しているのか、いろいろと感じることありました。長男は自由な校風の私立の一貫校に通っていましたが、学校がちっとも楽しそうに見えない。自分自身が小学校の時はすごく幸せでしたから「何が欠けているのだろうか」と気にかけていました。
「問題を探るには日本だけ見ていてもだめだ。世界の先端教育を自分の目で確かめよう」。そう思い立ちました。経営コンサルタント出身なので、情報を集めて分析することは得意です。アメリカを皮切りに、モンテッソーリ教育が有名なイタリアや韓国、イスラエルなどを回りました。教育先進地域で知られる北欧の事例も研究しました。
同時に、日本国内の教育についてもいろいろ調べ始めました。学校を訪問してインタビューする傍ら、教育ドキュメンタリーの自主上映会の活動にも興味を持ちました。そこで「AIやロボットが生活に浸透する21世紀の子どもに必要な教育とは何か」をテーマにした「Most Likely to Succeed」を保護者や子どもたちと視聴する会を主催したのです。上映の後には対話の会を開きました。また、ワークショップや未来型授業・ハッカソンなどを通じて大人と子どもが共に学ぶ国際教育イベント「Learn by Creation」の代表理事を務め、仲間と共に教育改革への理解を深めていきました。
「和魂洋才」を教育改革に
全国各地に足を運ぶことで、保護者や教育関係者が同じような悩みを抱えていることが分かりました。日本の教育は徹底して同一性が高い。これは素晴らしいことですけれど、一方で根深い社会的な問題も生む土壌にもなっています。教育を変えるには、草の根の活動が大事だと痛感しました。教育に関わる人は、ただ言われたことをやるのでは不十分です。「自分たちの学びの環境をどう整えていくのかを自分たちで考える」。そんな文化があたり前になってほしいと思います。著書では海外の事例をふんだんに紹介しましたが、一方的に「海外事例が優れているから導入してください」というのではありません。長い伝統が育んだ日本のよいところを、どう伸ばせばよいかを考えたい。日本は「和魂洋才」が得意ですから、うまく事例を活用していければと思います。