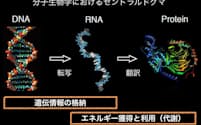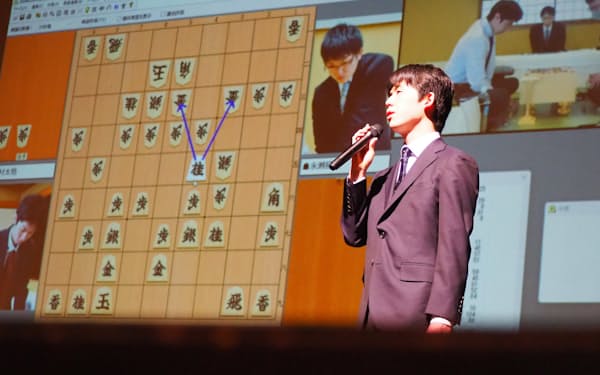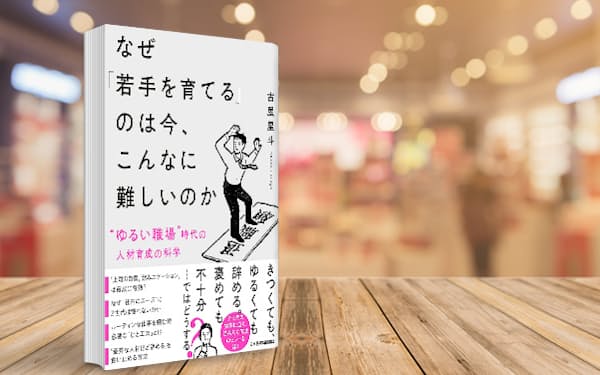こんなサプリメントにご用心 栄養疫学が教えるリスク
ケンブリッジ大学 医学部上級研究員 今村文昭(6)

◇ ◇ ◇
ケンブリッジ大学MRC疫学ユニットの今村文昭さんとの対話は長時間に及んだ。
朝9時ころから話しはじめて、気がついたらもうお昼になっていて、本当に飛ぶように時間がすぎた。
ぼくは午後、ケンブリッジ大学のメインキャンパスで別のアポイントメントがあったので、いったんアデンブルック病院を離れざるを得なかった。
お互いにまだ話が半分くらいしか済んでいないことを確認し、夕方、今村さんが仕事を終えてから、今度はケンブリッジ大学のメインキャンパスの会議室で話を再開することになった。
ここから先は、午前中の対話を前提にした「応用編」だ。
ちまたに溢れる食品情報と、ぼくたちはどうつきあっていけばいいか。
理論や方法に詳しい栄養疫学者の目から見るとどう見えるのか、これまでのところでも折に触れて述べてきたけれど(加糖飲料やフルーツジュースの件など)、あらためて目立った食品情報について、今村さんの意見を聞いてみたい。栄養成分レベルから食事パターンまで様々な階層がある中で、まずは栄養成分レベルから。
つまり、サプリメントの類はどうだろう。
「まず、ご存知の方もいると思いますが、栄養疫学の歴史で注意すべきこととして、サプリメントの服用で死亡率が上がるという衝撃的な結果が出たことがあるんです。1980年代にニンジンやカボチャなど黄緑色野菜に含まれるβカロテンが、がんを抑制するという仮説が提唱されこれは期待が持てるのではないかと盛り上がりました。日本でもβカロテン入りの健康飲料やサプリメントが発売されましたよね。でも、その後、臨床試験が行われると、βカロテンのサプリメント服用によって喫煙者など特定のグループで死亡率が上がるということが分かりました。その一方で、重篤な疾患に対する有効性を示す研究はまったく出ていません。2000年以降に行われた複数のメタアナリシスでも、サプリメントの常用が死亡率を10%弱上げるだろうという結果になりました」
健康によいと期待されていたものの効果が確認できなかっただけでなく、喫煙者などには有害であることが分かってしまった。ぼくも発売された健康飲料を時々飲んでいたから、衝撃を受けたことを覚えている。もっともこの健康飲料には、そもそも健康への影響が出るような量のβカロテンは入っていなかったそうなのだが。
では、最近、ドラッグストアでよくみる様々なサプリメントはどうだろう。
サプリメント専門ショッピングサイトで見たところ、本当におびただしい種類がある。トップページに名前が出ている人気商品としては、各種ビタミン、カルシウム、鉄といった伝統的なものはもちろん、コラーゲン、ヒアルロン酸、プラセンタ(牛や豚の胎盤のエキス!)、コエンザイムQ10、ロイヤルゼリー、そして、オメガ3脂肪酸といったものまで。
ここでは、今村さんが自分の研究でも扱ったことがある脂肪の摂取について取り上げる。サプリの効果を見るための研究ではないが、脂肪酸の効用は今村さんにとって専門の一つと言える。
「脂肪酸の種類って、固い脂質の飽和脂肪酸と液体の脂質の不飽和脂肪酸に分けられるんです。飽和脂肪酸はラードやバターなどに多く入っていて、不飽和脂肪酸は、サラダオイル、オリーブオイルなどに多く入っています。不飽和脂肪酸は、さらに、一価と多価というふうに分かれて、最近よく話題になるオメガ3脂肪酸は、多価の不飽和脂肪酸のひとつです。私自身、こういった様々な脂質と、炭水化物の摂取が、血糖値だとか、インスリン濃度だとか、糖尿病の指標にどういう影響を与えているかメタアナリシスをしました。その結論の一つは、炭水化物が多い食事よりも不飽和脂肪酸が多い食事をしたほうが、指標が改善するだろうというものでした」
なお、「脂肪酸」つながりで、有害とされる「トランス脂肪酸」はどうなのかと思った人もいるだろう。実は、トランス脂肪酸は不飽和脂肪酸の一種だが、化学構造上の理由で例外的に固くなる。だから「固い脂肪」「液体の脂肪」という分け方をするなら、「固い脂肪」だ。もっとも、トランス脂肪酸は、ある種のマーガリンやショートニングなどの製造過程でできたり(最近はかなり改善されてきている)、スナック菓子などに多いということが問題になっているので、別立てで考えた方がよいテーマではある。
さて、ここで今村さんが言及しているメタアナリシスは、研究参加者に食事を提供して、その結果、血中の指標がどう変わるかを見た研究を102件も集めて分析したものだ(※1)。系統的レビューの際に設定した条件で抽出した研究は、ランダム化して食事を提供するものに限っていて、栄養疫学分野では貴重な介入研究だ。メタアナリシスのひとつの事例として紹介したかったのだが、先に紹介した「加糖飲料」についてのものよりも扱っている事例が多く、高度に専門的な解析がほどこされているので見送った。興味のある方は是非、これまた膨大な補遺も含めて論文を見てほしい。読み解く能力に応じて、凄みが分かるだろう。
この論文やその他のエビデンスでどんなことが示唆されるのか、今村さんに簡単に述べてもらうとこんなふうだ。
「食物繊維やカロリーの摂取量は別に考えるものとして、不飽和脂肪酸、あるいは液体の脂肪は比較的よくて、飽和脂肪酸、固体の脂肪はよくもなく悪くもない。そして、私たちの身体の燃料となる炭水化物はそんなによくないといったところです。糖尿病関係以外の話ももちろん網羅しなくてはなりませんが、個人的には炭水化物も飽和脂肪酸についても毛嫌いすることなく、ほどほどならと考えています」
というわけで、不飽和脂肪酸はかなりよさげである。少なくとも糖尿病の予防効果があるのではないか。しかし、食品の中、食事パターンの中で摂取するのと、サプリメントとして単独で摂取するのでは違う。不飽和脂肪酸のうちにオメガ3脂肪酸も含まれるわけだが、はたしてサプリメントを飲めば効果は期待できるのだろうか。

「私のメタアナリシスで検討している不飽和脂肪酸というのは、オメガ3脂肪酸とオメガ6脂肪酸というものを足し合わせたものです。そのうち、オメガ6脂肪酸の摂取の方が高くて90パーセントにもなるので、オメガ3脂肪酸に関する知見を推察するには至りません。それに、糖尿病の患者に食事を与えた研究ですので、いずれにしてもサプリメントの効果はわからないんですよ」
つまり、オメガ3脂肪酸のサプリの効用を知りたければ、まさに「オメガ3脂肪酸のサプリ」そのものを対象とした研究を見ることが必要だ。当たり前といえば、当たり前なのだが、ぼくを含めて、世の人はすぐに「不飽和脂肪酸がよいなら、そのうちの一つであるオメガ3脂肪酸だけを補ったら健康によいのでは」と飛躍してしまいがちだ。
「オメガ3脂肪酸をサプリとしての効果を見た研究もありますが、糖尿病に関しては良好な結果は得られていませんね。日本の研究で、心疾患か脳卒中の既往歴のある人で二次予防効果が見られましたが、やはり健康な人が飲んで効果があるかは分からないので、この時点で推奨するのはちょっと無理があります」
とのことだ。
https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002087
結局、サプリメントで安心して服用できるのは、長い歴史があるビタミンやカルシウム製剤くらいだというとても保守的な結論にならざるをえない。
「いえ、実は、それさえも言えなくて……」と今村さん。

「カルシウムやビタミンDは、『骨を強くするのに必要なもの』と言われますし、実際に生化学的な知見は確立されています。でも一般的な成人がサプリメントで摂取したとしても、ベネフィットは限られていると考えてよいでしょう。その一方で、眉唾ものかもしれませんが循環器系疾患や腎臓への副作用の疑いも指摘されています。鉄剤のように貧血に対する効果が示されているものでも他の疾患のリスクを上げる可能性があると指摘されていますし、発展途上国では夜盲症を予防するビタミンAでも、飲みすぎるとビタミンA過剰症で肝臓を傷めたりします。こういったことまで含めて考えないといけないんですが、一般の人にそこまで求めるのは酷ですよね」
議論が込み入ったところに入ってくると、結局は栄養疫学を始めとする専門家でないと判断が付きかねる領域に至る。その際にはぜひプロに解説してもらいたいものだと思う。それも、巨大なサプリメント業界と利益相反のない立場から。
ぼくたちアマチュアができることといえば、まず「すぐに飛びつかない」ことを強調したい。また、もう少しだけ踏み込むとしたら、「メカニズムとして合理的に思えても、実際に効くとは限らないし、思いもしない副作用の可能性は常にある」ことを肝に銘じることも大事だろう。
不思議に思われるかもしれないが、体内での働きのメカニズムがかなり分かっていると思われる栄養素についても、サプリメントの総合的な効果はよく分からないことが多い。ましてや、もっと新規な栄養素で、その働きについてメカニズムを中心に語っているものは要注意だ。
例えば──
物質○○には、強い抗酸化作用があり、血液中の活性酸素を一掃してくれる。活性酸素はLDLコレステロール(いわゆる悪玉コレステロール)を変性させて血管壁に付着、蓄積させることから循環器系の疾患につながる。よって、物質○○のサプリメントを飲むと健康に良い。
というような言説だ。
こういうものは、部分部分は正しくても、全体としてはつぎはぎだらけで疑わしいことも多い。また、かりに十分に妥当な内容でも、サプリとして摂取したときの効果の証拠があるものは少ない。「エビデンスがないから、メカニズム論に傾倒するのだと考えるといいかもしれません」と今村さんも言っていた。
だから、現況では、「すごいメカニズム」が解説されていたら、それと同時に、サプリ摂取に関する疫学研究、臨床研究について言及があるかどうかは常に意識したほうがよい。
その上で──
「もしも、貧血や疲労感を抱いてサプリの利用も考えたいのでしたら、ご自身の食生活などの生活習慣を見直すことも選択肢にいれつつ、臨床医や栄養士にお世話になるのが適当だと思いますよ」
というのが、今村さんからの助言である。
=文・写真 川端裕人
(ナショナル ジオグラフィック日本版サイトで2018年10~11月に公開された記事を転載)
1979年、東京生まれ。英国ケンブリッジ大学医学部MRC疫学ユニット上級研究員。Ph.D(栄養疫学)。2002年、上智大理工学部を卒業後、米コロンビア大学修士課程(栄養学)、米タフツ大学博士課程(栄養疫学)、米ハーバード大学での博士研究員を経て、2013年より現職。学術誌「Journal of Nutrition」「Journal of Academy of Nutrition and Dietetics」編集委員を務め、「Annals of Internal Medicine(2010~17年)」「British Medical Journal(2015年)」のベストレビューワーに選出された。2016年にケンブリッジ大学学長賞を受賞。共著書に『MPH留学へのパスポート』(はる書房)がある。また、週刊医学界新聞に「栄養疫学者の視点から」を連載した(2017年4月~2018年9月)。
1964年、兵庫県明石市生まれ。千葉県千葉市育ち。文筆家。小説作品に、肺炎を起こす謎の感染症に立ち向かうフィールド疫学者の活躍を描いた『エピデミック』(BOOK☆WALKER)、夏休みに少年たちが川を舞台に冒険を繰り広げる『川の名前』(ハヤカワ文庫JA)、NHKでアニメ化された「銀河へキックオフ」の原作『銀河のワールドカップ』(集英社文庫)とその"サイドB"としてブラインドサッカーの世界を描いた『太陽ときみの声』『風に乗って、跳べ 太陽ときみの声』(朝日学生新聞社)など。
本連載からのスピンアウトである、ホモ・サピエンス以前のアジアの人類史に関する最新の知見をまとめた『我々はなぜ我々だけなのか アジアから消えた多様な「人類」たち』(講談社ブルーバックス)で、第34回講談社科学出版賞と科学ジャーナリスト賞2018を受賞。ほかに「睡眠学」の回に書き下ろしと修正を加えてまとめた『8時間睡眠のウソ。 日本人の眠り、8つの新常識』(集英社文庫)、宇宙論研究の最前線で活躍する天文学者小松英一郎氏との共著『宇宙の始まり、そして終わり』(日経プレミアシリーズ)もある。近著は、「マイクロプラスチック汚染」「雲の科学」「サメの生態」などの研究室訪問を加筆修正した『科学の最前線を切りひらく!』(ちくまプリマー新書)
ブログ「カワバタヒロトのブログ」。ツイッターアカウント@Rsider。有料メルマガ「秘密基地からハッシン!」を配信中。
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。