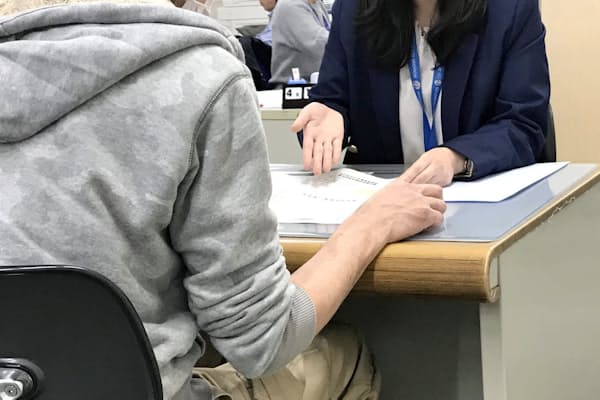淘汰と創造の時代がくる 経営者に求められる「決心」
ストライク 荒井邦彦社長

ストライク 荒井邦彦社長
新型コロナウイルスの感染拡大が経済や社会に大きな変化をもたらしている。ニューノーマル(新常態)の時代を迎え、中小企業は生き残るために何をすればいいのか。中小企業向けにM&A(合併・買収)仲介を手がけるストライクの荒井邦彦社長に聞いた。
◇ ◇ ◇
――新型コロナは中小企業にどのような影響を与えていますか。
「宿泊、旅行、飲食をはじめ多くの業種が厳しい影響を受けています。特に借入金に頼って事業展開したところは深刻なようです。プラスの恩恵を受けている会社もありますが一部に限られている印象です」
「ただ、緊急事態宣言の間に休業して店舗を移転、数カ月後の新装開店を決めるような飲食店経営者もいます。休業要請の期間を新規開店の準備期間とした格好です。このように、体力を蓄えていた会社は、知恵を絞って次の展開へ向けた準備を進めているのではないでしょうか」
平時から体力を蓄えていた会社が生き残る
「経営者の多くが『今どうすれば生き残れるか』を気にしていることと思います。しかし、全てを一気に解決できる魔法のつえはありません。私に言えるのは『いつ何時こういう危機的な状況があったとしても耐えうる体力をつけましょう』ということです。危機に備えるためには平時の努力が大事だということです」
――体力が限られる会社はどうすればいいのでしょうか。
「今の段階では『なんとか資金をやり繰りして乗り切りたい』『誰かに助けを請うより、まず自助努力でなんとかしなくては』と考えている経営者が多いのではないでしょうか。緊急融資など支援策も拡充されているので、こうした制度を活用で急場をしのいでいるところでしょう」
「体力が乏しかったとしても、事業に何らかの魅力があれば再生型M&A(合併・買収)や再生型の倒産手続きを経て再起を図ることも可能です」