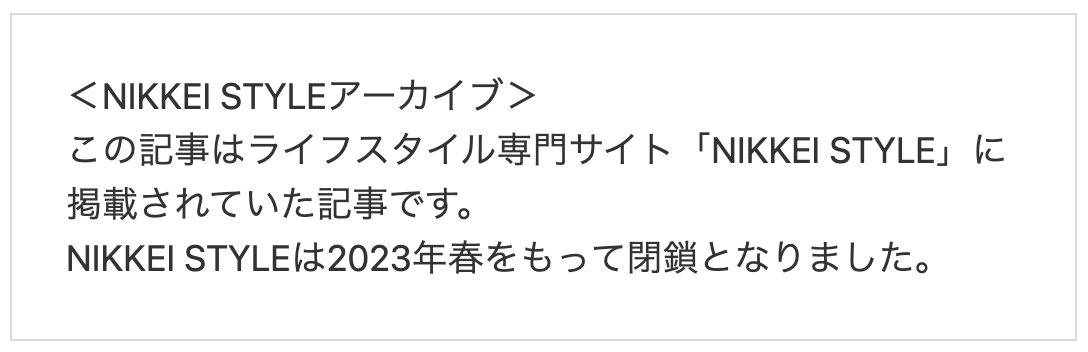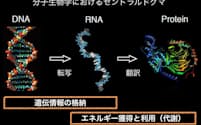その食品、健康にいいって本当? 栄養疫学が問う根拠
ケンブリッジ大学 医学部上級研究員 今村文昭(1)

◇ ◇ ◇
「健康によい食事」や「体に悪い食べ物」など、健康情報のなかでも人気の「食」の話。だがそれだけに、極端だったり矛盾したりする話も多く、何を信用していいのか分かりにくいのも確かだ。そこで、食と健康にまつわる根拠(エビデンス)を提供する栄養疫学の専門家として、世界的に活躍する今村文昭さんの研究室に行ってみた!(文・写真 川端裕人)
今の世の中には、いわゆる健康情報が満ち溢れている。
どうすれば、より健康になれるのか、誰もが知りたい。
特に食事にかかわる情報は人気だ。何を食べればよいのか。なにがヘルシーで、なにが危険な食べ物か。
栄養素レベルでは、最近では追いきれないほどたくさんの種類のサプリがドラッグストアの棚に並んでいる。そういえば、かつて悪者の代表のように扱われていた脂質も、不飽和脂肪酸という種類のものは体によいらしい。一方、炭水化物の評判はすこぶる悪い。毒だと言い切る人すらいる。脂質悪者論の時代から炭水化物ヘイトの時代へのうつりかわりが、たぶん平成の健康情報の一大イベントだったのではないだろうか。
食材レベルでは、野菜や果物は今も昔もヘルシーな食べ物だと思われており、タンパク質の供給源としては魚やチキンがよいというのもよく聞く。悪者にされがちなのはやはり炭水化物系で、砂糖はもちろん、白米を代表とする「精製された穀物」を食べることの是非が取りざたされる。その一方で、肉はどうだろう? 近所のステーキハウスは「肉は健康食!」と大きく書かれたパネルを掲げて客を呼び込んでいるが、それって本当にいいのだろうか。
食事パターン、いわば献立のレベルとしては、「地中海ダイエット」(地中海食)がすでに市民権を得ているかもしれない。野菜や果物、ナッツ、全粒粉のパン、魚介類、チキン、オリーブオイルや適量の赤ワインといった、地中海世界でよく食べられているものを真似た食事が健康的に優れているというもので、近所のイタリアンファミレスに行くと強力にプッシュされている。一方で専属コーチ付きのジムに通う知人は「低炭水化物食ダイエット」を信奉している。肉中心の食生活をよしとして、外食でステーキを頼んだ時にマッシュポテトがついてきても手を付けない。可能なところではブロッコリーなどにかえてもらうという。
こういったことは、それぞれどれだけ妥当なのだろう。極端に感じるものも多いし、お互い矛盾するものもある。
信頼できる判断の基準はありうるのだろうか。医療には、EBM(根拠(エビデンス)に基づいた医療)という概念があり、各学会がガイドラインを作って標準的な診断や治療を定めている。だから、ぼくたちは治療を受ける時にそれが妥当かどうかまずはガイドラインを参照することができるし、さらにそのもとになっているエビデンスを見ることもできる。
この時に言うエビデンスは「科学的根拠」と訳されることが多く、もともと疫学という学問に由来するものだ。日本では占いの「易学」と混同されることがあるほどマイナーな分野だが、実は様々な応用科学分野での実践に「根拠(エビデンス)」を与える重要な役割を担っている。医療におけるEBMは、まさにその具体例だ。
そして、食についても栄養疫学という分野があって、日々、まさにぼくたちが知りたい「よい食べ物」「悪い食べ物」について研究を深めている。食物に関する健康情報の多くは栄養学の範疇だと理解されていると思うけれど、その「根拠」の多くを提供するのが栄養疫学だ。ならば、直接、栄養疫学者に話を聞いてみたい。そんなふうにずっと思っていた。
機会が訪れたのは今年になってからで、たまたまぼくがロンドンに滞在中にケンブリッジ大学の栄養疫学者、今村文昭さんに会うことができた。
ロンドンからケンブリッジ駅までは直通列車で50分弱。駅前からバスに乗り、10分ほどで大学病院であるアッデンブルック病院に到着。そこでしばらく待っていると、グレイのベストを着た30代くらいの男性が、軽く手を挙げながら近づいてきた。
それが、今村さんだった。アメリカのボストンにあるタフツ大学で栄養疫学研究で博士号を取得、同じくボストンのハーバード大学公衆衛生大学院での博士研究員(ポスドク)期間を経て、2013年から英国のケンブリッジ大学MRC疫学ユニットの上級研究職に就いている。糖尿病や肥満に関する疫学を中心に活躍していると聞いている。
今村さんに導かれて病院の建物に入る。患者が行き来するエリアからエレベーターに乗り、MRC疫学ユニットのフロアに着くと、雰囲気が一変した。ぱっと見る限り、病院ではなく、ごく普通の会社のオフィスのような光景だった。たくさんデスクが並んでおり、着席している人たちはそれぞれのPCの画面を見ながら仕事をしている。ぼくたちはさらに奥まったところへと進み、こぢんまりした個室で対話を始めた。
まず今村さんの所属のMRC(Medical Research Council)について聞いておこう。字面通りに訳すなら「医療研究会議」だが、具体的なイメージがわかない。
「ちょっと特殊なんですが、私の立場は、ケンブリッジ大学の研究員であり、日本で言うところの厚生労働省の研究者でもあるんです。MRCは、医学研究の公的な資金をどう分配するかを決める機関で、研究拠点を英国各地に散らばせています。私たちのところは糖尿病と肥満にかかわる疫学のユニットです」
つまり、MRCはイギリス政府が医療関係の研究を委託する仕組みで、国立の研究所をドンと構えるのではなく、各地の大学や研究所にそれぞれのテーマに応じて予算を分配して研究を進める形を取っているのだそうだ。ケンブリッジには、「疫学」の他にも「分子生物学」や「がん」などのMRCユニットがある。
そんな中、疫学ユニットには、50人を超える研究者が所属している。ぼくが見た「オフィス」は、それらの研究者がプロジェクトごとに分かれた大部屋の一つだった。
では、栄養疫学者である今村さんのテーマが、なぜ糖尿病や肥満なのか。
「簡単に言いますと、糖尿病を予防するにはどんな食生活を送るといいのか、どんな生活習慣が望ましいかということを研究しています。今、日本でも1000万人くらい治療を要する患者さんがいると言われていますし、英国でも300万人と社会的な問題です。さらに、世界的に見ると数億人もいて、今も増えています。糖尿病って、それを入り口にしていろんな病気につながっていきます。心臓の病気だったり、腎不全だったり、血管系の疾患の危険因子です。公の立場からは医療費がかさんで社会的な負担になるということで、予防が重要です。そこで、どのような環境因子や遺伝子や代謝の因子が、どれだけ糖尿病に関与しているのか見つけて、それを介して予防をできればよいというわけです。食事というのは、そのひとつの大きな要素なんです」
つまり、今村さんの取り組みの視野と射程は、ぼくたちが素朴に知りたがる「健康情報」よりも広く長い。ぼくたちが健康情報を咀嚼する時に、こういった研究のあり方を知っておくことは大いに意味がありそうだ。今回のシリーズでは今村さんの研究の「風合い」を知ることをひとつの焦点にしていこう。
一応、確認しておくと、糖尿病は、膵臓から出るホルモンであるインスリンが十分に分泌されず、あるいは働くことができず、血液中のブドウ糖(グルコース)の濃度、つまり血糖値が高いままになってしまう病気だ。
ブドウ糖はぼくたちが生きていくための、いわば「燃料」になる必要不可欠なものだ。インスリンが働かずブドウ糖が血中に留まって細胞に入っていきにくくなるので、細胞が「飢餓状態」になってしまう。また、血中のブドウ糖濃度が高止まりし続けると、血管の細胞のタンパク質や脂質と結合するなどしてダメージを与えてしまう。「燃料」だけに、反応性が高いのだというふうにぼくは理解している。しかし、血糖値が高いだけでは自覚症状にとぼしいのが問題で、昔は合併症が出るまで気づかないこともあった。
合併症には重篤なものが多い。狭心症・心筋梗塞、脳梗塞など直接生命にかかわる疾患の他、腎症で透析が必要な状態になったり、認知症のリスクを上げたりもする。1964年生まれのぼくの子ども時代、近所で糖尿病由来の極端な血行障害から両足が壊死して切断を余儀なくされた人がいた。その後、別の知人が眼底出血を繰り返し失明したこともあった。それぞれ糖尿病足病変、糖尿病網膜症、といった病名があることを後で知った。子どもながらに非常に衝撃的な出来事だった。
いったいなにをすると糖尿病になるのだろう。食べ物が関係することは確かだが、それだけというわけではない。様々なことが絡まり合っている中、今村さんたちは、介入すると予防効果がありそうな因子を見出そうとしている。なお、糖尿病には1型と2型があり、1型は生活習慣と関係ない自己免疫系の疾患が原因だとされている。食事などの生活習慣の改善で予防が期待できるのは2型の方だ。今後、本稿の中で「糖尿病」と書いたら、基本的に2型のことだと読み替えてほしい。
では、どうやって研究するのか? 一般に「糖尿病の原因を探る研究」と聞くと、白衣を着て実験室でなにかをしたり、やはり同じく白衣の医師が患者を診たりする光景を想像する人が多いかもしれない。けれど、ぼくが見た今村さんの職場は「オフィス」そのものだった。

「白衣を着てやるようなものではないですね。普段は、コンピュータを前にしてデータを扱っています。ケンブリッジ大学は、1990年代から、ヨーロッパ10カ国の50万人を追跡しているEPIC(エピック)という名前のコホート(研究の対象になる集団)の運営に参加していて、まずそのデータを使わせてもらえます。また、2005年からは、私たちのユニットで独自に、フェンランド研究という1万2000人ぐらいのコホートをイギリス東部のノーフォーク地方の近郊で走らせていて、こっちは運動習慣に力をいれている疫学研究です。食事習慣、遺伝子なども見ているのですが、特に運動習慣と健康、病気がどう関係しているか、体に加速度センサーをつけてもらって、運動やGPSのデータを取っているのが特徴です。あと、タフツ大学での博士研究や、ハーバード大学でのポスドクでの研究では、聞いたことがあるかもしれませんがフラミンガム研究のデータを解析していましたし、ほかの北米のコホートで論文を書いたこともあります。ポスドク時代の研究テーマは、糖尿病の研究もしましたが、心臓の病気などがメインでした」
コホート研究という言葉が出てきた。コホートの語源としては、古代ローマの歩兵隊の1単位のことだそうだが、ここでは観察対象となる集団のことを指している。数千人から数十万人という大きな集団(コホート)を長期間追跡することで、どんな生活習慣なり、環境要因なりが、病気や健康に関係しているのか見つける。大規模なコホート研究は疫学研究の華であり、1948年にマサチューセッツ州フラミンガムで始まったフラミンガム研究はどんな疫学の教科書にも出てくる古典的でなおかつ現役のコホート研究だ。
今村さんはフラミンガム研究など北米のデータから始め、今では欧州の50万人規模のEPIC研究や、1万2000人と比較的小さめではあるけれど「運動習慣」に特に力を入れたフェンランド研究を「自分のコホート」として研究することができる立場なのだった。
(ナショナル ジオグラフィック日本版サイトで2018年10~11月に公開された記事を転載)
1979年、東京生まれ。英国ケンブリッジ大学医学部MRC疫学ユニット上級研究員。Ph.D(栄養疫学)。2002年、上智大理工学部を卒業後、米コロンビア大学修士課程(栄養学)、米タフツ大学博士課程(栄養疫学)、米ハーバード大学での博士研究員を経て、2013年より現職。学術誌「Journal of Nutrition」「Journal of Academy of Nutrition and Dietetics」編集委員を務め、「Annals of Internal Medicine(2010~17年)」「British Medical Journal(2015年)」のベストレビューワーに選出された。2016年にケンブリッジ大学学長賞を受賞。共著書に『MPH留学へのパスポート』(はる書房)がある。また、週刊医学界新聞に「栄養疫学者の視点から」を連載した(2017年4月~2018年9月)。
1964年、兵庫県明石市生まれ。千葉県千葉市育ち。文筆家。小説作品に、肺炎を起こす謎の感染症に立ち向かうフィールド疫学者の活躍を描いた『エピデミック』(BOOK☆WALKER)、夏休みに少年たちが川を舞台に冒険を繰り広げる『川の名前』(ハヤカワ文庫JA)、NHKでアニメ化された「銀河へキックオフ」の原作『銀河のワールドカップ』(集英社文庫)とその"サイドB"としてブラインドサッカーの世界を描いた『太陽ときみの声』『風に乗って、跳べ 太陽ときみの声』(朝日学生新聞社)など。
本連載からのスピンアウトである、ホモ・サピエンス以前のアジアの人類史に関する最新の知見をまとめた『我々はなぜ我々だけなのか アジアから消えた多様な「人類」たち』(講談社ブルーバックス)で、第34回講談社科学出版賞と科学ジャーナリスト賞2018を受賞。ほかに「睡眠学」の回に書き下ろしと修正を加えてまとめた『8時間睡眠のウソ。 日本人の眠り、8つの新常識』(集英社文庫)、宇宙論研究の最前線で活躍する天文学者小松英一郎氏との共著『宇宙の始まり、そして終わり』(日経プレミアシリーズ)もある。近著は、「マイクロプラスチック汚染」「雲の科学」「サメの生態」などの研究室訪問を加筆修正した『科学の最前線を切りひらく!』(ちくまプリマー新書)
ブログ「カワバタヒロトのブログ」。ツイッターアカウント@Rsider。有料メルマガ「秘密基地からハッシン!」を配信中。
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。