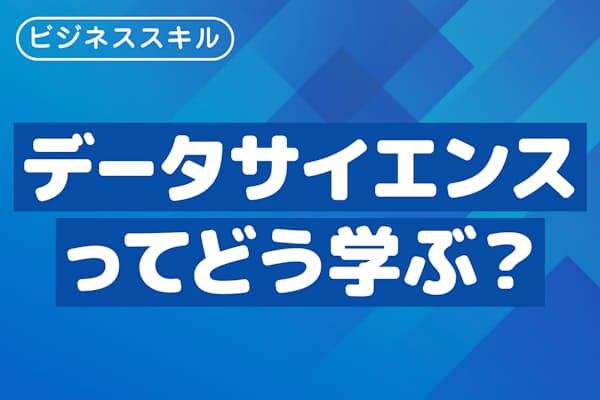名医の技、AIで現場に 起業家になったドクター
アイリス代表取締役 沖山翔氏

医療ベンチャーのアイリス(東京・千代田)。同社を率いる沖山翔氏は代表取締役兼医師としてAI(人工知能)を使って早期に高精度のインフルエンザ診断を支援する医療機器を開発している。新型コロナウイルスが世界的な大流行となっているが、インフルエンザも国内で年間1000万人超がかかるという深刻な感染症だ。AIをどのように医療に応用しようとしているのか、起業家兼ドクターの沖山氏に聞いた。
◇ ◇ ◇
「喉を見てインフルエンザか否かを正確に診断できるなんてすごい。まさに匠(たくみ)の技だな」。沖山氏は内科医の宮本昭彦医師の論文を読んでうなった。インフルエンザの検査には通常、咽頭あるいは鼻腔(びこう)から検体を採取して診断キットにかけて判定材料とするのが一般的。だが、発症してから24時間以上経過しないと診断精度が上がらず、全体で6~7割程度といわれる。
しかし、宮本医師はインフルエンザを視診で分かるという。喉に「インフルエンザ濾胞(ろほう)」と呼ぶ独自の腫れ物ができることを突き止めたからだ。色合いや形、大きさなどが他の風邪による腫れ物と微妙に異なるという。ただ「宮本先生のようなベテランの医師でないとなかなか高い精度で見分けることができない」のが実情だ。
沖山氏は2010年に東京大学医学部を卒業後、救命救急医としてあらゆる病気やけがに立ち向かってきた。都内の大規模病院で、時には「36時間連続勤務」で対応し、沖縄県の離島をドクターヘリで飛び回った。だが、限界も感じた。医者はどんなに頭脳明晰(めいせき)で豊富な知識を習得しても、すぐに名医になれるわけではない。臨床の現場でより多くの患者を診て10年、20年単位で経験を積まないといけない。外科医のバリューは手術の症例数で決まるといわれる。
医師不足のなか、病院勤務の若手医師は日々の診療に加え、論文を読んだり、当直勤務に追われたりして、疲労困憊(こんぱい)に陥るケースが少なくない。国や自治体の財政が限られ、高齢化社会で患者が増える中、名医になる前に医療現場は崩壊しかねない情勢だ。