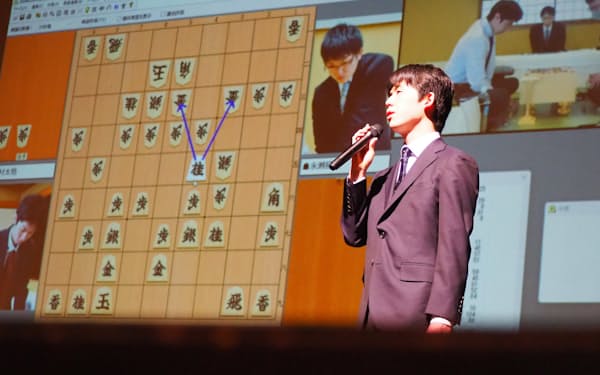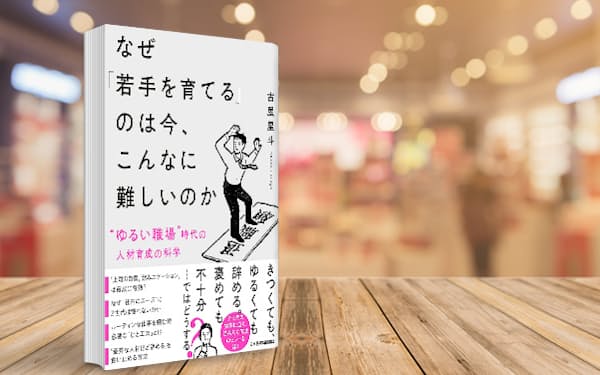子育て上手の武将は誰? 歴史はこう読めば楽しくなる
役に立つ歴史(後編)

歴史って、いろんなことの5W1Hを調べて、その因果関係を知る学問なんだって、国際日本文化研究センター准教授の磯田道史先生は教えてくれた。題材はなんでもよくて、「目」の誕生の歴史を調べると、今の人工知能(AI)の議論にもつながるんだって。でも、歴史の授業とかテストはそんなワクワク感がもてなかった人も多いよね? どうやったらもっと歴史をワクワク楽しめるか、コツをきいてみたよ。
――磯田先生のお話を聞いてると、どんな事柄も歴史の観点で楽しめそうな気がしてきました。でも、正直言って学校の歴史の授業は楽しめない人も多いですよね。
「暗記物になってしまったからでしょうね。やっとまともな歴史の話になってきました!」
――学校の先生は歴史の先生になるくらいだから、きっと歴史がもともと好きな人ですよね。だから歴史に興味持てない子の気持ちがあんまりわかんないのかなあ? というかそもそもきっと、カリキュラム終わらせるのに必死で本当に面白い歴史の話をする余裕が先生にないんだよね。だからこんなことになっている。
「もっと自分の問題として歴史を学んだほうがいいんです。例えばですけど僕はね、自分はなぜ生まれたかを細かく聞いたことがあります。両親はどうやって出会ったのか。祖父母はどうだったか。祖父母のお見合いの席でどのような順番で誰がすわってどんな会話がなされたかまで、その当時に話を聞ける人に聞きまくりました」
――それめっちゃ面白い!! たしかに「自分の歴史」っていま聞いて調べておかないと消えてなくなっちゃいますよね。
「そう。でも、いま生きている人に聞ける範囲は限られている。それで、次に古文書を読みました。たまたま実家に先祖の日誌のようなものが残っていたので、解読しました。これを繰り返すうちに、自分の家族だけではなく住んでいる地域や国、気になる人物がなぜこう行動したのかを分析したくなるんです。そうすると、図書館の中の本がすべて自分にとって輝いたものに見えるようになりました」
――先生、それ子どものときからやってたの? すごいね。そういう友達いなかった。小さいときから歴史家みたい。

「題材はなんでもいいと思います。電車でもファッションでも、口紅でも。その歴史を調べてみる。あるいは人物でもいい。ジャニーズが好きなら、ジャニー喜多川さんの生涯をテーマに調べてみたらいい。歴史というと、国同士の外交とか、王政がどう変わったかとか、産業革命、宗教革命みたいな社会科学的なものを思い浮かべがちですが、もっと身近な人物史や生きざまから入ればいい。そのうちに、だんだんと歴史的な思考ができるようになると思います」
――なるほど! 自分の好きなものでいいんだ。それなら女子高生たちも、好きな芸能人を調べるとか、追いかけるのとかは得意だからできそうですね。でも例えば、ある戦国武将のことを深く調べてみたいってなったときに、先生はどんなふうに調べるんですか? もしくは学生たちにどうアドバイスする?
「戦国武将の名前と合戦の歴史はみんな覚えるでしょうけど、そんな話ではなくて、彼らがどんな親でどんなふうに家計を考えていたか。こんな身近な話題だと面白いでしょ。例えば、江戸時代に編さんされた徳川家康についての伝記には、家康の大奥に足袋入れがあったと書いてあるの。大奥の女性たちが足袋を捨てる前には、必ずこの箱に入れなければいけないと決まっていた。そして、家康は女性たちの目の前で、まだ使えるものと捨てるものを仕分けたそうです」
――なんで? ケチだったの?
「そう。節約家なの。家康は天下人だからどんなぜいたくもできたはずなのに、足袋1足でも修繕したら使えるものは残す姿勢を見せた。そうすることで、賢く暮らす習慣を大奥の中でつくっていったのだと思います。こういうシステムをもっている家は長続きする」
「ところが豊臣秀吉は全然違いました。秀吉が朝鮮出兵で家を留守にしている間、息子の秀頼から手紙が来ます。女中が言うことを聞かないって文句が書いてある。秀吉は、『縛って置いておけ、わしが成敗する』って返事する。秀頼がおもちゃをほしいといえば、当時の明からものすごいものを取り寄せる。そんなことをしていた豊臣家は滅びました」
――へえー! そんなこと教科書には書いてなかった。そういうのを知ることができると、印象に残って自然と名前も覚えるし、その人がしたこととかにもリンクしやすくなっていいですね!! 織田信長は? なんか怖そうなイメージだけど、子どもはかわいがったのかなあ。
「自分の子どもにほとんど興味がないんじゃないかな。あるとき、家臣が嫡子の信忠のことを褒めたんですね。客人に対し、常識的にふさわしい返礼品を渡す見識があるって。ところが信長は激怒するんです。意表を突くところがないと武将は勝てないぞって。秀才で整った常識人だった信忠のことが面白くなかったんでしょうね」
「親として子どもを伸ばしたのは、前田利家です。嫡子の利長はさして優秀というわけではなかったようですが、利家は人前で息子をやたらとほめるんですよ。良いところをみつける人だったんです。利長には足りないところもあるけれど、みんなでもり立てようって。そうやって自信をもたせて、細かいところは具体的に指示して、一人前に育てたらしい」

――前田利家さん良い人! 坪田信貴先生みたい!! その時代からコーチングをしていた人がいたんですね。きっと今の時代に前田さんが生きていたら、社員が生き生き働いている会社の社長さんとか、子どもがぐんぐん伸びる学校の校長先生とかになっていそうだなあ。武将も人だもんね。人物像が浮かび上がると面白い。
「歴史とは5W1Hを調べて因果関係を考える学問だと言いましたが、もう一つおさえておきたい点があります。歴史とは、他者理解なんです。自分と違う時空のヒト・モノ・コトを一生懸命理解しようとする営みなんです。そこに、自分を重ねすぎると、歴史ではなくただの願望になってしまう」
――他者理解かあ。歴史がそんなに深いところにつながっているとは思いませんでした。なぜ、自分を重ねてはいけないのでしょうか。
「色眼鏡になるからです。色眼鏡をかけて見始めると、本当の5W1Hではなく、自分が見たい歴史を見ようとしてしまいます。自分中心の了見だけで天動説のようにみた世界は見かけ上のもので本物の世界ではありません。自分には自分の、他者には他者の理屈があります。個人でも国家でも民族でも、それぞれが自分とは違う価値観や考え方をもっていて、人それぞれに世は地動説のように動いている。お互いに自分の尺度だけで相手を見ても理解できない。こういうことを理解するときに、色眼鏡をかけずに他者を見る姿勢がとても重要になると思うのです」
「いま、日本には海外からの訪日観光客がかつてないボリュームで来ています。そして、その人数はあと10年もすれば日本の人口と同じくらいになるんじゃないか。いま、日本は他者理解がものすごく必要になっていると思うんですよ。だからこそ、相手がどう感じるか、それを知ろうとする歴史の視点が大事なんじゃないかなと思っています」
1970年岡山市生まれ。歴史家。国際日本文化研究センター准教授。
慶応義塾大学大学院文学研究科博士課程修了。茨城大学助教授、静岡文化芸術大学教授を経て2016年より現職。主な著書に「歴史とは靴である」(講談社) 「武士の家計簿 『加賀藩御算用者』の幕末維新」(新潮新書) 「天災から日本史を読みなおす」(中公新書)など。
1988年生まれ。「学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶応大学に現役合格した話」(坪田信貴著、KADOKAWA)の主人公であるビリギャル本人。中学時代は素行不良で何度も停学になり学校の校長に「人間のクズ」と呼ばれ、高2の夏には小学4年レベルの学力だった。塾講師・坪田信貴氏と出会って1年半で偏差値を40上げ、慶応義塾大学に現役で合格。現在は講演、学生や親向けのイベントやセミナーの企画運営などで活動中。2019年3月に初の著書「キラッキラの君になるために ビリギャル真実の物語」(マガジンハウス)を出版。19年4月からは聖心女子大学大学院で教育学を研究している。
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。