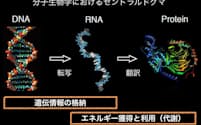日本人って、私って何? 「移民」を通して見えてくる
国士舘大学 社会学 鈴木江理子(最終回)

◇ ◇ ◇
今の日本が労働力不足であることは、ほとんどの人が合意する「事実」で、そのために「外国人材」を活用するというのが政府の方針だ。
しかし、そうやって「労働力」のみを求める政策は、生身の人間としてやってくる人たちにとって、しばしばあまりに過酷な環境を作り出す。「人身取引」「奴隷的状況」などとして国際社会から名指しの非難を受けるに足ることが起きてきた。
こんなことを続けたら、いずれ、日本に来て働きたいという人たちも少なくなるだろう。選択の余地がある人は別の国を目指し、やむにやまれず「日本しかなかった」というような人たちが送り込まれてくることになるだろう。それでもあえて来る人の中には「騙されて」身動きがとれないような形で来日する人が多かろうから、さらなる悲劇の温床にもなる。

ぼくたちの社会を維持するために、そんな酷いことが起きてよいはずがないので、改善すべきである。それについては、本当に議論の余地がないとぼくは思う。
ただ、「移民」にまつわるニュースはむしろ海外の方が多い。そして、それらの多くは別の意味で「ひどい」ものだ。アメリカのトランプ政権下で親と引き離された移民の子どもが収容所に入れられるなど、ちょっと信じられないようなことも起きている。こういったことをどう考えればよいのだろう。
「たしかに、アメリカひどいよね、ヨーロッパひどいよねって思っている人が多いかもしれません。でも、一方でアメリカやヨーロッパでは市民社会の力も同じようにあって、例えばトランプ大統領の移民排斥に対する反移民排斥の運動だって、何万と人が集まります。多分、日本ってその両方がまだ成熟していなくて、多くの場合、他人事になってしまっています。でも、本当に気をつけて周りを見ればいるんですよ。近所にいたり、知らなかったけどもクラスメイトにいたり……」
結局、目の前にいる人たちのことをいないことにしてきてしまったのが、日本の「移民問題」の特徴なのかもしれない。「いない」のだから、問題が起きても見えないし、政権も「移民政策ではない」と言い続けることができた。
でも、これからはそうはいくまい。今ですら人口の数パーセントはいる「移民」が可視化され、また、さらに増えていくとどうなるのだろうか。鈴木さんの観点では、日本は「すでに移民社会だ」ということになるけれど、それはもう避けられないものとして受け入れなければならないのだろうか。
このあたりになると、とたんに抵抗感をいだく人が増えるような気がする。
日本が日本ではなくなってしまう。日本が、ぼくたちの国ではなくなってしまう。そんな不安を感じる人もいるだろう。
「実は、2001年にネットで調査したことがあるんです。『日本人』に求められる条件って何ですかって。日本語なのか、血統なのか、日本で生まれたことなのか、日本文化なのか、日本で教育を受けたことなのか、どれが一番大事ですかと。それで、その時は圧倒的に『血統』が多かったんです。でも、最近、変わってきていると思います。私は、毎年学生たちに講義で同じ質問をするんですが、『血統』ではなく、『日本文化』や『日本語』という回答が増えてきました。時代とともに日本人像っていうのは異なってきていて、それは、社会の一つの変化なのかなと思います」
比較的最近まで、ぼくたちは「日本人」について、素朴に「血統」で決まると信じてきた。しかし、今は、その「日本人像」では対処しきれないほどの多様性を、すでに社会が持っていると多くの人が気づき始めたのだろうか。
考えてみれば、歴史的に言って、同じ場所に同じ血統の人たちが住み続けることはまずない。
たとえば、「縄文時代の日本人」(国家はなくともそこにいた人たちという意味で使う)は、「現在日本に住んでいる多数派」とは違う。国立科学博物館人類研究部が、福島県の貝塚から見つかった3000年ほど前の縄文人の核ゲノムを調べたところ、現在の日本人(東京でサンプルを得た本州出身者)のゲノムで縄文人に由来するのは14~20%ほどだったそうだ。そして、「現在の日本人」はむしろ中国、ベトナムなど、東ユーラシアの集団との親和性が高かった。いずれも、2016年に発表された論文に記されている。
それでも、ぼくたちは縄文人のことを、日本列島に住んでいた先達だと思っているわけだし、しばしば先祖、祖先、とも呼ぶ。たとえば、同じく国立科学博物館の人類研究部の海部陽介さんが主導して成功に導いた「3万年前の航海 徹底再現プロジェクト」は、台湾ルートで日本にやってきた「最初の日本人」、つまり、縄文時代よりももっと前の旧石器時代の「先祖」の航海を実証するものだった。

今は、人類の歴史上、もっとも人の移動が活発な時代だ。かつて、何世代、何十世代もかけてゆっくり起きた変化が、数十年、一世代のうちに簡単に起きうる。数十年後はともかく、これから数百年後、日本列島に住んでいる人たちが、今ぼくたちが言う意味での「日本人」と同じであるとする根拠はあまりないと思う。
だとしたら、ぼくたちが未来に送ることができるぼくららしさの中で、最良のものとは何だろう。できれば、それが不寛容と排斥の精神ではなく、寛容と相互尊重の精神に基づいたものであってほしいと願う。
最後に鈴木さん自身について。
これまで事実ベースの「ふまえておくべき日本の移民史」と、現在の問題点を伺ってきたわけだが、ともすれば問題だらけで大変なこの分野の話をしつつも、鈴木さんは常に朗らかだ。リズムよく弾むように語り、よく笑う。
書き起こすとその雰囲気は伝わらないけれど、ひょっとするとそういった前向きの力強さになにか大切なヒントが隠れているのではないかと感じていた。
というわけで、鈴木さんがなぜこういった問題にかかわり続け、また、研究をするに至ったのか聞きたい。
「実は、私、大学で学んだ専門は全然違っていて、美学なんです。でも、当時、大学教員は美学・美術史あわせての採用がほとんどなので、美術史もやらないとダメだってまわりの人に言われました。そこで、日本の美術史の勉強を始めたら、部落差別の問題に気づいてしまって。歌舞伎などの芸能も、屠畜や皮革加工なども同じ『河原者』の生業であったのに、前者がのちに高い社会的地位を獲得する一方で、後者は、いわれなき差別というか、本人が変えることのできない生まれによって可能性を奪われてきたということに引っかかってしまって。この時は研究というよりは、個人レベルでいろいろ本を読んだりするうちに、自然と在日コリアンの問題にも触れていくようになって……というのが始まりなんです」
そんな経緯で鈴木さんは大学の修士までの美学の研究から、社会学へと舵を切ることになった。「生まれ」という本人には変えることができないことで大きな不都合を抱え込むというのは、日本の「移住者」「移民」にもそのまま当てはまることだ。鈴木さんにとって、活動の場としても、研究の場としても、非常にやるべきことが多い出会いだったのだと想像できる。
「実は、そんなふうに問題に目覚めたというのは、話の半分で──」と鈴木さんは続けた。
「私が20代の時期は、ちょうどバブルの時代で、さまざまな外国人が日本に来るようになり、彼ら彼女らとふつうに接するようになりました。すると、単純におもしろいんです。違っているのがすごくおもしろい。えー、こんなもん食べてるとか(笑) 最初はちょっと食べにくかったものが、慣れるとおいしくなったりとか、そういった体験がベースにありました。オーバーステイの人も多くて、いろんな問題に直面するんですが、みんな明るいんです。それで、そんな体験から、私にとって、こういった移民とか外国人と呼ばれる存在が楽しいっていうふうになって、気づいたらここにいたんです」
ここに来て、ぼくは、おもわず、「あ」と声をあげそうになった。
話を聞いたり、関連書籍を読んだりしていると、「人身取引」だとか「奴隷的状況」だとか、ひどい話ばかりが出てきて、本当に大変なことになっていると分かる。それが日本で行われていることに対して、失望させられる。
それはとても大切なことで、ぼくも鈴木さんから聞いた話を、主に「ひどいことが起きているので背景から理解しよう」とばかりに書いた。文字で伝える中で、鈴木さんの明朗で前向きな語調はかなりのところ失われたと思う。
しかし、今、鈴木さんが指摘したのは、そのような構造の中にはめ込まれながらも、やはりそこにいるのは、まずは「人間」だということだ。

「正義論で語る以前に、まず、おもしろいんですよ。確かに、困ることはたくさんありましたけど、それは別に日本人同士だって、嫌な人とか、困ったこととか、トラブルはあるわけだから。多分、ジャパゆきさんの問題とかでもそうですけど、どこを見るかによって、可哀想と見えることと、したたかだって見えるのと、両方なんです。1人の人に、多分、いろいろな側面があって、それが見えてくるんです。追いつめられて従属的に生きざるを得ない部分もあるけども、そのなかで主体的に人生を選択し、しなやかに強く生き抜いているって、それは、私にとってとても興味深く、魅力的なことだったんです」
すごく困っていたり、それをしたたかに切り抜けたり、そして愉快だったり! それらは別に排他的なわけではなくて、同じ人の中に、同じ状況の中に共存しうる。まさにそうだ。
「勉強して移民や外国人について学んでいくと、どうしても距離があるかもしれないけども、出会って話して、一緒に食べたり飲んだりすれば楽しいです。いろんな面を見ることができて。それは本当にある面で、翻って自分自身を見つめて、日本人である、日本で生まれ育って今ここにいる私が、今生きていることをもう一回問い直すことができる。いろいろなことが当たり前のようにできている、この私っていうのは何なのかと思ったりもしますね」
ここまで話をして、ぼくは自分自身がこれまでの間、よく理解していなかったことが、大づかみに言って、2つの方面に分かれていると気づいた。
ぼくが冒頭で触れたコンビニで出会う深夜シフトの留学生たちを例にとってみよう。
2つの方面のうちのひとつは、「日本ではすでにたくさんの外国人が、多くの場合、低賃金で日々働いている」ということだ。
「接客を通じて出会えた彼ら彼女らはそこで出会えたわけですけど、他に『出会ってない彼ら彼女ら』もいるんです。たとえば、コンビニの場合で言っても、工場で弁当を作っている人とか、それを運んできてくれた人であるとか」
外国からきた人が日本のぼくたちの生活を支えているのは別に今に始まった話ではない。日本語を駆使した接客の場にはなかなか進出しにくかっただけで、ずっと前から人目につかない職場には外国からの労働者がいた。今、目につくようになったから「増えた」というのではないのである。この件については、今回、多くの紙幅を費やして、説明できたと思う。
そして、もうひとつぼくが見逃していたことというのは──
「労働者ではない側面です。彼ら彼女らがコンビニに来る前や、終えた後、どうやって帰るのかとか、何食べてるのか何が楽しいのかなって、そういうことに思いを馳せると、もう少し同じ人間として身近に見えてくると思うんですけど」
縁あって同じ時代、同じ土地に暮らしているぼくたちは、接点がコンビニだけだったとしても、それぞれ、生活の中で笑ったり泣いたり、喜んだり悲しんだりする存在だ。すごく当たり前のことだ。
そして、当たり前のことを認識することの先に、数十年後、数百年後の「ぼくたち」の形もくっきりと浮かび上がってくるだろうと、鈴木さんと話していて確信を抱いた。
=文 川端裕人、写真 内海裕之
(ナショナル ジオグラフィック日本版サイトで2019年8月に公開された記事を転載)
1965年、愛知県生まれ。国士舘大学文学部教授。博士(社会学)。NPO法人移住者と連帯するネットワーク(移住連)副代表理事。2008年、一橋大学大学院社会科学研究科社会学博士課程修了後、国士舘大学文学部准教授などを経て2015年より現職。『日本で働く非正規滞在者』(明石書店)で平成21年度沖永賞を受賞したほか、『外国人労働者受け入れを問う』(岩波ブックレット)、『移民受入の国際社会学 選別メカニズムの比較分析』(名古屋大学出版会)、『移民政策のフロンティア 日本の歩みと課題を問い直す』(明石書店)、『移民・外国人と日本社会』(原書房)など共編著書も多数ある。
1964年、兵庫県明石市生まれ。千葉県千葉市育ち。文筆家。小説作品に、『川の名前』(ハヤカワ文庫JA)、『青い海の宇宙港 春夏篇』『青い海の宇宙港 秋冬篇』(ハヤカワ文庫JA)、NHKでアニメ化された「銀河へキックオフ」の原作『銀河のワールドカップ』(集英社文庫)とその"サイドB"としてブラインドサッカーの世界を描いた『太陽ときみの声』(朝日学生新聞社)など。
本連載からのスピンアウトである、ホモ・サピエンス以前のアジアの人類史に関する最新の知見をまとめた近著『我々はなぜ我々だけなのか アジアから消えた多様な「人類」たち』(講談社ブルーバックス)で、第34回講談社科学出版賞と科学ジャーナリスト賞2018を受賞。ほかに「睡眠学」の回に書き下ろしと修正を加えてまとめた『8時間睡眠のウソ。 日本人の眠り、8つの新常識』(集英社文庫)、宇宙論研究の最前線で活躍する天文学者小松英一郎氏との共著『宇宙の始まり、そして終わり』(日経プレミアシリーズ)もある。近著は、ブラインドサッカーを舞台にした「もう一つの銀河のワールドカップ」である『風に乗って、跳べ 太陽ときみの声』(朝日学生新聞社)。
ブログ「カワバタヒロトのブログ」。ツイッターアカウント@Rsider。有料メルマガ「秘密基地からハッシン!」を配信中。
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。