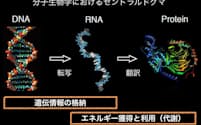戦前から現代まで 日本で暮らしてきた多様な「移民」
国士舘大学 社会学 鈴木江理子(2)

◇ ◇ ◇
移民というのは、「現在の国籍にかかわらず、国境を越えた移動により別の国に暮らすようになった人びと」のことだ。
移民の定義について誰もが合意する明確な定義はないけれど、ここは鈴木江理子教授が副代表理事としてかかわるNPO法人「移住者と連帯する全国ネットワーク」の小冊子『移民社会20の提案』から採った。また、同冊子では、移住先で生まれた移民2世や3世などを「移民ルーツ」と呼び、「広義には、(移民ルーツの)彼ら彼女らも含めて『移民』と記載している場合がある」としている。鈴木さんもこういった「移民ルーツ」まで含めて、「移民」と捉える立場だ。
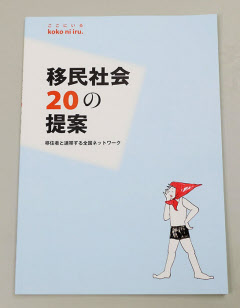
この捉え方だと、例えば、親のどちらかが外国籍で、日本に居住している「ダブル(ハーフ)」の子どもも「移民」に含まれる。ぼくは、そういう「ダブル(ハーフ)」の子たちをかなり知っているけれど、それは「移民」だろうかと少しひっかかりを覚えた。親しいダブル(ハーフ)たちは、自分が「外国ルーツ」を持つことは明確に意識しているけれど、親の片方は日本人で、自分も日本で生まれ、日本で育ち、日本語で生きてきた人たちも多く、「移民」と言われると違和感があるのではないだろうか、と。
「たしかに、ダブル(ハーフ)の子どもの場合など、本人が移民と言われることは望まない場合が多いんです。でも、私としては、彼ら彼女らの背景には異なる文化とのつながりがあることに気づくことが大事だと考えて、あえて移民として捉えています。この社会は多様な人たちで成り立っていて、地域社会にも学校の教室にも、あるいは働く職場においても、移民は身近にいるんだよということにまず気づいてほしいんです。そして、じゃあ、こういった人たちとどんな社会をつくっていくのかと考えていければということです」
まずは、多様性を認識するきっかけとして、「移民」の範囲をここまで広げておいた方がよいのでは、ということだ。実際、アメリカやオーストラリアやニュージーランドなど、移民が作った国では、「私はアイルランド系アメリカ人」「ぼくはドイツ系ニュージーランド人」といったふうに自分の移民としてのルーツを明確に意識して、明示する人たちが結構多い。そして、その結果、常に社会の多様性がイメージしやすくなるということはあるかもしれない。
「それに、今では、日本国籍を持っているからといって、必ず日本語ができるわけではないんですよね。日本語指導が必要な児童生徒の調査を文科省がやっているんですけども、そこでは外国籍と日本国籍の両方を調査の対象にしています。その調査結果では、日本国籍の子どもにも、日本語指導が必要な子がいることが示されているんです。こういった現実をふまえて、移民政策を考えていく必要がありますね」
文科省が2017年に発表した2016年度調査の結果を見たところ、「日本語指導が必要な児童生徒数」は、外国籍の場合、3万4000人あまりだった。一方、日本国籍でも、9600人おり、10年前に比べて2.5倍にも急増している。日本国籍を持っているという意味での日本人だからといって、日本語ができることになってしまうと、これらの児童生徒たちはなんの支援もなく放り出されることになりかねない。やはり、それだけの多様性をぼくたちの社会が持っていることを知らねばならない。文科省のデータ(※)はそういった現状を垣間見させてくれる。
※「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査(平成28年度)」の結果について」(文部科学省) http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/29/06/__icsFiles/afieldfile/2017/06/21/1386753.pdf
とすると、今、日本には、どんな「移民」がいるのだろうか。あるいは、いずれ「移民」になるかもしれない「外国人」はどんなかたちでここにいるのだろうか。
前回、「留学」「研修」「技能実習」「特定技能」という在留資格をあげて、それらがこんがらがって理解しにくいと言ったけれど、これらは主にここ30年程度の話だ。しかし、第2世代、第3世代まで考えるというと、それよりも前からある歴史的な経緯を含めて、見取り図を描いておかなければならなくなる。というわけで、あえて遠回りして、歴史的な経緯を見ていきたい。
「じゃあ、私が講義で使っている資料をお見せしますね」と鈴木さんはプリンタで資料を打ち出してくれて、ぼくはそこから講義を受けるモードになった。
「日本は、歴史上、移民を送り出す側の国だったので、移民(外国人)を受け入れる側になったのは、比較的最近です。けれども、移民受け入れを考えるにあたって、まず、覚えておかなければならないのは、旧植民地出身の人たちのことだと思います。日本の移民研究の中では、オールドタイマーとか、オールドカマーと呼ばれていて、つまり、戦前から日本に居住している旧植民地出身者とその子孫のことです。戦後、日本が主権を回復したと同時に日本国籍を失い、『外国人』となってしまった人々で、多くが朝鮮半島にルーツを持つ、いわゆる『在日コリアン』です」
オールドタイマー・オールドカマーという言葉は、当然、ニューカマーと対になっていて、後者は戦後新たに来日した外国人を総称するものなので、旧植民地出身者は、日本の移民受け入れの歴史の中で、一大分野だ。
ただし、今では1世の高齢化による死亡、日本国籍の取得や日本人との結婚などによって、戸籍上の外国人としてのオールドタイマーは少なくなりつつあるという。

「それでも、その存在は踏まえたほうがよくて、今、日本の過去のいろんなことが消されていってますよね。例えば関東大震災における朝鮮人虐殺に関しても、小池都知事になって以降、都知事は、関東大震災の朝鮮人犠牲者追悼式に追悼文を送らなくなりました。学校の教科書の記述もかなり変わってきていて、そういった部分が消されて、忘却されていくわけです。でも、過去を知らないと、じゃあ、なぜ朝鮮学校があるのかといった意義も分からなくなります。今、多様な人が日本に来ている時にこそ、やはり過去を踏まえる必要があると思うので、まずはそのことを強調しますね」
日本に生まれ育った人なら、誰でも、身近なところで、ここでいう「オールドタイマー」との接点があるはずだ。ぼく個人で考えても、小中高、そして大学などの学校に通う際にも、大人になって住んだ地域にも職場にも、朝鮮半島ルーツの2世、3世、つまり、ここでいうオールドタイマーがいた。ここで気付かされるのは、彼ら彼女らは、まさに本稿の定義ならまさしく「移民」だということだ。
そういったベースがありつつ、日本が次に「外国人」を受け入れるのは、1970年代の「中国帰国者」だ。1964年生まれのぼくは、この「残留孤児」の話題をよく覚えている。幼い頃に家族と生き別れて遠い国で育った人たちの帰還は、当時、まだ小学生で自分自身幼かったこともあって、胸に響いた。
「1972年に中国との国交が回復したことで、敗戦の混乱の中、中国東北地区に取り残されてしまった『残留孤児』や『残留婦人』の肉親捜しが、政府の支援のもとに始まり、『残留孤児』や『残留婦人』、その家族が、日本に永住帰国するようになりました。国費による帰国者とその家族は2万人強、私費での帰国者やその家族・親族を含めると10万人以上になると言われています」
もともと日本人だった人たちとその家族が「帰国」したのだから移民というのは違和感があるという人もいるかもしれないが、これも「国境を越えた移動により別の国に暮らすようになった人びと」であることには変わりないだろう。
さらに1978年からは、社会主義国になったインドシナ三国(ベトナム、ラオス、カンボジア)から逃れてきたインドシナ難民の受け入れが始まり、1万1000人以上が定住資格を得た。また、難民条約が発効した1982年以降は、条約に基づいて日本政府が認定した難民の受け入れが始まる。もっとも、日本の難民認定は狭き門で、これまでに認定されたのは750人(2018年末時点)にすぎない。
ここまでは戦争によってもたらされた混乱をなんとか復旧する営みや、近隣諸国の政治的な不安定に基づくものが中心だが、やがて日本が次第に経済発展するなかで、労働目的に日本にやってくる外国人が増える。
「70年代後半からは、風俗産業で働くアジア出身女性の姿を見かけるようになります。『唐ゆきさん』(日本がまだ貧しかった時代に、海外に渡った日本人女性)にならって、『ジャパゆきさん』などと呼ばれましたが、東南アジア出身女性に対する歪んだイメージを与えることにもなりました。騙されて来日した人も多かったことも問題です。その後、バブル景気の労働力不足のなか、アジア各国からの男性労働者が急増します。日本が本格的な外国人労働者受け入れ国になっていく時代です。彼らのほとんどが合法的な就労資格をもっていなかったのですが、当時は『ジャパゆきくん』と呼ばれることもありました」
多くの外国人が日本に住んで働くようになると、国際結婚も多くなる。特に「ジャパゆきさん」たちは接客を通じて日本人男性と知りあう立場だったので、日本人男性と結婚したり、シングルマザーとして日本人の子を生み、養育するようになったケースも多い。さらにいえば、日本人配偶者が見つからない農村の男性のもとに、アジア各国から結婚のためにやって来た「農村花嫁」の存在も80年代後半以降、増えていく……。
20世紀中の経緯をこのあたりまでたどったところで、いったん「年代記」を中断する。
というのも、ちょっとした注意喚起をしたいからだ。
こういった時期に日本にやってきて定着した人の子どもたちは、今、本稿を読んでいるであろう成人した日本語話者にとって、ともに同じ社会の中で成長してきた隣人であり仲間だからだ。それどころか、まさに「その人」も読者にはいるだろう。

歴史的な経緯を聞くつもりで、実際に「残留孤児」や「インドシナ難民」や「シャパゆきさん」など、最近、聞くことが少なくなっていた言葉を再確認しつつ、ふと気づいた。言葉を聞かなくなったからといって、彼ら彼女らや、その子どもたちは、いなくなったわけではない。それどころか、あれ以来、ずっといるのであって、「ぼくたち」の中の確固とした一部なのだ、と。
「学生の中にも中国帰国者の3世の子とかいますし、インドシナ難民の子も小中学生ならほぼ3世です。学生には、異なる背景をもつ人と出会うことを大事にしてほしいので、そういった友だちに出会ったときに、彼女とか彼のことが理解でき、本人たちも自信を持って自分のことを伝えられるようにできればと思っています。それで、どんな背景があってやってきた人たちがいるのかを伝えるようにしてます」
ただし、本人が自分のルーツを明らかにしたくない場合もある。
「気をつけなければいけないのは、外国ルーツとか移民の背景に、私たちの側がこだわりすぎて、あなたにはこのルーツがあるんだから、それを大事にしなさいって押しつけるのは、してはならないということです。授業が終わった後にこっそり来て、『先生、他の人には言わないでね』って、自分が外国ルーツだと教えてくれる学生もいます。アジア系だと、見た目ではわからないですし、日本生まれだったり、幼少期に来日したりしていて、日本語も普通に読み書きできる子だと私もわからないですから。ただし、『言わないでね』と伝えなければならないこと、ルーツを隠そうとする気持ちの背景を考えてみる必要があると思っています」
均質だと多くの人が思っている日本の社会で、外国ルーツの子どもの生きにくさというのは、想像にあまりある。それは、在日コリアンたちの7割が今も「通称名」で生活していることにも通底しているだろう。実はこの社会にはこれほどの多様性があるのだと気づくべきだという立場だとしても、「ルーツを大事にせよ」と強要するのはおかしなことだと鈴木さんは考えている。
「ただ、これまで接してきた子どもや若者たちの経験からすると、何かのきっかけで、ルーツに目覚めるときがくるんですよ。それまでは絶対嫌だって言っていたのに、言葉を学んでみるとか、自分の国に行ってみるとか。それで本人が目覚めることができれば、本人なりにルーツを受け入れて、葛藤がありながらも、自分自身の存在を肯定的に受けとめられたということです。しかも本人がそう思えるということは、周りの人たちがそういう本人を認めているということだと思うんですね。そうやって自分のルーツに自信が持てたのなら、それは大事にしてほしいなと思います」
=文 川端裕人、写真 内海裕之
(ナショナル ジオグラフィック日本版サイトで2019年8月に公開された記事を転載)
1965年、愛知県生まれ。国士舘大学文学部教授。博士(社会学)。NPO法人移住者と連帯するネットワーク(移住連)副代表理事。2008年、一橋大学大学院社会科学研究科社会学博士課程修了後、国士舘大学文学部准教授などを経て2015年より現職。『日本で働く非正規滞在者』(明石書店)で平成21年度沖永賞を受賞したほか、『外国人労働者受け入れを問う』(岩波ブックレット)、『移民受入の国際社会学 選別メカニズムの比較分析』(名古屋大学出版会)、『移民政策のフロンティア 日本の歩みと課題を問い直す』(明石書店)、『移民・外国人と日本社会』(原書房)など共編著書も多数ある。
1964年、兵庫県明石市生まれ。千葉県千葉市育ち。文筆家。小説作品に、『川の名前』(ハヤカワ文庫JA)、『青い海の宇宙港 春夏篇』『青い海の宇宙港 秋冬篇』(ハヤカワ文庫JA)、NHKでアニメ化された「銀河へキックオフ」の原作『銀河のワールドカップ』(集英社文庫)とその"サイドB"としてブラインドサッカーの世界を描いた『太陽ときみの声』(朝日学生新聞社)など。
本連載からのスピンアウトである、ホモ・サピエンス以前のアジアの人類史に関する最新の知見をまとめた近著『我々はなぜ我々だけなのか アジアから消えた多様な「人類」たち』(講談社ブルーバックス)で、第34回講談社科学出版賞と科学ジャーナリスト賞2018を受賞。ほかに「睡眠学」の回に書き下ろしと修正を加えてまとめた『8時間睡眠のウソ。 日本人の眠り、8つの新常識』(集英社文庫)、宇宙論研究の最前線で活躍する天文学者小松英一郎氏との共著『宇宙の始まり、そして終わり』(日経プレミアシリーズ)もある。近著は、ブラインドサッカーを舞台にした「もう一つの銀河のワールドカップ」である『風に乗って、跳べ 太陽ときみの声』(朝日学生新聞社)。
ブログ「カワバタヒロトのブログ」。ツイッターアカウント@Rsider。有料メルマガ「秘密基地からハッシン!」を配信中。
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。