8歳で年収28億円 子供ユーチューバー、過熱と規制と
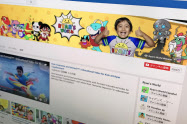
8歳で年収28億円――。こんなニュースが2019年末、世界を駆け巡りました。米フォーブス誌が発表した同年の「最も稼ぐユーチューバー」のトップに米国の少年、ライアン・カジ君が選ばれたのです。
ユーチューバーとは、インターネットサイト「ユーチューブ」に動画を投稿し、広告などで稼ぐ人を指します。カジ君はおもちゃを紹介する動画などを配信し、2年連続で世界のユーチューバートップとなりました。
フォーブスの上位10人のランキングを見ると気づくことがあります。子ども向け動画が上位を席巻しているのです。3位は5歳で、子どもが好むゲーム関連の番組を扱うユーチューバーも5人ほど入っています。
「子ども番組は視聴度が3倍以上」。米ピュー・リサーチセンターは19年にリポートを発表しました。25万人以上の登録者がいる4万3千チャンネルを分析した結果です。子ども番組は全体に占める数は多くないものの、視聴回数が他の番組より多いことがわかりました。
日本でも子どもの夢にユーチューバーが挙がる中で、悪影響を懸念する人も少なくないようです。米国では、こうした懸念を受け、規制の動きが出始めています。
米連邦取引委員会は19年秋、米グーグルに180億円の制裁金を科すことを発表しました。傘下のユーチューブが子どもの個人情報を集め、広告などが配信されていた実態が、子どものプライバシー保護に違反すると判断したのです。
制裁を受け、ユーチューブも対策を決めました。利用規約を変更し、動画を投稿する際には、子ども向けかどうかの申告が1月から必要になりました。番組内容は人工知能(AI)も使って調べるということです。
ユーチューブは本来「13歳以上が対象」としていますが、実際は年齢を偽って投稿したり、親の端末で見たりできます。今後、子ども番組を見ているユーザーのデータは、年齢に関係なく子どもの個人情報とみなします。それにより、個人の嗜好に合わせた「パーソナライズド広告」を停止します。
影響は小さくなさそうで、日本でも「業界に大激震」「収益半減じゃきかないかも」といった声が、ユーチューバーから挙がっています。一方、動画制作教室を展開するフルマ(東京・渋谷)の中條武・最高執行責任者(COO)は「視聴者にとって安全なプラットフォームになる」と前向きに捉えます。
子どものオンラインデータを巡っては、英国も保護のための規制をする方針です。子どもが安心して使えるネットの環境づくりが、世界の潮流になりそうです。
中條武・フルマCOO「上手な付き合い、教えることから」
子どもたちにとってユーチューバーはどんな存在なのか。小学生を対象にしたユーチューブ向け動画の制作教室を展開するフルマの中條武COOに話を聞きました。
――フルマの事業内容を教えてください。

「2017年に『ユーチューバーアカデミー』という事業を始めました。小学生を対象とした動画制作の単発のワークショップでした。18年からは継続的な習い事として展開しています。関東を中心に、これまで累計3千人超の小学生が受講しています。授業ではネットのリテラシーから企画立案、実際の政策までを教えています。安全に楽しく遊べるようにすることが目的です」
――子どもたちにとってユーチューバーはどのような存在ですか。
「好きなユーチューバーを尋ねると、一人ひとり違う答えが返ってきます。テレビでみる『みんなが知る芸能人』より、身近な存在なようです。教室に来る子どもたちも、ユーチューバーのマネをしてみたい、という子が多いです。例えば『タピオカを1メートルのストローで飲めるか挑戦』のような企画をやってみたいといったことです」
――子どもたちは有名ユーチューバーになりたくて教室に通っているのでしょうか。
「実際に『自分の動画をインターネットで公開して、世界中から注目を浴びたい』という動機は少ないです。それよりも『自分で動画を撮影して編集する』という作品作りに動機を持っている子どもが多いです。デジタルなコンテンツづくりの楽しさを体験したいのです。教室で制作した動画は、URLを知っている人だけがユーチューブで見られる限定公開にしています。祖父母に送る家庭が多いですね」
――親は子どものユーチューブ利用にどう向き合えばいいですか。
「親の世代には総じて、インターネットは怖いから、できるだけ触らないように、という感覚もあると思います。しかし、これからの世代の子どもたちがネットに触れないで生きていくのは難しいでしょう。闇雲に制限するより、どう上手に使っていくかということを教えたほうがいいと思います。フルマの教室ではネットリテラシーとして、個人情報や撮影場所、著作権の扱いなどについて教えています。具体的には、自宅が特定されないようにしたり、他人が映り込んで迷惑をかけたりしないようにしたりということです」
――ユーチューブの子ども向け動画に関する規制は、今後どのような影響があると思いますか。
「子ども向けの動画を制作している人にとっては、広告収入が減る可能性があるので影響があると思います。動画の構成が、より直接的な企業の商品のPRに変わる可能性もあります。一方、好きな番組を視聴する側の子どもには大きな影響はないのではないでしょうか。規制が進めば、ユーチューブは少しずつ、子どもが安全に楽しめるプラットフォームに変わっていくと思います」
(福山絵里子)
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。














