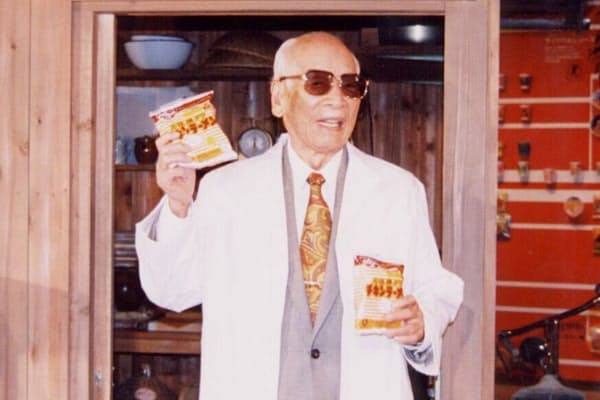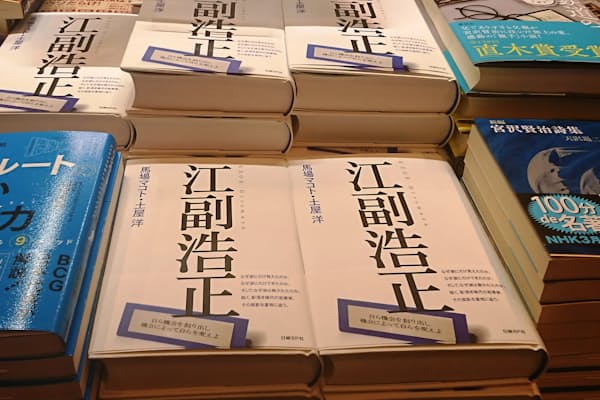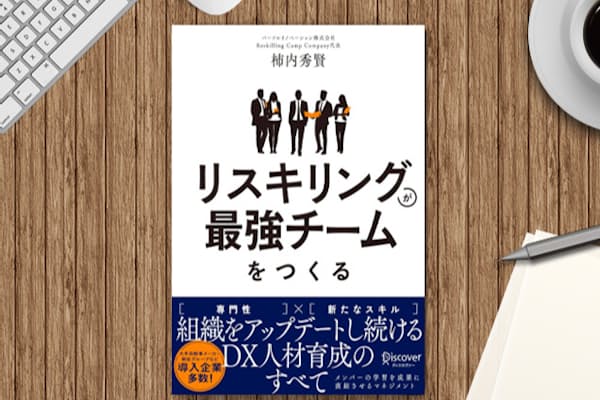「夢の実現装置」 ハーバードも驚くリクルートの強み
ハーバードビジネススクール教授 サンドラ・サッチャー氏(上)

サンドラ・サッチャー教授はリクルートの人材開発法に着目した
世界トップクラスの経営大学院、ハーバードビジネススクール。その教材には、日本企業の事例が数多く登場する。取り上げられた企業も、グローバル企業からベンチャー企業、エンターテインメントビジネスまで幅広い。日本企業のどこが注目されているのか。作家・コンサルタントの佐藤智恵氏によるハーバードビジネススクール教授陣へのインタビューをシリーズで掲載する。11人目は、「企業はいかに信用を構築し、失墜し、回復するか」を長らく研究テーマとしてきたサンドラ・サッチャー教授だ。
(下)リクルートは世界で成功するか ハーバードの視点
■社員の起業促せる不思議 ハーバードが見たリクルート
■常識超えに潜むリクルートのリスク ハーバードの視点
佐藤 サッチャー教授は2018年に「グローバル化する日本のドリームマシン:株式会社リクルートホールディングス」という教材を日本語と英語で出版されました。なぜリクルートを教材にしようと思ったのですか。
興味深いのは人材開発法
サッチャー 長らくハーバードビジネススクールで様々な企業事例を教えていますが、リクルートのような企業に出合ったのは初めてです。「リクルート事件」という大きなスキャンダルから見事に再生し、独自の理念を確立し、成長を続けている――このような企業は世界でもまれです。

ハーバードビジネススクール教授 サンドラ・サッチャー氏
特に私がリクルートの経営について興味を持ったのは、人材開発法です。中でも次の3点が新しいと感じました。
第一に、リクルートの経営陣は社員に仕事内容を指示したり、強制したりしないこと。リクルートでは自分の仕事は自分で考えなければなりません。「どのように世界の役に立ちたいか」「どんな社会問題を解決したいか」を社員に考えてもらい、会社はそのためのリソースを提供しましょう、というのがリクルートの人材育成方針です。
第二に、社員の自律性を促すために、上司が部下に対して「質問形式」でコミュニケーションをとっていること。「会社の結論はこうだから、あなたはこういう仕事をしてください」とは言わないのです。人事面談では「なぜリクルートで働いているのか」を問いかけ、部下が問題に直面したときは「あなたは今、何をすべきだと思うか」と問いかける。自分の頭で考え、進んでリスクを取る社員を育成するために、質問形式を使っているのです。
第三に、リクルートは社員の離職をネガティブに考えていないこと。リクルートでは入社して6年半(注:新卒の場合)経つと、キャリアアップ支援金や退職金などをもらう資格を得ます。「社外でやりたいことが見つかったら、リクルートを卒業してぜひ実現してください。会社はそれを支援します」という方針を貫いているのです。これによって良い意味での人材の流動性がうまれています。
リクルートからハーバードの学生が学べることはたくさんあると思いました。