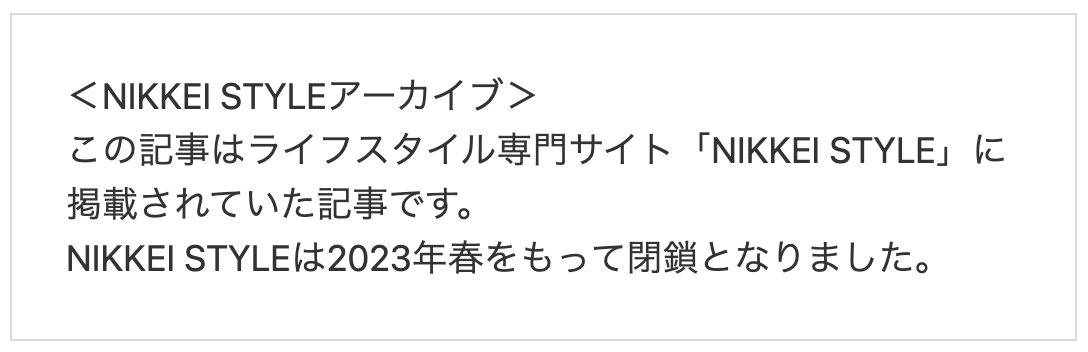湊かなえの『落日』 裁判で見えぬ真実、小説が埋める
デビュー作『告白』がミリオンセラー。超大型新人として本屋大賞をも受賞した衝撃の2009年から10年。湊かなえは、途切れなく作品を発表し、映像化多数。『ユートピア』(15年)で山本周五郎賞受賞。人気と文壇からの評価を併せ持ち、エンタテインメント小説界をけん引する。

『落日』は再生に向かう人たちの物語。鳴かず飛ばずの脚本家の甲斐千尋は、新進気鋭の映画監督・長谷部香から相談を受け、15年前に起きた一家殺害事件を調べ始める。千尋の故郷で起きた事件で、殺された家族は、幼い頃の香と関わりがあった。裁判記録を追うも真実にはたどり着けず、事件の周辺人物と接触しながら真相に迫っていく。
着想は版元社長の角川春樹氏からの「裁判」と、編集担当者からの「映画」だった。"お題"を受け取った湊は、執筆前に初めて裁判所へ足を運び、傍聴をしたという。
「裁判は『真実』を追求する場だと認識していたら、全然違って。『起きた事実を報告し合う場』でしかありませんでした。被告人が殺害したと認め、動機を語ったとします。それは本当にそう思っていたのかよりも『(裁判において)自分の立場を有利に進めるためについてきている感情』である可能性が高い。判決が確定した事件でも、加害者がどう思って罪を犯したのかは分かり得ないと感じました」
「その"実際の感情"の部分を小説は埋められるのではないか。『こんな事情でこう考えていたのではないか?』と、想像する余白がある小説なら、判決が確定している事件でも、真実の色が変わるような何かを提示できると思えました」

2つ目のお題「映画」には、表現者が作品に向かう姿も深く描いた。自分の世界観の中で紡ぐ脚本家・千尋と、人間の表も裏もあぶり出そうとする映画監督・香。事件に迫ることで、それぞれが蓋をしてきた過去も明らかに。当初は互いをいらつかせる存在だった2人の関係が、化学変化を起こしてもいく。2人は売れない脚本家 vs 売れっ子映画監督などと安易な対比では描かれない。湊は登場人物を考える際に「壮大な一代記を描けるぐらいに個々の履歴を作る」というが、今回は「作家の分身のようにしても生まれた」とのこと。
「大切な人を亡くしたとして、真実を知ることが怖くても、例えば、亡くなる前のエピソードとか、自殺ではなかったかもしれないと分かるだけで救いになる。死者が生き返るわけではなくても、生きている人の生き方が変わる。日が沈むからこそ、また昇る。そういう解決方法を提示したかったし、タイトルに込めました」
今年でデビュー11年目。作家を続ける原動力は「ファンでいてくれる方の存在」だと語る。一昨年から全国のサイン会で読者と対面し続けた。
「執筆はいつも夜中。暗闇でマラソンをしているような孤独感だったのが、沿道の応援を受けて走っているよう。力を抜いて書けるようにもなりました」
(日経エンタテインメント!11月号の記事を再構成 文/平山ゆりの 写真/鈴木芳果)
[日経MJ2019年11月1日付]
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。