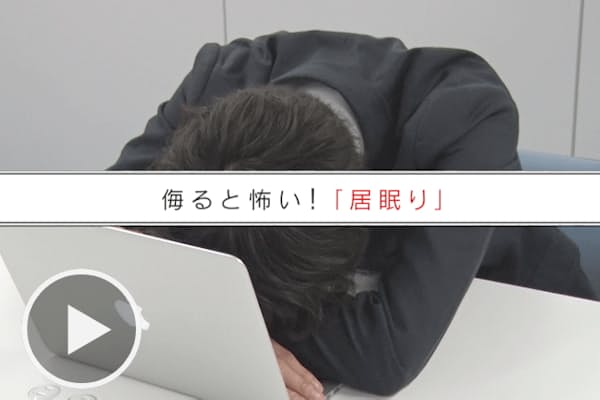同僚の「頭痛」侮らない 痛み別対処、脳卒中の前兆も
産業医・精神科専門医 植田尚樹氏

イラストはイメージ=PIXTA
社員がいきいきと働き、高いパフォーマンスを発揮する職場をつくるには何が必要か。産業医として多くの企業で社員の健康管理をアドバイスしてきた茗荷谷駅前医院院長で、みんなの健康管理室代表の植田尚樹医師に、具体的な事例に沿って「処方箋」を紹介してもらいます。
◇ ◇ ◇
仕事中に頭痛や目まいを覚えても「たいしたことない」と、そのままに放置していませんか。実は頭痛が「脳梗塞」や「くも膜下出血」といった命に関わる病気の前兆であることもあるのです。
激しい頭痛を生じる椎骨動脈解離
産業医として相談を受けたIT系企業に勤める30歳代男性の事例です。
後頭部のしびれと、後頭部の痛み、左足のしびれを訴えていました。就業中、パソコンを操作していたところ、突然の痛みで動けなくなったといいます。すぐに総合病院の脳神経外科で検査したところ「異常なし」との診断されましたが、頭痛は続いていました。
その後、大学病院の脳神経外科を紹介したところ、磁気共鳴血管撮影(MRA)による検査の結果、「椎骨(ついこつ)動脈解離」と診断されました。
「椎骨動脈解離」は、脳梗塞やくも膜下出血の原因のひとつとして注目されている病気です。動脈解離とは、血管の内側が傷つき、血管の壁の中に血液が入り込んで、血管が裂ける症状のこと。首の脊椎骨を通る「椎骨動脈」でこれが起こると、突然の激しい頭痛を引き起こすのです。
この男性は、あやうく血管が裂けて血液が漏れ出す寸前で、くも膜下出血の一歩手前の状態だったといいます。産業医として、3週間休職して自宅で安静するように指示しました。休養後、症状は改善して、現在は問題なく出社しています。
「経験したことがないような頭痛」には即対応を
突然これまでに経験したことがないような激しい頭痛に襲われたらくも膜下出血かもしれません。職場でくも膜下出血を起こした発症した60歳代男性の事例です。
当日、起床したときから頭がボーッとする感じがあったようですが、頭痛はありませんでした。昼休みにトイレに行った直後、頭頂部の下あたりに今まで経験したことがないような痛みを感じたといいます。念のため医務室で血圧を測ると、最高血圧が190mmHgを超えていたため救急搬送されました。頭部CTA(コンピューター断層撮影による血管撮影)検査でくも膜下出血と診断され、すぐに手術を受けることとなりました。退院後は職場復帰し、現在も何の後遺症もなく勤務しています。
激しい頭痛を「異常」と考え、即座に対応したことで、発症から2時間で手術を行うことができました。早期に適切な対処ができたことが、命に関わる大事に至らなかったポイントになったといえます。
頭痛は脳腫瘍の前兆である場合もあります。「モーニングヘッドエイク(早朝頭痛)」といわれますが、早朝や起床したときの頭痛は要注意です。特に吐き気を伴う場合は、脳腫瘍で脳圧が高まっている恐れがあります。