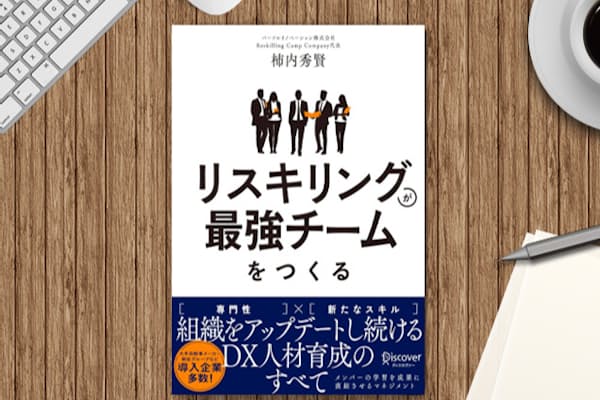怠けていると思わないで 職場が誤解しがちな女性の病
産業医・精神科専門医 植田尚樹氏

写真はイメージ=PIXTA
社員がいきいきと働き、高いパフォーマンスを発揮する職場をつくるには何が必要か。産業医として多くの企業で社員の健康管理をアドバイスしてきた茗荷谷駅前医院院長で、みんなの健康管理室代表の植田尚樹医師に、具体的な事例に沿って「処方箋」を紹介してもらいます。
<< 新人の5月病どう防ぐ 「けちなのみや」でチェック
遅刻常習の同僚からアルコール臭 産業医の提案は… >>
女性の社会進出が進んだとはいえ、従業員の半数以上が男性だという企業がほとんどではないでしょうか。職場での女性の健康管理を考えるうえで、女性特有の事情に対する男性の理解が不可欠といえます。
女性の10人に1人が発症するとされる「子宮内膜症」をご存じでしょうか。子宮以外の場所に子宮内膜と似た組織が増殖して剥離を繰り返す病気で、強い生理痛や腹痛などの症状が特徴です。長年、生理痛を経験しているとその痛みに慣れてしまい、我慢してしまいがちです。すると炎症や癒着がひどくなり、ある日突然、我慢できない激痛に襲われることがあります。
私が産業医として面談したIT企業に勤める30歳代女性の事例です。遅刻や欠勤が多く、勤怠不良ということで人事部から面談を求められました。
話を聞くと、子宮内膜症で婦人科を受診していたのですが、処方された内服薬の副作用に悩まされていました。子宮内膜症による腹痛、それに伴う不眠、不安感、落ち込みなどのメンタル不調を伴っていました。
彼女の場合は、服用することにより、腹痛は軽減したものの、吐気、汗が止まらなかったり、体がだるくて起きられなかったり、目まい、立ちくらみ、感情の不安定、涙もろさも頻繁に認めていました。
難しい治療薬の選択
それまで通っていた婦人科はあまり体調の説明をしても聞いてもらえず、薬についての説明もしてくれないということでしたので、別の病院に通うことを勧めました。病院をかえて、内服薬を変更したことで、今まであった症状は軽快し、出社も問題なくできるようになりました。
婦人科系の疾患は治療薬の選択が難しいことがあります。薬が合わないケースもあります。服用すると吐き気、目まい、頭痛が起きる人もいるので、副作用がなく、その人の体に合う薬を選ぶのに時間がかかる場合があります。
本来の腹痛などの痛みにより、また、薬が合わないために、不眠になり、朝起きられなかったり、不安になったりするほか、落ち込みなどの症状を認めることがあります。それが原因で、勤怠不良とみなされ、昇進・昇格などの評価に影響するようであれば、女性の社会進出の足かせとなる恐れもあります。