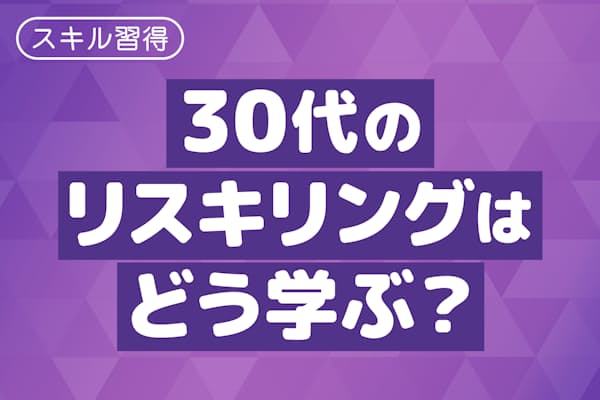理念は話してこそ伝わる ぴあ社長、社員反乱で気づき
ぴあ 矢内広社長(下)

ぴあ 矢内広社長
情報誌に始まり、チケット販売からコンサートなどの興行主催までエンターテインメント事業を拡大させてきたぴあ。ただ、矢内広社長(68)は株式上場後も「ぴあは利益を追求するだけの会社ではない」と創業の理念にこだわってきたという。その大切さに気付いたのは、社員の小さな「反乱」からだった。(前回の記事は「危機で知った『任せて任せず』 ぴあ社長のくじけぬ魂」)
企業理念を明確にするのは社長の責任
――出版もチケットも好調だった1990年代前半、現場の社員が反旗を翻すようなことがあったそうですね。
「95年に、デジタル化が急速に進むなかで『21世紀のぴあのビジョンを考える』という社内プロジェクトを立ち上げました。私から冒頭に目的を説明すると、ある社員が『目的はわかりました。でも社長が考えるようには実現しないと思います』と言うのです。どういうことかと驚きました」
「理由を聞いてみると、『今のぴあには昔のような熱気やチャレンジ精神が薄れている。いくら良い戦略を考えても、実行するのは社員だから実現しない』という。すると他の社員も『隣の部署が何をしているのかわからない』など、会社が病んでいる実態を次々と勇気を持って発言してくれました」
――すでに大企業病の兆候があったということですか。
「そうですね。72年の創業以来ずっと前を向いて走り続けていましたが、後ろを振り返ると、ほとんどの人がついてこられなくなっていたことに気付かされました。その場でプロジェクトの目的を変え、なぜチャレンジ精神を失ってしまったのか、どうやったら取り戻せるのかを考えるプロジェクトにしたのです」
「まずは企業理念をつくるべきだという話になりました。私は正直、『いやいや、ちょっと待って』と思っていました。なぜかというと、毛筆で書かれた社是が額縁に入れられて壁に高々と飾られて、朝礼で社員が唱和するみたいな会社にだけはしたくないと思ってきたからです」
「しかし事業が多角化し、メンバーも部署も増えていくなかで、社員が何をよりどころにして仕事をしていいのかわからなくなってきていた。その原因は、企業理念が明確になっていないからであり、それは社長の責任だと、はっきり言われました」