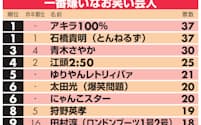社員の幸福が経営を左右 ときめかない仕事は捨てよう
前野隆司慶応義塾大学大学院教授(上)

近年の研究の結果によると、幸福な社員は不幸な社員に比べて、創造性や生産性が明らかに高いという。企業はどうすれば社員を幸福にできるのか。日本における「幸福学」の第一人者で、「幸せの経営学」をテーマに企業組織の幸福度を上げるためのコンサルティングも手がける、慶応義塾大学大学院の前野隆司教授に伺いました。
幸せな社員は創造性が3倍高い
白河桃子さん(以下敬称略) 前野先生はキヤノン勤務、ハーバード大客員教授を経て、現在は慶応義塾大学大学院でイノベーション教育の研究に携わっていらっしゃいます。専門領域は企業も注目し始めた「幸福学」。最近、『幸福学×経営学』(内外出版社)という共著も出されました。まずお伺いしたいのは、幸福と生産性の関係について。これまでどんなことが分かってきているのでしょうか?
前野隆司さん(以下敬称略) 国内外でいろんな研究が発表されていて、例えば米カリフォルニア州立大学のリュボミアスキー教授は「幸せな社員は不幸せな社員より生産性が1.3倍高い」というデータを出しています。国内では「ハピネス計測」の技術開発をしている日立製作所の矢野和男さんの研究をはじめ、やはり幸せであることは生産性を30%ほど増やすといわれていますね。また、これも米国の研究ですが、「幸せな社員は不幸せな社員より創造性が3倍高い」という結果も出ています。

白河 3倍ってすごいですね。
前野 創造性に差が出るということは、定型作業(ルーティンワーク)ではなく、非定型な創造性を発揮できる仕事でより幸福度が影響するということでしょう。
白河 工場労働者よりも、知的生産に従事するナレッジワーカーが増えている今の時代においては、「社員の幸福度を上げる」ことが、経営者にとってお得だということですね。
前野 ナレッジワーカーは幸せに働かなければ効率的に生産性が上がらないのだと知っておくべきですね。さらに、企業研究会という団体が行った調査によると、「定型作業をしている人より、非定型の仕事をしている人の方が幸せ度が高い」ということが分かりました。やはりこれからは、できるだけ定型作業を人工知能やロボットに置き換えて、人間は非定型作業で創造性を発揮すると、幸せ度も高まり、かつ創造性・生産性も高まっていくのだと思います。
白河 イノベーション経営と社員の幸福度は切っても切れないものだと。そして、仕事の種類そのものを、幸福度を高めるものへとシフトしていったほうがいいということですか?
前野 はい。高度経済成長期はピラミッド型の製造業大企業型の経営が中心で、「とにかく同じ型の冷蔵庫をたくさん作りましょう」という仕事の仕方さえすればもうかったわけです。でも、今は皆テレビも冷蔵庫もすでに持っているのですから、働き方そのものも変えないといけない。
人工知能(AI)の機械学習の世界なんて、たった1週間で主役が変わってしまうほどの猛スピードで業界が動いているんですよ。こんな時代に、ピラミッドのてっぺんから「えー、わが社の今期の方針は~」なんて悠長に言っていると負けてしまいますよね。組織を構成する一人ひとりがいかに創造性を発揮して働くか、という時代に来ているんです。つまり、時代が求める経営の流れと個人の生き方を満たす幸せのあり方が一致し始めてきたということです。
白河 経営と働く人の幸福の一致、すごくいい流れになってきたんですね。
前野 そう思います。逆に言うと、社員に不幸せな働き方を強いている企業は、社員も不幸だし、利益も出ない。最悪です。
白河 「会社のために我慢すれば給料は上がるから」と滅私奉公する時代は過ぎ去ったというわけですね。この最近の人事のトレンドを見ていても、あきらかに「人を管理する」から、より個人をエンパワーメント(能力開花)するにはどうしたらいいかという方向に変わってきていると思います。
前野 おっしゃるとおりで、早く乗り換えないと大変なことになります。すでに破綻しかけている企業はいくつもあると思います。
高度な知識を使う定型作業は通用しない
白河 中小企業のほうがフットワーク軽く、思考をシフトしている印象があります。大企業はどうしても遅れてしまうみたいで、仕事の中身はナレッジワークのはずなのに働き方や人事管理は定型作業のままになってしまっているところが多い気がします。

前野 獲得してきた高度な知識を使ってやる定型作業、みたいになっていますよね。でも、それでは通用しない時代がやってきた。
白河 一刻も早く企業は社員の幸福な働き方を設計しなければならないということが明らかになってきたわけで、社員の幸福度を上げるための手段として「働き方改革」は機能する可能性はありますよね。
でも、実は「ビジョンなき働き方改革」が横行してしまっているのではないか?というのが、私が抱いている危機感です。「残業時間が減りました!」「カッコいいオフィスを作りました!」といった数字や目に見えやすい形での改革ばかりが先行しているというか。
前野 それ、改革じゃないですよね。できることからやろう、というレベルは「改善」止まりです。ほとんどの会社のやり方は間違っていると思います。
白河 中には残業時間を減らす第1フェーズは成果を上げ始めた企業もちらほら出てきているんです。婚活女子から「白河さん、働き方改革、進んでいますよ。大手勤務の40代ぐらいの見合い相手が5時に会いましょうというんです」ですって(笑)。これはこれでいいことかもしれませんが、そろそろ第2フェーズの「その先に生み出す価値を高める」という本質的な改革まで進まないと意味がないと思っているんです。
前野 残業時間を減らす成果がそれほど出ているとはちょっと意外ですね。ただ、本当に無理のない形での残業圧縮になっているかどうかは注視しないといけないですよね。単純に無駄な作業を省いて「やればできたじゃん」という成果ならいいのですが。
白河 根本的に人が足りていなかったり、仕事全体の設計そのものに無駄が多過ぎる場合には、むやみに残業削減をするだけでは無理が生じますよね。
前野 かえってゆがみが生じているのではないかと心配ですね。頑張ってやっても22時までかかっちゃう仕事を17時までに終わらせようとすると必ず負荷がかかるので、ストレスが増大し、社員は不幸になってしまいます。すると、創造性や生産性も低下する。辻つま合わせのような働き方改革は意味がないどころか、危険だと思います。

掛け声は「楽しく働こう!」
白河 先生から見て、企業が社員の幸福度を上げるためにやるべき行動ってどんなものですか?
前野 そもそも「生産性を上げろ」なんて言わないことでしょうね。生産性を上げるために無理をさせてしまうと、ストレスが増してしまうのですから。生産性はあくまで結果でしかなく、最初の掛け声はやっぱり「楽しく働こう!」ですよ。たとえ無駄があってもいいから、生産性のことは忘れてとにかく楽しく働いてみる。すると、創造性が3倍になり、生産性は1.3倍になるわけですから、いつの間にか10時間かかっていた仕事が7時間になっちゃうわけです。
白河 たしかに順番をよく考えないといけないんですね。
前野 短期的な生産性だけを目指していてはダメ。詰め込むと短期的には業績が上がるかもしれないけれど、そこに負荷が生じていたら、結局その後に長期休暇を取らなければいけなかったりして長期的には生産性が下がることだってあり得ますよね。もしも「これまでの働き方改革は短期視点に偏っていた」と気づいたとしたら、今からでも遅くないので180度方向転換したほうがいいと思いますね。
白河 サイボウズ社長の青野慶久さんも「仕事が楽しくないのはなぜだろう?」と提起されていましたが、やはり「楽しく仕事をする」を起点にすることが重要なんですね。
前野 そうです。やっぱりワクワクしながら働くことが大事。片づけコンサルタントの近藤麻理恵さんが「ときめかないものは捨てましょう」とおっしゃっていたのと同じで「ときめかない仕事は捨てましょう」と言いたいです(笑)。
白河 本当に捨てちゃっていいんですか(笑)? すごく面倒な仕事もありますけれど。私の場合、マイナンバーの書類の提出とかすごく嫌いです。
前野 あれも国がしっかりと投資して不正が生じないシステムを整備すれば、アメリカのソーシャルセキュリティーナンバーのように国民全員が特に個人情報だと気にせずに取り扱え、無駄が省けるわけですよね。要するに、「人を疑うこと」が前提になっている社会は生産性を落とすんです。
白河 ああ、確かに。テレワークを導入すると部下がサボるんじゃないか、と疑心暗鬼になっている上司とかいますよね。
前野 僕から言わせれば、その上司の心の中に「サボりたい」気持ちがあるだけ。究極的には人を信じるしかないんですよね。企業訪問を続けていますが、やはり社員が幸せな会社というのは、トップが現場に権限を委譲して完全に任せているところが多いですよね。「ホウレンソウ(報告・連絡・相談)」を禁止した未来工業さんしかり。「かんてんぱぱ」で有名な長野県の伊那食品工業さんなんて、経費精算は領収書をバサーっと出すだけで承認されちゃうんですよね。社員を徹底的に信じているし、信頼に基づく経営であることをしっかり教育しているから、社員も皆いい人なんですよ。
白河 伊那食品工業さんは私も見学に行かせていただいたことがあるのですが、社員一人ひとりが本当に誇りを持って働いているんだなということが伝わってきました。社員の皆さんが清掃しているという敷地もとてもきれいで。他にもモデル企業はありますか?
前野 自動車用のネジを作っている西精工という会社も素晴らしい取り組みをしています。感心したのは毎朝、朝礼に1時間かけて、会社の理念や「自分たちの仕事がどう社会に役立っているか」を共有しているんです。朝礼に1時間って、一見無駄のように感じますが、全然無駄でなくて、「このネジ1本で世界中の車がちゃんと走って、たくさんの人を幸せにしているんだ。俺たちすげー!」ってワクワクしながら働くための原動力になっているんです。形式だけに走ると「朝礼を削減」とかになりがちですが、やはり本質を見失っちゃいけないなと気づかされましたね。
(以下、下編の「きれい事でも… 社員の幸せ考えるのが経営者の役割」に続く。下編では幸福度を上げるために社員自身、管理職や企業はどうすればいいかをお聞きします。)

(ライター 宮本恵理子)
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。
関連企業・業界