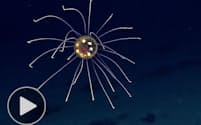クラゲ この美しく奇妙で多様な生物
数億年前から水中を浮遊するクラゲ。ナショナル ジオグラフィック2018年10月号の「魅惑のクラゲ」では、『6度目の大絶滅』でピュリツァー賞を受賞したことで知られるエリザベス・コルバートが、この謎めいた生き物を取り上げた文を寄せている。山形県の鶴岡市立加茂水族館で撮影取材したデビッド・リトシュワガーの美しいクラゲの写真とともにお届けしよう。
◇ ◇ ◇
世界各地の水深の浅い入り江に生息するミズクラゲは、小さいがお化けのようで怖い感じだ。透明な傘の下から淡い水色の触手が伸びたミズクラゲが、体を拍動させて水中を浮遊する様子を見ていると、まるで海水そのものが生きているように思えてくる。
米国メリーランド州ボルティモアにある国立水族館では、来館者がミズクラゲに触れる機会を設けているが、最初は怖がって誰も手を出そうとしない。このクラゲは痛くないから大丈夫だと言われて初めて、来館者は恐る恐る水槽に手を伸ばすのだ。
「ぐにゃぐにゃしてる!」「冷たい!」子どもたちから歓声が上がる。「クラゲは本当に魅惑的な生き物だと思います」と、クラゲの飼育を担当するジェニー・ジャンセンは話す。
ゼラチン質の体以外は共通性がない
不気味、ぐにゃぐにゃ、冷たい、脳がない、魅惑的……。クラゲの不思議さを言葉で表現するのは難しい。体の構造を見ると、脳ばかりか血液も骨格もなく、原始的な感覚器官しかない。そして、分類学的に見ると、クラゲは種類の異なるいくつかのグループに分けられる。
「クラゲ」と総称される生き物は、互いに近縁関係にないものが多い。生物の系統樹において完全に異なる系統に分類されていて、生息する環境もさまざまだ。海面近くを好むクラゲもいれば、深海に生息するもの、さらには淡水域で暮らすクラゲまでいる。こうした異なる生き物をひとくくりに「クラゲ」と呼んでいるのは、ひとえに、水中を浮遊して生きていくのに適した進化を遂げた点で共通しているからだ。それが、ゼラチン質の体だ。
当然のことだが、進化の過程がまちまちなため、クラゲの体の形や大きさ、生態は実にさまざまだ。繁殖方法に関して、刺胞動物のクラゲは多様性を誇り、有性生殖でも無性生殖でも繁殖できる。有性生殖では、受精卵は「プラヌラ」と呼ばれる幼生となり、岩などに付着してイソギンチャクのようなポリプになる。
ポリプの無性生殖の方法には、種類によって、2つに分裂する方法もあれば、組織塊から増える方法、さらには「横分体形成」と呼ばれるプロセスを通じて微細な雪の結晶状のクローン(エフィラ)を遊離する方法もある。
そして、何よりも驚くのは、死んだ後にポリプになる――つまり若い段階に再生するクラゲがいることだろう(この奇跡のようなプロセスを、研究者たちは「分化転換」と呼ぶ)。
ミズクラゲやキタユウレイクラゲ、オキクラゲ科のシーネットルなどは、分類上、同じ「綱」に属し、「真正クラゲ」とも呼ばれる。これらは、サンゴに代表される「刺胞動物門」のうちの「鉢虫綱」に分類され、成長した姿は、伏せた皿や膨らんだパラシュートのような形だ。
鉢虫綱のクラゲは傘の筋肉を収縮させて拍動しながら進み、とげの付いた微細な刺糸を触手の刺胞から発射し、水中を浮遊する獲物に毒を注入して捕獲する。獲物を口に入れる際は口腕と呼ばれるリボン状の付属器官を使う。なかには口腕に口が付いているクラゲもいる。
カツオノエボシは群体
猛毒をもつことで恐れられるカツオノエボシは、刺胞動物門のヒドロ虫綱クダクラゲ目に分類されている。カツオノエボシは1つの個体のように見えるが、実は同じ受精卵から発達した多数のヒドロ虫が集まった群体なのだ。受精卵は単に大きく成長するのではなく、さまざまな機能をもつ新しい「体」をいくつも生み出す。たとえば、成長して触手になるものもあれば、生殖器を形成するものもあるという具合だ。
有櫛動物門に属するクラゲは、それ自身で独立した門を形成する変わり種だ。このクラゲは、「櫛板」と呼ばれる体表を覆う櫛状の繊毛をゆらゆらと動かして泳ぐことからクシクラゲとも呼ばれ、体はさまざまな奇抜な形をしている。平たいリボン状の体をしたものもいれば、小さな袋や王冠のような体をしたものもいる。クシクラゲの大半は獲物を捕まえるのに粘着性のある物質を使う。「クシクラゲの触手には、膠胞という接着剤を詰めた袋のようなものがいくつもあるんです」と、米モントレー湾水族館研究所のスティーブ・ハドックは言う。
(文 エリザベス・コルバート、写真 デビット・リトシュワガー、日経ナショナル ジオグラフィック社)
[ナショナル ジオグラフィック 2018年10月号の記事を再構成]
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。