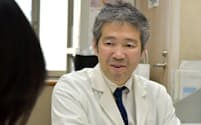対話から生き方を問い直す がん患者向けの哲学カフェ

がんや難病患者とその家族を対象に、お茶を飲みながら身近なテーマについて対話する「おんころカフェ」が、大阪を拠点に開催されている。近年、がんの悩みや不安を患者本人と家族、医療者が語り合う場が全国的に増えつつあるが、おんころカフェは哲学者を中心とした進行役のもと、話を掘り下げる「哲学対話」の手法が用いられる。「哲学」という名前が付くが、哲学の知識はまったく必要ない。自身もがんを経験しているライターがおんころカフェに参加。直視しにくい死やいかに生きるかを考える時間となった。
「おんころのたね」で気持ちをほぐし対話へ
この日は、大阪大学最先端医療イノベーションセンター(大阪府吹田市)2階の会議室に、がん患者や看護師、哲学対話研究者ら10人が集った。お菓子がテーブルに並び、お茶は各自が持参。がんや難病患者とその家族だけでなく、医療者、哲学対話研究者も参加できる。参加費は無料で予約は必要ない。
まず、「おんころカフェ」を運営する一般社団法人哲学相談おんころの代表理事で進行役を務める哲学者の中岡成文さんが、参加者の気持ちをほぐすため、「おんころのたね」と称する話題を提供する。語り合うときの発想のヒントになりそうな言葉を紹介するもので、対話のテーマとは直接関係がない。今回の「たね」は「笑ってあげる」。マザー・テレサの言葉として知られる「笑ってあげなさい。笑いたくなくても笑うのよ。笑顔が人間に必要なの」などの言葉を伝えた。
いつもはこの後、「今日のテーマは〇〇でお願いします」という中岡さんの言葉で対話が始まる。例えば「愛」「自分らしさ」「遠慮」など身近なテーマを進行役が選び、当日に発表する。病気にちなんだテーマでなくても、対話が進むうちに毎回、生きることを考える内容になっていくという。ただ、今回は例外でテーマを決めないことに。「笑ってあげる」のたねの話を深めることになった。
病気とは関係のないテーマから生死を考える話に
「『笑ってあげなさい』という言葉は、上から目線で言われているようにも受け取れ、反発を覚える人もいるかもしれません。皆さんはどのように思われますか」と中岡さんが発言を促す。
運営メンバーの一人で、哲学対話コーディネーターの佐野桂子さんは「笑うことには、ほほ笑むことと、ワッハッハと笑うことの2種類があります。マザー・テレサが言っているのはほほ笑む方で、こちらには人を癒やす力があると思います」と語った。
参加者がそれぞれに思うことを話し、他の人はじっと耳を傾ける。そして、「医療者が患者に与える笑顔」についての話題に。希少がんを経験した60代の男性会社員は「自分が一番に求めるのは、笑顔よりも話をしっかり聞いてくれる医師や看護師です」と話した。
中岡さんは話の流れを遮らないようにしながら、開業医だった自身の父の患者への接し方を紹介。その辺りから別のがん患者が、死への不安を吐露し始めた。死をどのように考えればいいのかという、正解のない深い問いに皆が思いを巡らせ、発言したり、人の話を聞いたりした。
「おんころカフェでは結論を出すことはしません。死や生について考え、対話することで、それぞれの方の何かの気付きにつながればと思います」と言って中岡さんは会を閉じた。
がんで家族を亡くした2人が出会い始まった「おんころカフェ」
おんころカフェが始まったのは2016年5月。家族をがんで亡くした経験のある中岡さんと佐野さんが、哲学の勉強会で出会ったのがきっかけだった。がんや難病患者とその家族を対象に「哲学対話」(哲学カフェともいう)を開くことにしたのだ。オンコロジー(腫瘍学)に由来し、おんころカフェと名付けた。

「もともと哲学対話は、1998年に大阪大学大学院文学研究科に発足した『臨床哲学研究室』で始めた取り組みです。私は同僚だった哲学者・鷲田清一さんとともに、研究室の創設に関わりました。臨床哲学は決まった定義のある学問ではないのですが、『書を捨てて町に出よう』という精神で社会の現場に赴いて人々の苦しみに関わります。例えば、ホスピスの関係者とコンタクトを取り現場に入って研究した院生がいますし、2001年に大阪で開かれた日本ホスピス・在宅ケア研究会(医療・福祉従事者や市民ががん、在宅ケアなど医療・福祉の諸問題を考える会)の全国大会で哲学対話を行いました」(中岡さん)
臨床哲学研究室が誕生した年に、中岡さんは離れて暮らす父を胃がんで亡くした。「その年の3月に訪ねたときは体がとても弱っていて。死が近づいているのに父と有意義な会話ができず、テレビの相撲中継をぼんやりと見て過ごしました。家族だからこそ父の苦しさがよく分かり、なかなか話を切り出しにくかったのです。当時は仕方がないと考えていましたが、これでよかったのだろうかという後悔が、潜在的にずっとあったと思います。3年ほど前に佐野さんと出会い、話をするうちに、私たちで哲学対話を始めましょうということになりました」
一方佐野さんは、10年前に父が余命2カ月の腎がんと診断され、その後亡くなった。「当時、病院の中に相談できる窓口はなく、診療以外に声をかけてくれる医療者もいませんでした。私と母は決めなければいけない医療的・事務的な事柄に追われ、本当に孤独で苦しい日々を送っていました。ですから、私も当事者であることを実感しながら、おんころカフェに参加しています」と話す。
がんになり変化した生き方を対話で立て直す
おんころカフェは進行役が重要な役割を果たす。中岡さんのように発言を促したり、話の流れが脱線しないように導いたりするには、哲学対話の豊かな経験が必要だ。
「私は患者さんや家族の経験、感情を尊重し、自分の言葉で自然に表現してもらえるように努めています。対話に介入する姿勢は取りませんが、参加者が話した言葉の中で、皆さんに注意を向けたいところをフォーカスして伝えることはあります。そのような言葉には哲学でいう普遍性があり、他の参加者にも意味を持つ内容になるからです。とはいえ、必ず発言する必要はなく、聞いているだけでも構いません。積極的な発言を希望しますが、沈黙してじっくり考えることも大切にしています」(中岡さん)
では、がんや難病患者に、なぜ哲学対話が必要なのだろうか。
「死に直面するような病気を経験した人は、社会や仕事に対する価値観が変わり、セルフイメージも変化し、自分の生き方を再構築することが必要になってきます。そのときに、人間は何のために生きているのか、死とは何かという問いは、ごまかさない限り普通に出てくるでしょう。そうした問いにしっかりと向き合うことで、生き方の立て直しができると思います。生き方を再構築するには、安心できる環境で対話することが有益だと考えます」と中岡さんは話す。
音楽を活用した哲学対話も検討中
おんころカフェは基本的に、毎月第2金曜の午後5時30分~と第4土曜の同2時~、大阪大学最先端医療イノベーションセンター2階の会議室で開催している(2018年9月のみイレギュラーで第4土曜がなく15日(土)同2時~)。所要時間は約2時間。不定期だが東京でも開いている(スケジュールはホームページまでhttps://oncolocafe.com/)。
対話の際に発言した、希少がんを経験した男性会社員は、敷地内にある大阪大学医学部附属病院に入院していたことからおんころカフェを知り、度々訪れている。「ここはがん経験者以外にも色々な人が参加します。話の内容が豊富で勉強させてもらっています」と話す。
「今後は、音楽を活用した哲学対話も考えたいと思っています。歌詞もそうですが、メロディーが支えになるという人もいますから。話すことが苦手でも、好きな曲や心に残る音楽を通してなら、何らかの表現ができるかもしれません。また、出張おんころカフェのように、対話を必要とする人に届くような活動も検討していきたいです」(中岡さん)
同じ病気を経験した患者やその家族が集う患者会は全国各地にあるが、おんころカフェのようにがん患者が死について深く踏み込んで語り合える場を私は初めて知った。
私自身、がんと告知されたときは、はるか遠くにあった死が、突然、すぐ近くにやってきたように感じ、眠れない日々を過ごした。対話に参加して、「死は怖いけれど、そこに意識を持っていかず、毎日の小さな幸せに目を向けるようにしている」と発言。がんになった後、完治するのか先が見えない不安の中にいたが、年月を経て、自分の生き方を立て直せていることに気付いた。
がんになった人にとって生死を深く考えることは、死の恐怖を経験しているだけに苦しさがあるかもしれない。しかし、死や生とは何かという問いに向き合って出てくる言葉は、自分自身を支えているように思う。
(ライター 福島恵美 ※悪性リンパ腫を経験、カメラマン 水野浩志)

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。